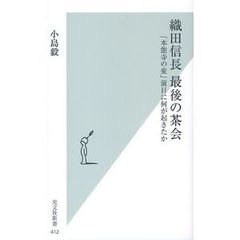「細川家家臣略歴」や「先祖附」では長瀬氏とされているが、「肥陽諸士鑑」では永瀬氏との表記がある。その家祖は志水宗加入道清久である。清久の三男・雅楽の子牛之介が江戸に赴く時舟の事故で亡くなり、嫡子新九郎が家督したが「不満・若年絶家」し、妹蝶の壻・長瀬助之丞がこれを継ぐことが許され、あに新九郎の三百石を家禄とした。
宗加
---+--志水清久---+--九左衛門---次郎兵衛(九兵衛)===久馬・・・・・→凍家
| |
| |日下部与助
| +--元五---+--新之允・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→新九郎家(嫡家)
| | |
| | +--権之助・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→隼太家
| | |
| | |新之丞克重
| | +==恵重---吉之允・・・・・・・・・・・・・→源九郎家
| | | ∥
| | | 圓光院(筑紫重門・細川幸隆女兼夫婦の女)
| | |
| | +--久馬(九兵衛為養子)
| |
| | 雅楽 牛之介
| +--恵之---+--元茂--+--新九郎
| | | |
| | | +--●蝶(兄・新九郎跡目相続)
| | | ∥・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→長瀬家
| | | 長瀬助之允
| | |
| | +--恵重(元五為養子)
| |
| +--要善院日富 志水家菩提寺・真浄寺創建
|
| 志水清久・子
+--悪兵衛清秀======加兵衛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→八代松井家家臣・志水家
志水雅楽
志水牛之助
1、助之允 (1)御詰衆 三百石 (真源院様御代御侍名附)
(2)三百石 (真源院様御代御侍免撫帳)・・永瀬助丞
(3)有吉頼母允組 三百石 (寛文四年六月・御侍帳)・・永瀬助丞
細川光貞公宛行状(寛永十八年)三百石 永瀬助丞宛
2、助左衛門 御詰衆・九番佐久間平右衛門組 三百石 (御侍帳・元禄五年比カ)
3、助之進 著作:長瀬助之進覚書(一名:妙応院様御備頭え御茶被為頂戴節御意之覚)
4、助左衛門・正勝(初・弁之助)
5、助左衛門(養子 喜平太・正遊) (1)八百石 御側御中小姓 屋敷・手取
(2)御長柄頭 八百石
以下略
宗加
---+--志水清久---+--九左衛門---次郎兵衛(九兵衛)===久馬・・・・・→凍家
| |
| |日下部与助
| +--元五---+--新之允・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→新九郎家(嫡家)
| | |
| | +--権之助・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→隼太家
| | |
| | |新之丞克重
| | +==恵重---吉之允・・・・・・・・・・・・・→源九郎家
| | | ∥
| | | 圓光院(筑紫重門・細川幸隆女兼夫婦の女)
| | |
| | +--久馬(九兵衛為養子)
| |
| | 雅楽 牛之介
| +--恵之---+--元茂--+--新九郎
| | | |
| | | +--●蝶(兄・新九郎跡目相続)
| | | ∥・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→長瀬家
| | | 長瀬助之允
| | |
| | +--恵重(元五為養子)
| |
| +--要善院日富 志水家菩提寺・真浄寺創建
|
| 志水清久・子
+--悪兵衛清秀======加兵衛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→八代松井家家臣・志水家
志水雅楽
志水牛之助
1、助之允 (1)御詰衆 三百石 (真源院様御代御侍名附)
(2)三百石 (真源院様御代御侍免撫帳)・・永瀬助丞
(3)有吉頼母允組 三百石 (寛文四年六月・御侍帳)・・永瀬助丞
細川光貞公宛行状(寛永十八年)三百石 永瀬助丞宛
2、助左衛門 御詰衆・九番佐久間平右衛門組 三百石 (御侍帳・元禄五年比カ)
3、助之進 著作:長瀬助之進覚書(一名:妙応院様御備頭え御茶被為頂戴節御意之覚)
4、助左衛門・正勝(初・弁之助)
5、助左衛門(養子 喜平太・正遊) (1)八百石 御側御中小姓 屋敷・手取
(2)御長柄頭 八百石
以下略