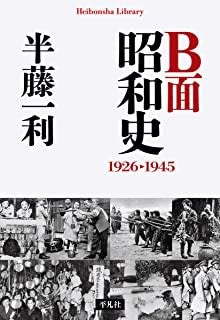相変わらずの読書三昧、と言いたいところですが。ついつい緊急事態宣言下でも出かけてしまい、・・・。少し自重して。
さて、今年1月亡くなられた半藤一利さん。ブログでも何度か紹介していますが、下町・大畑(現在の八広)生まれということで、けっこう親近感を持っています。生家は、通称「こんにゃく稲荷」・三輪里稲荷神社の前だったとか。
この本が世に出たのは、2016年2月。それから3年後。平凡社ライブラリー版として発刊されました。
『昭和史1926―1945』がA面としたら、この書は、戦前の市井の生活を描いたもの。
半藤さん自身は、1930年(昭和5年)生まれですから、生まれる前から昭和が始まっています。小学校(国民学校)から府立7中(現隅田川高校)に進学、1945年(昭和20年)3月10日の東京大空襲で九死に一生を得て、茨城・下妻、さらに父の生地である長岡へ、というまさに時代に翻弄されつつ、少年・青年期を送って来た方。
「60年近く一歩一歩、考えを進めながら、調べてきたことを基礎として書いた本書の主題は、戦場だけでなく日本本土における戦争の事実をもごまかすことなしにはっきりと認めることでありました。民草の心の変化を丹念に追うということです。昔の思い出話でなく、現在の問題そのものを書いている、いや、未来に重要なことを示唆する事実を書いていると、うぬぼれでなくそう思って全力を傾けました。」
「・・・レコードには主となるA面と裏側に従となるB面とがありました。それにならえば、昭和史も政治・経済・軍事・外交といった表舞台をA面、そしてそのうしろの民草の生きる慎ましやかな日々のことをB面と呼んでも、それほどおかしくないと勝手に考えました。」
「誰の名言であるか忘れましたが、『戦争はうその体系である』というのがあります。その名言にそっていえば、わたくしは物心ついてから15歳まで、その『うその体系』のなかで生きてきました。その後の70余年の平和は、そのことをじっくり考えさせてくれました。」
文庫本でも650Pになりますが、じっくり読んでほしいと思います。
巻末に載せられた、同年生まれの澤地久枝さんとの対談もすばらしい内容です。
今回読み進めていくうちに、意外なことに気づきました。戦後生まれ、半藤さんよりも15年以上、年が離れている小生。
当時、大いにはやった流行歌、また軍歌などが載せられていますが、けっこう知っている(歌える)ものが多いことに。
そのいくつかを。
・昭和4年(1929年)『東京行進曲』♪昔恋しい銀座の柳 仇な年増を・・・
「その第4連の出だしは♪シネマ見ましょか お茶のみましょか いっそ小田急で逃げましょか・・・と実はもともとの歌詞は♪長い髪してマルクス・ボーイ 今日も抱える『赤い恋』・・・であった。」
・昭和5年(1930年)
浅草のエノケンの舞台ではやったのは『洒落男』♪俺は村中で一番 モボだと云われた男 己惚れのぼせて得意顔 東京は銀座へと来た
注:「モボ」(「モガ」という語もあります)「モダンボーイ」に「モダンガール」のこと。
・同じく『デカンショ節』♪俺らが怠けりゃ 世界は闇よ ヨイヨイ 闇に葬れ資本主義 ヨーイヨーイデッカンショ
昭和6年(1931年)
・『酒は涙か溜息か』♪酒は涙か溜息 こころのうさの捨てどころ とおいえにしのかの人に 夜毎の夢の切なさよ
・『侍ニッポン』♪人を斬るのが侍ならば 恋の未練がなぜ斬れぬ
昭和7年(1932年)
・『天国に結ぶ恋』♪ふたりの恋は清かった 神様だけがご存じよ 死んで楽しい天国で あなたの妻になりますわ
注:この歌は知りませんでした。「坂田山心中」事件にからむ歌。
昭和8年(1933年)
・『島の娘』小唄勝太郎の名調子で♪ハアー島で育てば 娘16恋心 人目忍んで 主と一夜の仇なさけ
注:この年、大島三原山が投身自殺の名所になった。
・『東京音頭』♪ハア踊りおどるならチョイト東京音頭ヨイヨイ 花の都花の都の真ん中で サテヤートナソレヨイヨイヨイ
注:日比谷公園では、1週間ぶっ通しで踊り、日本中の神社や境内、公園、空き地で人波が大きな輪をいくつもいくつもつくって踊り狂った、という。
今は、「ヤクルトスワローズ」の応援歌? となっています。
昭和9年(1934年)
・『さくら音頭』♪ハアー咲いた咲いたよ 弥生の空に ヤットサノサ
注:前年の「東京音頭」につづく「音頭」。お分かりのように、出だしが「ハアー」となっていて、「島の娘」で大受けして、「歌い出し」としてはやった。
昭和10年(1935年)
『二人は若い』♪あなたと呼べばあなたと答える 山のこだまのうれしさよ 「あなた」「なんだい」 空は青空 二人は若い
昭和11年(1936年)
・『うちの女房にゃ髭がある』♪何か言おうと思っても 女房にゃ何だか言えませぬ
・『あゝそれなのに』♪空にゃ今日もアドバルーン さぞかし会社で今頃は
・『花嫁行進曲』♪髪は文金高島田・・・みなさんのぞいちゃいやだわよ
・『花言葉の唄』♪可愛い蕾よきれいな夢よ 乙女ごころによく似た花よ
こうして挙げていくと、まったく戦後生まれの小生ですが、TVなどの「懐メロ特集」かなんかで耳に残っているのかも知れません。知らない歌もありますが。
しかし、A面では昭和11年(1936年)2・26事件を契機に一段と軍部支配が強固になり、次第に戦争体制の気配が色濃く、思想統制・弾圧も激しくなり、市井の生活にも次第に窮屈になってきます。
 2・26事件。
2・26事件。