
時・空を、あるいは人称を越えた語り口。これが、この方の小説作法なのだろう。夢うつつ、その端境に聞こえる声、声、声・・・。鳥の、赤子の、老人の、両親の、兄弟の、・・・。そして、晩鐘の。否、外界の音だけではない、自らの内から聞こえてくる音。これらの深みに対しては、彩りをなす花々は、どれもこれも「淡い」イメージ、もっといえば、セピア色、さらにいえば、無色透明さえも感じ取らせる。
死者は、息を引き取る際、五感のうちの聴覚が最後まで残っていると聞いたことがある。生者と死者との交流は声をもって終わりとなすか。そして、さまざまな、肉親を含めて人間を看取る主人公。いつか自分も。
老いてますます研ぎ澄まされる聴覚、そして視覚、嗅覚、・・・五感。身体へ心へ染み渡り、醸し出される、不思議(思議せず)な「小説」世界。登場人物たちは、自在に己の世界を紡いでいく、その語り部としての作者に徹底する姿勢は、読者をうならせる魅力にあふれている。
「窓の内」から始まる八つの連作。騒然と、何かにせかされるように生きる(しかない)現代人に静寂をかぎ取る感性というものの豊かさを気づかせる見事な語り口でした。
「鐘の渡り」。3年ばかり暮らした女をついふた月ほど前に亡くした友人に誘われて晩秋の山にでかける男。自身は春には女と暮らすことになるだろうと思っている。
「―鐘の音に目を覚まして、ひさしぶりにぐっすり眠った気がした。思うことも尽きたように鳴り止んだ。明日からは物も考えなくなるだろう。」
山から帰った晩、女の部屋を訪ね、目の前の女にのめりこんでいく男。山で聞いた鐘の音は二人の幻聴だったのか、とも。
「朝倉のつぶやきが隣でまどろむ自分の内に鐘の音を想わせ、余韻の影を追いきれなくなり目をさました自分の声が朝倉の内に、幻聴ながらおそらくくっきりとした、鐘の音を響かせた。これはつかのまながら交換になりはしないか。暮らした女を亡くした男と、これから女と暮らす心づもりの男との間の。」
こうして、幽冥の世界が描き出される。過ぎ去った者の生の声、声、声。連作を通して通奏低音のごとくに響いてくる。
死者は、息を引き取る際、五感のうちの聴覚が最後まで残っていると聞いたことがある。生者と死者との交流は声をもって終わりとなすか。そして、さまざまな、肉親を含めて人間を看取る主人公。いつか自分も。
老いてますます研ぎ澄まされる聴覚、そして視覚、嗅覚、・・・五感。身体へ心へ染み渡り、醸し出される、不思議(思議せず)な「小説」世界。登場人物たちは、自在に己の世界を紡いでいく、その語り部としての作者に徹底する姿勢は、読者をうならせる魅力にあふれている。
「窓の内」から始まる八つの連作。騒然と、何かにせかされるように生きる(しかない)現代人に静寂をかぎ取る感性というものの豊かさを気づかせる見事な語り口でした。
「鐘の渡り」。3年ばかり暮らした女をついふた月ほど前に亡くした友人に誘われて晩秋の山にでかける男。自身は春には女と暮らすことになるだろうと思っている。
「―鐘の音に目を覚まして、ひさしぶりにぐっすり眠った気がした。思うことも尽きたように鳴り止んだ。明日からは物も考えなくなるだろう。」
山から帰った晩、女の部屋を訪ね、目の前の女にのめりこんでいく男。山で聞いた鐘の音は二人の幻聴だったのか、とも。
「朝倉のつぶやきが隣でまどろむ自分の内に鐘の音を想わせ、余韻の影を追いきれなくなり目をさました自分の声が朝倉の内に、幻聴ながらおそらくくっきりとした、鐘の音を響かせた。これはつかのまながら交換になりはしないか。暮らした女を亡くした男と、これから女と暮らす心づもりの男との間の。」
こうして、幽冥の世界が描き出される。過ぎ去った者の生の声、声、声。連作を通して通奏低音のごとくに響いてくる。










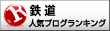
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます