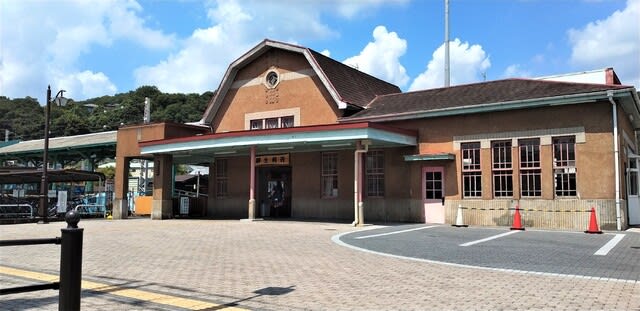大網駅まで再開。 下り坂。
下り坂。
 下りきったら、左折して上り坂を。
下りきったら、左折して上り坂を。
 けっこうな急坂。
けっこうな急坂。 右に曲がると、
右に曲がると、
落ち着いた家並みに。

奥に「天満宮」。
振り返る。
突き当りを右折し、下り坂に。

大網街道の右手にあすみが丘池。
この付近の今昔。

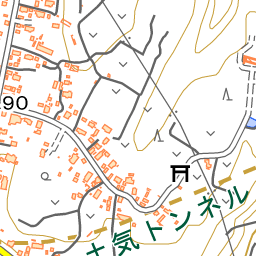

 (現在)下りきって「現大網街道」に合流。
(現在)下りきって「現大網街道」に合流。
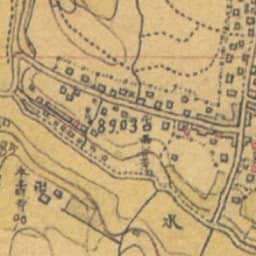


 (1880年代)
(1880年代)
大網への旧道(大網街道)は曲がりくねっている。(「歴史的農業環境閲覧システム」より)
 正面に「昭和の森」。
正面に「昭和の森」。
千葉市昭和の森
千葉県千葉市緑区にある都市公園(総合公園)である。名称に公園はつかない。敷地面積は約100haと千葉市内最大規模の公園であり、広場、遊び場、キャンプ場、野球場、テニスコート、サイクリングコース、ウォーキングコース、展望台、アウトドア施設、宿泊施設等多くの施設がある。園内には遺跡も保存されており、荻生道遺跡は県指定史跡に指定されている。公園は一部を県立九十九里自然公園に指定され、日本の都市公園100選、房総の魅力500選にも選定されている。

千葉市の中心部から東南に約18km、緑区土気地区に位置する面積105.8ha、南北2.3km、東西0.8kmの市内最大、県内でも有数の規模を誇る総合公園である。
公園の西側は、標高60mから90mの下総台地に連なり、東側は九十九里平野と下総台地を分ける高低差約50mの崖地(海食崖)に接している。展望台(標高101m)からは、九十九里平野と太平洋の水平線が一望できる。
公園の一部が県立九十九里自然公園に指定され、良好な自然環境が残されているため、四季を通じて草花や樹木、野鳥や昆虫など多くの種類の植物や生物を見ることができる。3月 - 4月には菜の花や桜が、5月 - 6月上旬にはツツジやサツキが、6月 - 7月はハナショウブとアジサイが、6月 - 8月まではスイレンなどの花々が季節ごとに楽しめる[2]。施設も充実しており、自然公園、遊び場、キャンプ場、野球場、テニスコート、サイクリングコース、ウォーキングコースなど多くの施設がある。各有料施設(駐車場、サイクリングセンター、野球場、テニスコート)については、株式会社昭和の森協力会によって運営されている。
また、1989年(平成元年)には、国を代表する公園の一つとして「日本の都市公園100選」に選定される。
園内の旧ユースホステルは、その跡地を合宿、キャンプ、公園、スポーツ施設を融合した複合施設を設計・改修工事を実施しており2014年(平成26年)4月、野外活動ゾーンにて「昭和の森フォレストビレッジ」としてリニューアルオープンした。公園内はレクリエーションゾーン、展望ゾーン、中央林間ゾーン、宿泊・野外活動ゾーン、スポーツゾーンの5つに分かれている。
(この項、「Wikipedia」より)


(「 」より)
」より)
出会ったところは、北の入口のようです。












 房総地域では多く見られる垣根。よく整備されています。
房総地域では多く見られる垣根。よく整備されています。

 畑地が広がる。
畑地が広がる。 外房線を望む。
外房線を望む。

 「大木戸新田」交差点。
「大木戸新田」交差点。














 誉田駅を望む。
誉田駅を望む。



 「誉田IC」。
「誉田IC」。
 左右に畑地が広がる。
左右に畑地が広がる。


 けっこう車の交通量が多い。
けっこう車の交通量が多い。

 (「じゃらんネット」より)
(「じゃらんネット」より) 「大網」方向。
「大網」方向。
 竹林。
竹林。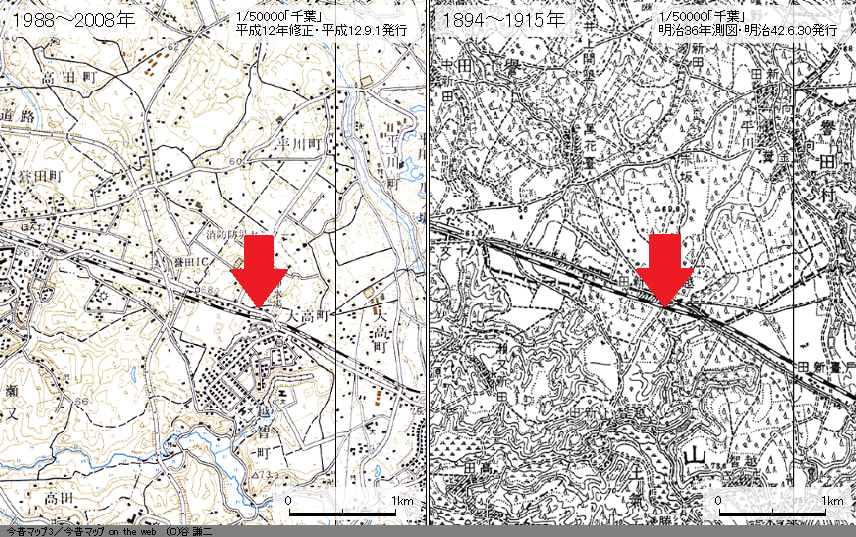

 線路方向を望む。
線路方向を望む。 「大木戸」。
「大木戸」。

 野田十字路。「野田」はこの地域の地名。
野田十字路。「野田」はこの地域の地名。 旧道に復帰。
旧道に復帰。




 土蔵。
土蔵。
 (この項、「
(この項、「 」HPより)
」HPより)






 大網駅方向を望む。
大網駅方向を望む。 」HPより)
」HPより)



 「北生実上宿」信号を右折。
「北生実上宿」信号を右折。
 (「Wikipedia」より)
(「Wikipedia」より)



 (「ジョルダン」より)
(「ジョルダン」より)


 広いアンダーパスと交差。
広いアンダーパスと交差。




 愛らしいフクロウ?
愛らしいフクロウ?

 解説板。
解説板。
 汚水用。
汚水用。



 雨水用。
雨水用。



 振り返る。
振り返る。 前方に「東関東自動車道」高架。下は国道16号線。
前方に「東関東自動車道」高架。下は国道16号線。
 千葉市立生浜小学校。
千葉市立生浜小学校。



 「本満寺」。
「本満寺」。





 (現在)「生実町」。寺を右折する道が旧道。
(現在)「生実町」。寺を右折する道が旧道。


 (1880年代)家並みが続く。
(1880年代)家並みが続く。

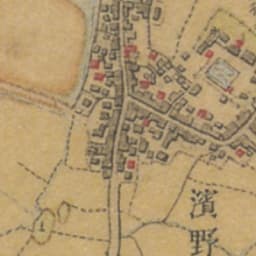
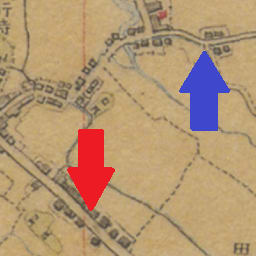 (
(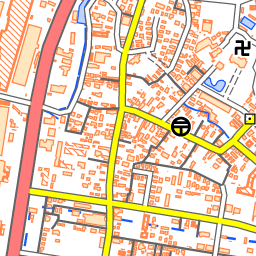
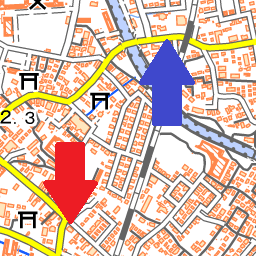


 塩浜橋。
塩浜橋。




 住宅地を進みます。
住宅地を進みます。
 」より)
」より)



 (「ジョルダン」より)
(「ジョルダン」より) 「木更津」~「上総亀山」。
「木更津」~「上総亀山」。










 延命院共同墓地
延命院共同墓地


 で(+400円)。
で(+400円)。


 路面電車風に走るところも。
路面電車風に走るところも。

 本銚子駅・駅舎内。
本銚子駅・駅舎内。 (「もとちょうしえき」)
(「もとちょうしえき」)

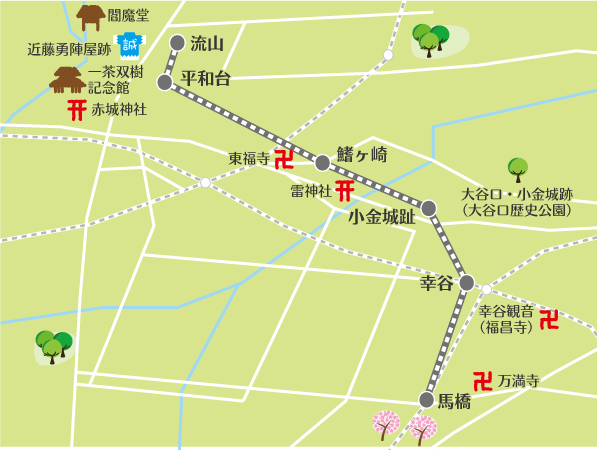





 流山南高校家庭科部装飾電車。
流山南高校家庭科部装飾電車。 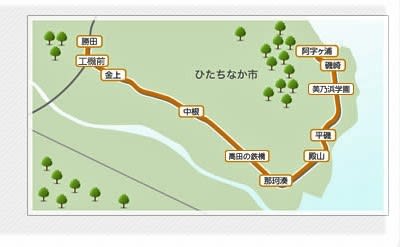 勝田~阿字ヶ浦。14.3㌔、乗車時間約28分。
勝田~阿字ヶ浦。14.3㌔、乗車時間約28分。



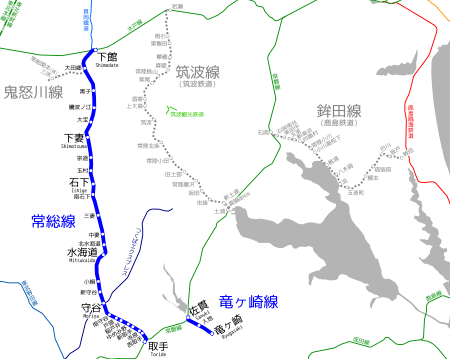
 駅前広場。
駅前広場。