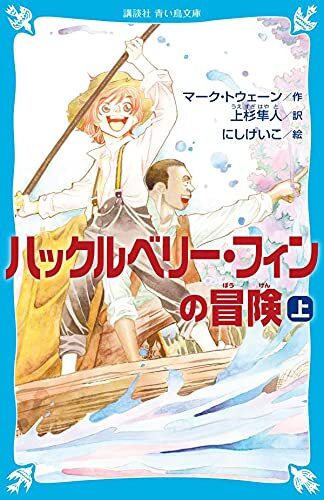トマス・J・デロング『Flying Without a Net 命綱なしで飛べ!』(仮題、2023年刊行予定、サンマーク出版)を目下いちばん集中していて進めている。
本日のGetUpEnglishは本書から紹介する。
During leadership development seminars or in other forums in which I’m acting as a facilitator, I ask participants to write down the name of a person that they have viewed as a leader, mentor, or teacher. The only criterion is that this individual must be someone with whom they have had a relationship (as opposed to the leader of a country or a business superstar). In most instances, older participants have an easier time with this assignment than younger ones; they often ask,
わたしが司会進行を務める各種リーダーシップ開発セミナーやそのほかのフォーラムでは、参加者に、この人が自分の経営者、指導者、教師と思う方の名前を挙げてほしい、と求める。
それにあたっての唯一の条件は、「関係を持ったことがある人」でなければならないということだ (国の指導者やビジネス界のスーパースターの名前を挙げることはできない)。
概して、年上の参加者は若い参加者より簡単に作業を終えてしまう。
年上の参加者によくたずねられる。
以下、訳文で紹介する。
「ほかにも挙げていいですか?」
一方、若い参加者はなかなか書き出せない。
長く仕事を続けていれば、昇進しながら、指導者や経営者と個人的に深い関係を築くことができる。昔は今より会社組織がより小さく、上下関係が親しかったこともある。
誰もが家族のように感じていた。
ベテラン社員は新入社員を自分の娘や息子のように扱うように期待された。社員がうまく仕事ができるように援助する責任があったのだ。漠然と「責任」を負っていたわけではない。直属の部下の面倒を見て、彼らがうまく仕事ができるように援助の点を差し伸べることを経営陣に期待されていた。
部下を指導、教育するのは上司の重要なスキルであり、部下がいい仕事ができれば、若い社員を育てる能力があると尊敬された。
部下を指導、教育することは、上司の職業評価や業績評価対象の項目として正式に記されていない。
だが、年長者は部下や若い人に対して気を配り、彼らが組織でいい仕事ができるように必要に応じて導くという暗黙の了解があった。
そして部下が会社を去ることはほとんどなかった。家族から離れるようなものだからだ。父親や母親のように尽くしてくれた人たちを失望させることになるからだ。
こうした指導者がいてくれたことで、結果を出したい、成功したいと強く望む者たちは「不安の罠」にはまらずにすんだ。
問題にぶつかった、不安を感じるということがあれば、話を聞いてくれる人がいたからだ。
見返りの報酬は基本的に考えることなく、親身になってアドバイスしてくれる人が常にいてくれた。
さらに、変化が必要であると教えてくれる人が、今の状況に甘んじていてよいのか、「望ましくないことを無難にやること」できみは満足なのか、ときびしいことを言ってくれる尊敬できる人がいた。
このように全編、実に刺激的な内容が記されている。
ご期待ください!