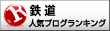大江健三郎さんが亡くなりました。
いろいろな作品(様々なジャンルの)を読みましたが、8年前に発刊された「イン・レイト・スタイル 晩年様式集」の読書感想を掲載しました。再掲し、哀悼の意を。
4年前の3月11日。「東日本大震災」。
このあいだ岩手に行きましたが、復興の話は随所に出てきても(悩みや不安や期待や・・・)、原発の話はなし。
こちらも、復興への励ましはあっても、福島原発の、今も悲惨で、しかし忘れ去れてしまいそうな(ここでも「復興」という大義名分によって)現状について、言い出し得ませんでした。
そして、確実に原発の再起動は迫ってきています。またしても、災禍を乗り越えて、日本の「輝かしい」再建が「着実な」歩みとなっていく、と多くの国民を信じさせながら。
多くの被害者や科学者や政治家や哲学者や文学者が、そして市井の人々が語ってきた「福島原発事故」。さまざまな立場での発言。それらが(賛否いずれもが)、アベ自公政権の強引な再稼働方針とその実施に対する強固な姿勢(4年前の出来事をすっかり忘れさった)に、すっかり(遅れた)過去の言説にでもなってしまったかのような、今の日本の、暗澹たる文化状況、言論状況。
・・・
気がついてみると、
私はまさに老年の窮境にあり、
気難しく孤立している。
否定の感情こそが親しい。
自分の世紀が積みあげた、
世界破壊の装置についてなら、
否定して不思議はないが、
その解体への 大方の試みにも、
疑いを抱いている。
自分の想像力の仕事など、なにほどだったか、と
グラグラする地面にうずくまっている。
しめくくりに記された「詩のごときもの」の冒頭の一節。
福島原発事故のカタストロフィーに追い詰められる思いで書き続ける主人公・長江。
大江さんの分身ともいえる長江古義人が主人公のシリーズ。
「晩年の様式を生きるなかで」書き表す文章となるので、“In Late Style”それもゆっくり方針を立てではないから、幾つもスタイルの間を動いてのものになるだろう。そこで、「晩年様式集」として、ルビをふることにした。
私=長江は、執筆途中だった長篇小説に「3・11後」興味を失い、揺れに崩壊した書庫を整頓しながら、以前購入した「丸善のダックノート」に、思い立つことを書き始める。
一方、四国の森の中に住んできた老年の妹が、自分と2人(妻・千樫と娘・真木)、そして何よりも息子・アカリが、長江(大江)に一面的な書き方で小説に描かれてきたことに不満を抱いている。こうして、3人の女は、あなたの小説への反論を書いたので、読んでもらいたいという。それらを合わせることで私家版の雑誌「晩年様式集+α」をつくるという設定で、話が進んでいく。
妹、妻、娘という3人の厳しい批判が、そして、アカリのつぶやく言葉が、長江に突きつけられる。「家庭を基盤にして、個人的なことから社会的な事まで小説にしてきた。・・・モデルにされた家族からいえば、兄の小説はウソだらけだ」・・・。
さらに、ギー兄さんの子供、ギー・ジュニアや塙吾良(義兄の伊丹十三)の愛人であったシマ浦なども登場し、かつて「小説(フィクション)」のモデルとして扱われた当事者達によって、「事実」が明かされる手法をとっている。
「イン・レイト・スタイル 晩年様式集」は、大江の今までの作品の一つ一つを「解題」しているようなものにも感じられる。「懐かしい年への手紙」、「空の怪物アグイー」、「個人的な体験」、「万延元年のフットボール」、「人生の親戚」、「新しい人よ眼ざめよ」、「『雨の木』を聴く女たち」、「M/Tと森のフシギの物語」、等々。特に、息子の「アカリ」との関わりでしばしば登場する「アグイー」の存在。
また、伊丹十三の自死にまつわる『取り替え子(チェンジリング)』、父の死にまつわる『水死』など、当事者からの異議申し立てを含みながら、謎解きをしていく。特にアカリとの関わり。
そうした展開の中で、その根底にあるのは、3・11後の出来事。
福島原発から拡がった放射性物質による汚染の現状を追う、テレビ特集を深夜まで見終わった後、2階へ上がっていく途中の踊り場で、長江は子供の時分に魯迅の短編の翻訳で覚えた「ウーウー声をあげて泣く」ことになる。
・・・この放射性物質に汚染された地面を人はもとに戻すことができない。(中略)それをわれわれの同時代の人間はやってしまった。われわれの生きている間に恢復させることはできない・・・この思いに圧倒されて、私は、衰えた泣き声をあげていたのだ。
(息子のアカリは父に向かって)
モノマネの語り口はとめないままで。
――大丈夫ですよ、大丈夫ですよ! 夢だから、夢を見ているんですから! なんにも、ぜんぜん、恐くありません! 夢ですから!
「反原発」運動に積極的に関わりながらの執筆(3人+αとのやりとり)は、長江をとりまく大勢の生きる者、死んだ者達。そして、真木や千樫とりわけアカリとの関係の再構成を目論むやりとりでもあった。
《「すべての国民は、個人として尊重される」という第13条に、自分の生き方を教えられた気持でした。あれから66年、それを原理として生きてきた、と思います。もう残された日々は短いのですが、次の世代が生き延びうる世界を残す、そのことを倫理的根拠としてやっていくつもりです。それを自覚し直すために、「原発ゼロ」へのデモに加わります。しっかり歩きましょう! 》
誰かれから、『形見の歌』からの詩が「3・11後」の詩ではないことを知って驚く、といわれるのを聞いた。私自身、詩の中の私の70年という言葉通り70歳の自分から80歳の定点に向かう私への〈端的に、さらに苛酷となる「3・11後」に生き残っている自分への、ということだ〉手紙だったのかもしれない、。と感じる。しかしそれとしての言葉の勢いに、千樫はともかく希望が感じられるといったのだ。
書き写して、終刊号の付録とする。
・・・
否定性の確立とは、
なまなかの希望に対してはもとより、
いかなる絶望にも
同調せぬことだ・・・
ここにいる一歳の 無垢なるものは、
すべてにおいて 新しく、
盛んに
手探りしている。
私のなかで、
母親の言葉が、
はじめて 謎でなくなる。
小さなものらに、老人は答えたい、
私は生き直すことができない。しかし
私らは生き直すことができる。
この小説の執筆時点(現在)は、福島原発事故直後からの約2年間。大震災、大事故からすでに今年で4年が経過した。この作品が世に出てからも1年半が経とうとしている。
大江さんがこの小説の中で、憂いたこと、嘆いたこと、確信したこと、期待したこと、・・・それらは、その後の4年間、いな2年間経ち、今、どうなっているだろうか?
・・・
「私」から「私ら」へ。
少なくともまだ大江さんよりも若い「私ら」(といっても、途方もなく長く残された年月ではないが)は、「生き直すことができる」だろうか? 自問自答しつつも、生きながらえなければならない。