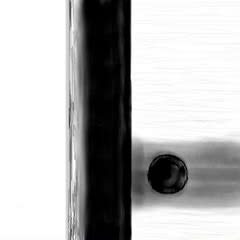先日案内が来ていた、学内講演会に足を運んだ。
東亜同文書院というのは、1901年に中国上海に創立した日中提携人材育成を目的とした教育機関で、後の愛知大学創設につながって行く。
講師は同院25期生で百歳迎えられた安澤隆雄氏、今年市制百周年を迎える豊橋と同い年である。
学長の挨拶のあと、同氏の生い立ち、入学からの中国での生活や出来事、その後の人生について講演された。
聴講者には招待者のほか同院出身者や現職員、大学研究生など様々で、聴講者による質疑応答も行われた。
(長野県松本市 2001年7月22日)
五時十五分起床。修行時代の振鈴時間を思い出す。
昨年7月は立山黒部へ向かったが、今回いつも通り過ぎるだけであった岳都松本へ降り立った。
場所的に多少涼しいのかと思っていたが、私の体温より高い36℃。
歩いてみて先ず感じたことは、人口の割に全てが小ぢんまりしている・・・そんな印象であった。
国宝松本城到着。やはり思っていたより狭い感じがした。期間限定で、小天守が開放されていた。私は建造物にも興味があるので、隅々まで見てまわったが、平日にも関わらず満員。狭い階段を安全に昇り降りさせるために、待ち時間が多かった。
・・・急な階段、足元に注意の説明・・・私にとっては頭上注意が優先であった。
 (乾小天守)
(乾小天守) (六階梁 守護神「二十六夜様」)
(六階梁 守護神「二十六夜様」)
この地に城が築かれたのは、永正の頃(1504)小笠原氏の家臣である島立右近貞永が深志城(砦)を築いたのが始まりという。
その後、武田氏、木曽氏、徳川氏の支配となり、石川氏が城主となった際、城郭(現存天守等)、城下町の整備を行い、地名を松本と改めたという。
そして武蔵川越より堀田氏、三河吉田より水野氏、戸田松平氏がそれぞれ居城し、廃藩となった。
(関連記事:岳都松本 美ヶ原 梓橋 上高地 安曇野平成十九年 開智学校 松本市旧司祭館 里山辺 岳都松本平成二十五年 松本城平成二十五年)
(静岡県磐田郡水窪町)
旧大嵐(おおぞれ)駅から旧白神(しらなみ)駅方向にあるトンネル。旧飯田線のトンネルである。
使われなくなった経緯は、大嵐駅ホームと同じように天竜川佐久間ダム築造により線路が水没するため、新線を造り移動したからである。
最初の短いトンネルが栃ヶ沢トンネル、次が長い夏焼トンネルで、現在は県道、及び夏焼という集落を結ぶ道として使われている。然し、私がこの場所に居た約2時間の間、通る者は無かった…。
一部にこのトンネルを、心霊スポットと称している者もいるという。



昭和9年(1936)12月29日、三信鉄道大嵐(おおぞれ)駅として開設。
昭和18年(1943)国策により重要路線とみなされ、国有化し全長195.7kmの飯田線となった。その後、電源開発佐久間ダム築造により、飯田線中部天竜~大嵐間14.1㎞が水没することになり、昭和28年(1953)静岡県水窪町経由の迂回路線を築くこととなった。それにより、昭和30年(1955)大嵐駅も東方に移動し、使われなくなったホームは、今もただ形としてダム湖畔に佇んでいる。

(写真は、一昨年 富山村に訪れた際の光景)
(HP版: http://www.d1.dion.ne.jp/~tenyou/structure/ozore-station-platform.htm )
覗くには少し広い、出入りするのは少し狭い幅であった。
誰も開けた者もなく、謎ではあったが、仏間に入ったときに感じたのはムッとする暑さ。
“暫く閉めきっていたから、ご先祖さまも暑かったのだろう”と、そう思って昼間は襖を開け風を通すことにした。
それから今日までのところ三日間、朝起きると襖はちゃんと閉まっている…。
(2000年7月16日の考歴雑記から)
愛知県豊橋市牟呂町坂津の前方後円墳、三ッ山古墳平成12年度発掘調査現地説明会へ向かった。
今回は公園整備前提として、範囲確認とともに調査が行われ、前方部・後円部からそれぞれ竪穴式石室が確認され、追葬が行われたことがわかった。出土品は、土師器・須恵器のほか、太刀・鉄鏃・円筒埴輪・人物埴輪片等も出土し、また、鎌倉時代に埋葬されたと思われる蔵骨器(古瀬戸)と組合式五輪塔も出土した。
今回の現説の特色は、子供にも理解できるような配慮があったこと。子供向け資料や、遺物を触れてみるコーナー、参考文献の閲覧、「ハニワのスケッチをしよう」など、これからの人に取り付き易い環境になってきた点などの変化がみられた。


上段: 墳丘くびれ部周溝検出状況
下段: 竪穴式石室検出状況
現在は毎年7月第3土・日曜日に行われている祭礼。
万治三年(1660)小笠原義忠が、衰退していた煙火を再興させたという。祭りには多額の費用がかかる。それを補うため、地元の若衆に呼びかけ、荒地を開墾し、田畑を増加させることでその費用を充て、そして若衆に花火の製法を教え、彼らを東西二組に分け花火を競わせたのが今に続く慣わしであるという。今でも参加する家の玄関先には、祭礼で使用する手筒が看板のように置かれている。
(写真は一昨年の光景)

(平成十九年の模様)
さすが商業もしっかりしており、大型商業施設、個人商店及び仲見世というアーケード街もあって活気があった。
と思いきやそんな中、ある百貨店の閉店セールが行われていた。
関東では有名な、服飾系百貨店の最期。
39年間続いたようだが、このビルは7階建てであるのにエスカレーターが無い。
面積の狭さもあると思うが、その点が印象に残った。
そのビルの地下に中華料理店があった。
何やら懐かしげな雰囲気漂う店で食事をしていると、店の人が「ここがなくなったら商売はもうやめる」と話した。
この言葉が一番印象に残った。
今年の春、再び訪れた。
百貨店跡は更地となり、衰退の文字が浮かんだ。我が近隣浜松を思い起こさせる…。
市役所に寄り、その前にある謎の飲食店の跡が目に入った。
一体これがなんであったのか定かにならずに、この地を離れた…。


(関連記事:千本松原)