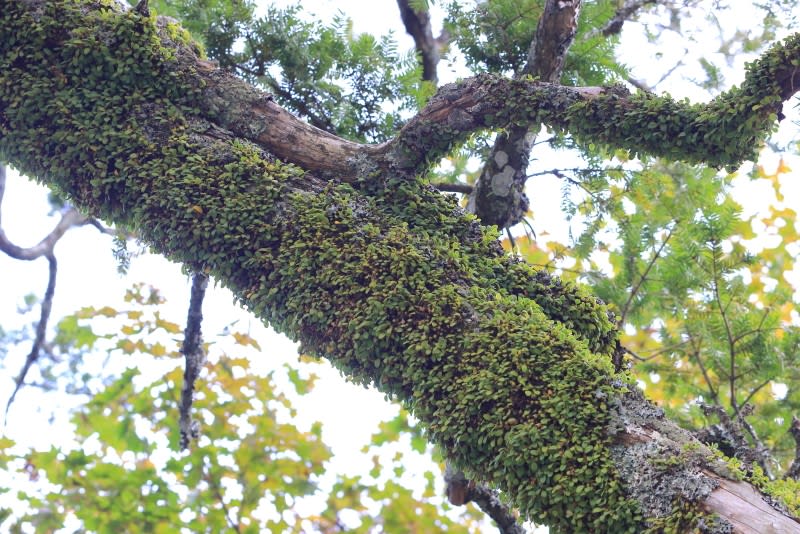亜高山帯の草地に生える多年草。高さは20~40㎝になる。根元近くの葉は普通1個で狭長楕円形、長さ3~7センチで先端は尖らない。鱗片葉は2~3個つき、先端はやや尖る。穂状の花序に黄緑色の花を多数つける。側花弁は開かずに背萼片とともにずい柱を囲み、兜型を呈する。長い距は先端部が緩く下向きに曲がる。花期は7~8月。山梨県では良く似たヤマサギソウが多く見かけられるが、大菩薩・小金沢山系でホソバノキソチドリ生育しているのが発見された。隣県の長野県では普通に見られるであろうが、山梨県ではあまりお目にかかれない。

ホソバノキソチドリ 2023年7月 大菩薩・小金沢山系で撮影

長い距がある。

別株。根元の葉は見えないが鱗片葉は小さくて先端部が少し尖る。

穂状花序にやや黄色味を帯びた花を多数付ける。

黄色い部分は側花弁で、開かずに後ろ側の背萼片とともに兜型を呈する。

距は長く先端部が緩く下に曲がる。
環境省の絶滅危惧種には入っていないが、9府県で絶滅危惧種に登録されている。山梨県ではまだ調査が不十分であるが、ヤマサギソウ(山梨県絶滅危惧Ⅱ類)よりも個体数は少ない印象を持っている。