「白髭橋」から「本所吾妻橋」付近まで。 「橋場の渡し」付近(明治13年頃)。中央下に「橋場の渡し」とある。西岸に町家が集まっているようすが分かる。鐘淵付近は古代の東海道があり、重要な渡し場であったが、隅田川の流路はかなり変化していたようで、渡し場の位置も不明確。現在の(西岸)「橋場1、2丁目」(東岸)「堤通1、2丁目」付近。
「橋場の渡し」付近(明治13年頃)。中央下に「橋場の渡し」とある。西岸に町家が集まっているようすが分かる。鐘淵付近は古代の東海道があり、重要な渡し場であったが、隅田川の流路はかなり変化していたようで、渡し場の位置も不明確。現在の(西岸)「橋場1、2丁目」(東岸)「堤通1、2丁目」付近。
「白髭橋」の西詰付近・「橋場」は古くから歴史的な土地柄だった。江戸時代にも風流な場所とされ、大名や豪商の別荘が隅田川河岸に並んでいた。そのため有名な料亭なども多く、華族や文人などが出入りしていた。明治期に入ってからも屋敷が建ち並んでおり、とくに三条実美の別荘である「對鷗荘」が「橋場の渡し」の西岸にあった。 「白髭橋」西のたもとにある「明治天皇行幸對鷗荘遺蹟」。
「白髭橋」西のたもとにある「明治天皇行幸對鷗荘遺蹟」。 「對鷗荘跡」という掲示(台東区教育委員会)。それによれば、征韓論を巡って政府内の対立が続いていた明治6年、心労のあまり病に倒れこの別邸で静養していた三条実美のもとを明治天皇が訪れた、とのこと。なお、「對鷗荘」は昭和3(1928)年、白髭橋架橋工事に伴い、「多摩聖蹟記念館」に移築されている。
「對鷗荘跡」という掲示(台東区教育委員会)。それによれば、征韓論を巡って政府内の対立が続いていた明治6年、心労のあまり病に倒れこの別邸で静養していた三条実美のもとを明治天皇が訪れた、とのこと。なお、「對鷗荘」は昭和3(1928)年、白髭橋架橋工事に伴い、「多摩聖蹟記念館」に移築されている。 「白髭橋」の由来碑。かすれてしまってほとんど判読不可能。
「白髭橋」の由来碑。かすれてしまってほとんど判読不可能。 上流の自転車通行道は「カミソリ堤防」のために隅田川の流れは全く見えない。河岸にはテラス・遊歩道がある。
上流の自転車通行道は「カミソリ堤防」のために隅田川の流れは全く見えない。河岸にはテラス・遊歩道がある。 かなりの高さの堤防面。民家の地面は数㍍下。
かなりの高さの堤防面。民家の地面は数㍍下。 明治13年頃の白髭橋下流付近。左下の流れは、「山谷堀」。右に見える土手道が現在の「墨堤通り」の前身。赤い橋が「桜橋」。
明治13年頃の白髭橋下流付近。左下の流れは、「山谷堀」。右に見える土手道が現在の「墨堤通り」の前身。赤い橋が「桜橋」。 「白髭橋」と「桜橋」の中間地点付近のテラス。おだやかな「大川」の流れ。遠くにスカイツリー。
「白髭橋」と「桜橋」の中間地点付近のテラス。おだやかな「大川」の流れ。遠くにスカイツリー。 案内板。1905(明治38)年に始まった伝統の「早慶レガッタ」と天保通宝を鋳造していた「橋場の銭座」の説明があります。
案内板。1905(明治38)年に始まった伝統の「早慶レガッタ」と天保通宝を鋳造していた「橋場の銭座」の説明があります。 壁画3点。
壁画3点。 「凌雲閣機繪双六」明治23年11月作。
「凌雲閣機繪双六」明治23年11月作。 河口より8㎞(隅田川右岸)。
河口より8㎞(隅田川右岸)。 「山谷堀」に架かっていた「今戸橋」。
「山谷堀」に架かっていた「今戸橋」。
・今戸の渡し
「寺島の渡し」とも称される。現在の桜橋の上流付近にあった渡し。橋場に対して、新しく作られたということで「今」戸と呼ばれたという。 「桜橋」を望む。
「桜橋」を望む。 「竹屋の渡し」跡碑。
「竹屋の渡し」跡碑。 説明板。
説明板。 「竹屋の渡し」跡付近からの「スカイツリー」。
「竹屋の渡し」跡付近からの「スカイツリー」。
・竹屋の渡し
「向島の渡し」とも称される。待乳山聖天のふもとにあったことから「待乳(まつち)の渡し」とも。「竹屋」の名は付近にあった茶屋の名に由来する。現在の言問橋のやや上流にあり、山谷堀から 向島・三囲(みめぐり)神社を結んでいた。付近は桜の名所であり、花見の時期にはたいへん賑わったという。文政年間(1818年 - )頃には運行されており、1933年(昭和8年)の言問橋架橋前後に廃された。 「山谷堀」跡の緑道公園。
「山谷堀」跡の緑道公園。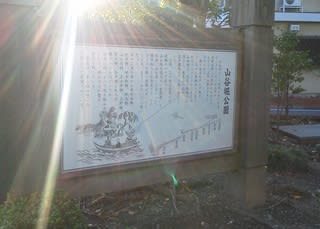 「山谷堀」は吉原通いの舟が往き来していた堀。
「山谷堀」は吉原通いの舟が往き来していた堀。 対岸(墨田区)を望む。
対岸(墨田区)を望む。 「桜橋」東詰の少し北。牛島神社境内にあった「常夜燈」。「竹屋の渡し」の目印になった、という。
「桜橋」東詰の少し北。牛島神社境内にあった「常夜燈」。「竹屋の渡し」の目印になった、という。 明治の頃のようす(案内板より)。上の写真の右手に「常夜燈」が見える(現在地のまま)。
明治の頃のようす(案内板より)。上の写真の右手に「常夜燈」が見える(現在地のまま)。 対岸(台東区)を望む。
対岸(台東区)を望む。 「言問橋」。
「言問橋」。 「山の宿(しゅく)の渡し」跡の碑。
「山の宿(しゅく)の渡し」跡の碑。
・山の宿の渡し
吾妻橋の上流、東武鉄道・隅田川橋梁の付近にあった渡し。渡しのあった花川戸河岸付近は「山の宿町」と呼ばれ、その町名をとって命名されたようです。また、「花川戸の渡し」と称されたり、東岸(対岸)の船着場が北十間川・枕橋のたもとにあったので「枕橋の渡し」とも。
ただgoo提供の明治古地図(年代不明)には、「枕橋の渡し」「山の福の渡し」と表記されている。「福」は「宿」の誤りか。その地図には、少し北の隅田川沿いに「山の宿郵便局」と記載された郵便局がある。  現在の「枕橋」から隅田川方向を望む。「枕橋」は、北十間川(スカイツリー南側の流れ)に架かっている橋。水門で隅田川と結んでいる。
現在の「枕橋」から隅田川方向を望む。「枕橋」は、北十間川(スカイツリー南側の流れ)に架かっている橋。水門で隅田川と結んでいる。 明治13年頃。北十間川と曳舟川が見える。曳舟川の東付近に「スカイツリー」。隅田川沿いは両岸とも「隅田公園」。
明治13年頃。北十間川と曳舟川が見える。曳舟川の東付近に「スカイツリー」。隅田川沿いは両岸とも「隅田公園」。

















