本日はあの忌まわしい東日本大震災が起こってから8年が経ち、9年目を迎えようとしているいわば日本人とって忘れがたい日である。あの震災を振り返り、被災地の今を知り、そのことから学び、自分たちが住む地域のまちづくりに活かそうというイベントが開かれ、ちょっとだけ覗かせてもらった。
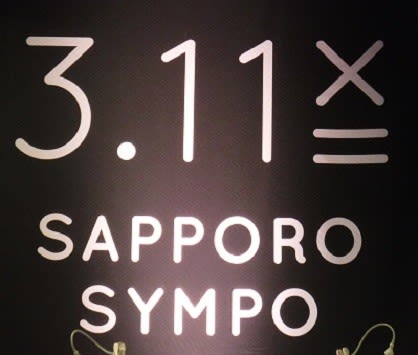
3月11日(日)、12日(月)の両日、チ・カ・ホ(札幌駅前通地下歩行空間)北3条交差点広場において「3.11 × SAPPORO SYMPO」なるイベントが開かれたのを知り、ちょっとだけ覗かせてもらった。
×の意味するところは、3.11大震災を直視しよう(=)という意味と、大震災から学びまちづくりに活かす(×)という意味を込めたと私は解釈したのだが、果たして?
そのSYMPOSIUMの内容は、①「南相馬中央図書館 震災後の歩み」、②「だれでもできる小さな世界の救い方」、③「誰もがみんな被災者だった」、④「原発事故損害賠償・北海道訴訟」、⑤「等身大の関わり方」、⑥「仙台海岸から見える海辺の自然とのつきあい方」、というトークや報告、さらには「北海道胆振東部地震を経験して」という報告や、音楽や落語のライブを間に挟んだり、と多彩な内容になっていた。
私が参加したのは、3月11日(土)の最初のプログラム「南相馬中央図書館 震災後の歩み」について、南相馬市中央図書館司書の高橋将人氏のお話を伺うコマだけだった。

※ シンポ①で対談した南相馬市中央図書館司書の高橋将人氏(右側)と聞き手の北海道ブックシェアリング代表理事の荒井宏明氏です。
高橋氏が南相馬市に図書館司書として勤めだしてから2年目に東日本大震災に遭遇したということだ。年齢が若い割にはしっかりした印象を受けた。南相馬市は福島県の浜通り(太平洋岸)にありながら、中央図書館は幸いに津波の被害には遭わなかったそうだ。そのため図書館は避難所となったが、原発事故で閉鎖したそうだ。
その後、市民の要望を受けて震災から5か月後に制限付きながら再開したという。このエピソードは南相馬市の図書館が日常の中で市民にとってなくてはならぬ存在となっていたことをうかがわせるエピソードである。

※ 南相馬市では、「地震」、「津波」、「原発事故」の三重苦が地域課題となってそうです。
事実、南相馬市の中央図書館は地震、津波、原発事故に対応するために情報を収集し、市民への情報提供に努めているという。コトが起こってからの対応はもちろん大切であるが、日常の中でいかに職務に誠実に向き合うことが大切なのかを教えられた。
その後も紹介したように数々のシンポジウムが組まれていたが、私は早々に退散してしまった。というのも、どうもお話を聞いていても落ち着かない思いがしたのだ。何せ会場は多くの市民や旅行者が行き交う地下歩行空間である。はたしてこうしたシリアスな問題を考える場として地下歩行空間は適当なのだろうか?今回は6回目の開催だと聞いた。主催者もいろいろと試行錯誤の結果、今回のような会場にしたものと推察される。そのあたりを想像したとしても、私としてはもう少し落ち着いた場所でこうした問題についてお聞きし、考えてみたいと思ったのだが、どうなのだろうか??









