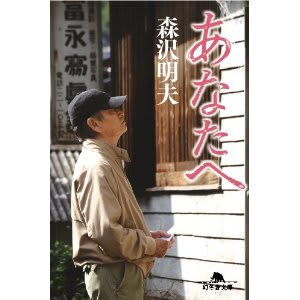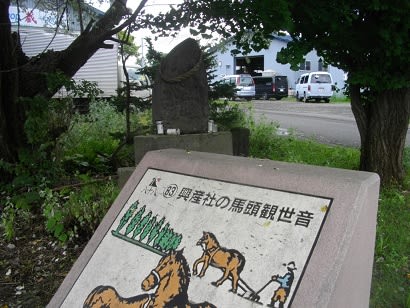コースの一部となっている「あいの里緑道」はあいの里ニュータウンを開発するときに計画的に設けられた緑道のようである。だから地区住民にとっては理想的な緑道に思える遊歩道だった…。
私は「藍の道」から、再び「あいの里緑道」に戻った。
「あいの里緑道」はちょうどあいの里地区をすっぽりと取り囲むように延長約6キロの遊歩道が形成されている。その他調べてみると、あいの里地区には住宅街を縦横に走る数多くの緑道があった。
その緑道を列挙してみると、「あいの里東緑道」、「あいの里公園前緑道」、「あいの里駅前緑道」、「あいの里せせらぎ緑道」、「あいの里北公園前緑道」、「大学前緑道」、「鉄道沿線東緑道」、「鉄道沿線西緑道」といったぐあいに街中に緑道が張り巡らされている感じである。
 ※ 遊歩道の両側には種々の樹が配され、典型的な「あいの里緑道」の姿です。
※ 遊歩道の両側には種々の樹が配され、典型的な「あいの里緑道」の姿です。
この地域は1980年代に入ってからニュータウンの造成が行われたという。ということはかなり計画的な街づくりが可能だったということだ。そのために理想的とも思える緑道が住宅街を取り囲み、あるいは住宅街を縦横に走る緑道を造ることも可能にしたのだろう。
さて肝心の「あいの里緑道」は、約2メートルの幅にレンガが敷き詰められた心地良い遊歩道である。ところどころにベンチが配され、さらに東屋も数か所設置されている。そして夜間の足元を照らす街灯まで完備しているのだ。
 ※ 緑道にはこうしたベンチがいたるところに配置されていました。
※ 緑道にはこうしたベンチがいたるところに配置されていました。
 ※ さらには東屋もかなりの数が設置されています。形もさまざまでした。
※ さらには東屋もかなりの数が設置されています。形もさまざまでした。
 ※ 右側に見える小さな柱が足元を照らす街灯です。
※ 右側に見える小さな柱が足元を照らす街灯です。
ただ、造成されて30数年が経過したせいだろうか、レンガとレンガの間から雑草が伸びてきているところが目立った。中には幅が1メートル未満となっているようなところもあり対策が必要な気がした。
 ※ 緑道のところどころでこのように雑草が進出しているところがあり気になりました。
※ 緑道のところどころでこのように雑草が進出しているところがあり気になりました。
コースはあいの里の最も北側に位置する教育大札幌校やその付属小・中の敷地を取り囲むようにして進む。緑道の両側には意図的に植樹されたと思われる多種多様な樹が植わっている。(種類が分からないのが残念)
平日の午後ということであまり多くはなかったが、ウォーキングしている地域の人たちにも何人か出会った。
コースのさらに北側には茨戸川が流れているのだが、コースからは見ることができなかった。やがてコースの最西端に位置する拓北高校、その隣のあいの里公園内にある「トンネウス沼」のところで「あいの里緑道」は終わりとなる。
 ※ 緑道の樹間から教育大札幌校の建物が望めました。
※ 緑道の樹間から教育大札幌校の建物が望めました。
 ※ このようにウォーキングをしている人にも何人か出合いました。
※ このようにウォーキングをしている人にも何人か出合いました。
 ※ ちょっと気の早い木が紅葉をはじめていました。
※ ちょっと気の早い木が紅葉をはじめていました。
 ※ 緑道の最西端に位置する拓北高校の校舎です。
※ 緑道の最西端に位置する拓北高校の校舎です。
この「トンネウス沼」は絶滅危惧種のカラカネイトンボの生息地として知られている沼である。
しかし、そのことを知らずにこの沼を見た者はどう思うだろうか、と思ってしまった。沼は流れがほとんどないためだろう、水草が水面のほとんどを覆ってしまっている。その様子はお世辞にも美しいとは見えない。流れがないからトンボやその他の水棲生物にとっては棲みよい環境なのだろう。
沼は「あいの里公園」内に位置しているのだが、公園の方は芝生がきれいに刈られ整備が行き届いている。一方は手つかずの自然をそのまま残そうとしている。住宅地に囲まれたトンネウス沼はこれからも今の姿のままで在り続けることができるのだろうか?
 ※ トンネウス沼です。いかにも多くの水棲生物が生育していそうです。
※ トンネウス沼です。いかにも多くの水棲生物が生育していそうです。
 ※ 一方で沼の隣には見事に整備された芝生の公園が広がっていました。
※ 一方で沼の隣には見事に整備された芝生の公園が広がっていました。
コースは住宅街に入り、「あいの里北公園」から「せせらぎ緑道」に入った。緑道の中に水の流れを入れた遊歩道である。夏には小さな子どもたちの絶好の遊び場になるのではと思わされた。
 ※ いかにも子どもが喜びそうな「せせらぎ緑道」です。
※ いかにも子どもが喜びそうな「せせらぎ緑道」です。
あいの里地区は住宅街とともに駅前近くには大きなマンションも目立った。札幌のベットタウンとして発展しているのかもしれない。
と思ったのだが、あいの里教育大前駅の駅前には小さなショッピングモールが形成されているだが、そこの様子が4年前に訪れたときと比べて明らかに寂しく感じたのだが…。
詳しくは不明だが、あいの里地区を開発する際の計画人口は32,000人だったのだが、開発後30数年が過ぎようとしている現在人口が約18,000人だという。その目論見の違いが商店街の寂しさの原因なのだろうか?
 ※ このように大きなマンションが建っているとはちょっと意外でした。
※ このように大きなマンションが建っているとはちょっと意外でした。
 ※ 4年前に来た時と比べ明らかに寂しくなっていた駅前です。
※ 4年前に来た時と比べ明らかに寂しくなっていた駅前です。
あいの里教育大前駅から拓北駅まで住宅街を歩いたが、これといった特色ある光景を見ることはなかった。
 ※ JRあいの里教育大前駅の駅前の様子です。
※ JRあいの里教育大前駅の駅前の様子です。
あいの里地区は札幌市のベッタウンとして位置づけとして開発されたと思われるが、JRで札幌駅まで25分を要するということは、その前後を考えると通勤・通学に最低でも1時間はみなくてはならない。このことがどうなのだろうか?
また、あいの里地区は冬期間の豪雪地帯としても名高い。
計画していたように人口が増えてはいないのではないだろうか?
しかし、これは外から見た素人の見方である。実際はどうなのだろうか?
《フットパスウォーク実施日 ‘12/09/11 距離 約9.5Km》