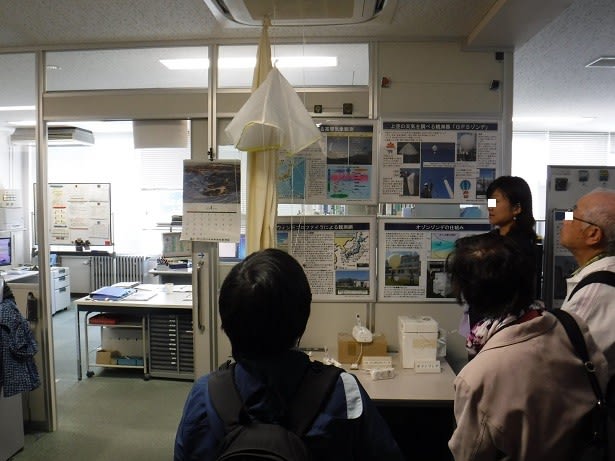これというテーマは設けなかった。「ミズバショウ観察会」に参加した後、春らしい陽気に誘われてなかなか訪れる機会のない星置界隈をぶらりと散歩してみた。
4月14日(日)午前に星置緑地を会場に開催された「ミズバショウ観察会」に参加し、そのまま帰宅するのも芸がないと考え、なかなか訪れる機会のない星置界隈をぶらりと散歩することにした。
車を郊外型店舗が集中しているショッピングモールの駐車場に停車して、星置地区から海岸の小樽ドリームビーチを目ざし、その後は海岸線を横切り、方形に歩いて帰ってくるコースを自分の中で設定してスタートした。

※ 数えなかったけれど、相当多くの郊外型店が集まり、広大なショッピングモールを形成していました。
星置の住宅街から海岸を目ざして歩き始めたが、住宅街をちょっと離れるとそこはもう畑地だった。このあたりは砂地のためかスイカなどの生産が盛んと聞いている。

※ 住宅街からほんの少し離れると写真のような畑が広がっていました。
さらに海岸を目指すと小さな橋を渡った。すると橋には「山口運河」と銘板が貼ってあった。「山口運河」とは、明治27年、道庁により銭函-花畔間に掘削された「銭函運河」延長6.5キロの排水兼輸送用水路だが、そのうちの手稲村山口地区の部分を指すという。海岸に近い砂の多い湿地のため土手の崩壊などで水路は浅くなりやすく、また海岸に沿っているため高低差も少なく効果は薄かったため短命に終わったという。しかし、地域の人たちはその歴史を消すまいと整備、維持管理に努め、学校の児童生徒とともに「手稲山口運河まつり」を毎年開催し、歴史を語り継いでいるという。

※ きれいに整備された「山口運河」です。往時とは違い河岸も整備されています。
さらに行くと辺りに住宅はほとんど見えない中に目に入ったのが小学校だった。校名を確認すると「手稲北小学校」と判明したが、校舎の屋上に「開校127周年」と書かれていてちょっと意外な思いがした。というのも、周辺は新興住宅街でそんなに古くから拓けていたとは思われなかったからだ。帰宅して調べてみると1892(明治25)年に「山口村立山口尋常小学校」として開校したとあった。つまり始まりは小さな農村の学校が始まりだったようだ。なお、学校の紹介では札幌市で海に最も近い学校(海岸から1.5km、標高5m)としても紹介されている。

※ 意外と歴史のある「札幌市立手稲北小学校」の校舎です。
海岸へは星置地区から真っすぐ伸びているが、道々337号線の広い道路を横切ると建物はほとんど見えなくなる。唯一(唯二?)あったのが造園業者とその向かいに何かの会社の建物があった。

※ 道々337号線を越えると、写真の造園業者と道路向かいの会社の建物しかありませんでした。
そこから少し行くと、私立学校(高校?大学?)が取得したのではないかと思われるグランドが目に入った。しかし、今は使われていないのだろうサッカー用のゴールが見えたが、グランドには雑草が生い茂っていた。

※ 今はもう使われなくなったグランドです。
さらに海岸への道は真っすぐ伸びていた。周りは海岸が近づいたことを示すように防風用の灌木が生い茂っていたが、その隙間から「小樽カントリー倶楽部」のグーリーンが垣間見えた。海岸に近く、砂地の多い土地では他の利用価値があまりないと思われるが、ゴルフコースには最適なのかもしれない。

※ 道路は海岸に向かって真っすぐ伸びていました。

※ 海からの風を防ぐための防風林でしょうか?灌木が生い茂っていました。

※ そんな灌木の林の中からぽっかり顔を出した「小樽カントリー倶楽部」のグーリーンです。

※ こちらも同じくゴルフ場ですが、前の写真とは反対側からプレー中の人が写る写真が撮れました。
そうするうちに周りが開け海岸に出た。小樽ドリームビーチの一角である。(ちょうどドリームビーチの真ん中付近と思われた)好天も手伝って海岸には釣り人や海を眺めに来た人たちが何人かいたが、まだまだ静寂そのものだった。遠くには海に浮かぶ船も何艘か見えた。私は海を右手に見ながら小樽方面(南西方向)に向かって歩いた。ドリームビーチは最近浸食が激しいと聞く。海岸段丘が海の近くまで迫ってきているところもあった。

※ 小樽ドリームビーチの海岸段丘の上の砂浜です。

※ こちらは海辺まで降りたところの写真ですね。

※ かなり望遠を使って遠くの船を写しました。釣り船でしょうか?

※ ご覧のように海岸段丘が海辺まで迫っています。砂浜が削られているのでしょう。

※ 中にはこのように土留めをして崩壊を防ごうとしているところもありました。
カラスが海岸に流れ着いた(?)カレイの死骸を啄んでいた。また、釣り人がちょうどカレイを釣り上げているところにも遭遇した。好天の中、波の音を聞きながら波打ち際を歩くのは心地好かった。

※ カレイの死骸を啄むカラスくんです。

※ このように釣りを楽しむ人に3人ほど出合いました。

※ 釣った魚はカレイ2匹ですね。ちょっと小ぶりのようですが…。
やがて星置川が日本海に注ぐ河口のところに至った。

※ 星置川が日本海に注ぐ河口です。
私はそこから海に別れを告げ、星置川沿いを星置の街に向かって舵を切った。川沿いはまだ春が浅く、雑草も茂っておらず、遠くには手稲山の山並みも望めてこの辺りの散歩もまた気持ちの良かった。

※ 星置川沿いは写真のようなのどかな散歩道が続いていました。

※ 手稲山が良く見えました。スキーコースにはまだ雪が残っているようです。
やがて星置川沿いに広がる「星観緑地」の端に到達すると、左折して車を駐車したショッピングモールまで一路真っすぐである。一か所だけマップに気になるところがあった。星置川沿いに大きく水色に塗られた沼地状の図があった。そこを確かめるため横道にそれて確認したのだが、そこに沼地はなかった。あったのは低地に広がる広場のようなものだった。近くにお住まいの方がいたので聞いてみると、どうも沼地ではないらしい。冬には雪捨て場になるということで特に利用されてはいないようだ。

※ 「星観緑地」に到達です。川向うでは少年たちがサッカーを楽しんでいます。

※ この低地はいったい何に使われているのか?舗装されているようですが、その用途は謎です?
元の道に戻り、車の往来は激しいが、人の通りは少ない道をショッピングモール目ざして歩を進めた。途中、星置中学校、星置養護学校の校舎が見えたが、写真は撮らなかった。距離にして約9.5キロ、やや物足りない思いもしたが「ぶらり散歩」を終えることにした。
新しい住宅街はどこも同じ表情の建物が並んでいて、私が期待するような興味ある物件には遭遇しない。それでも新しいところは、私自身の経験値を広げるうえで無駄ではない。これからも時間と心身に余裕があるかぎり、あちこちと出没してみたい。