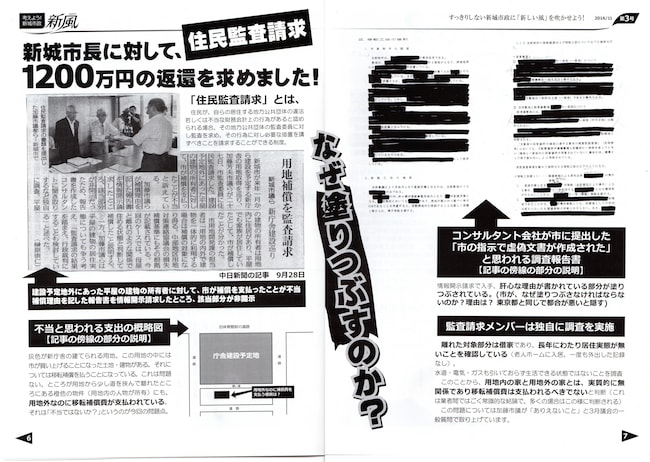やはりブルックナーは女性には人気がないというのが定説のようだ
自分自身がプログラムがブルックナーのときにコンサート会場で男ばかり見かける
といった経験をしている訳ではないが
何故か「絶対女の人には受け入れられない(理解されない)音楽だ」
と妙に確信を持って思い込んでいる(絶対間違いのないと思い込んでいる)
電車の中で読み終えたこの本
冒頭に、女性でブルックナー好きは珍しいという話から始まっている
この本は残念ながら、ブルックナー好きの男の立場からすると
少し物足りない
確かにオーストリアの田舎者丸出しで、鈍くさくて、常識知らずで
強気の人にはからっきし弱くて、それでいて若い女性に相手の気持ちも考えず
結婚を申し込んだりする、、少し変な男のことは書かれている
ブルックナー好きな者なら知っているエピソードを、うまくまとめて
ある人の小説(インターネット上のページ)として取り上げているのは
ひとつのアイデアだ
しかし、もう少しウダウダと書いてほしかったのは
(それが独断であれ偏見であれ)ブルックナーの音楽は
男しか理解できないと思うのは何故か?ということ
これが充分なほど(くどいほど)書かれていないので
なにか中途半端に放っておかれた気がしてしまう
ところで、ブルックナーは何故女性に受けないのか
の自分なりの考えは、、、
感情的、情緒的ではないのもひとつの理由ではないかと考える
なかなかきれいなメロディもあるが、ショパンやチャイコフスキー
ブラームスのような情感に訴えるものではない
それは瞑想的な思索的なメロディ
子供の頃、男の子は機械もののおもちゃが好きで
女の子は花が好きみたいな、最初から向かう方向性が違うような
その差がここでも見られるような気がしてる
別の言い方をするなら、理数系が好きなのは男
文化系が好きなのは女 みたいな違いがここでも見られるのではないか
ということ
しかし、ブルックナーが苦手な女性も、彼のピアノ曲
「思い出」とか「秋の夕べの静かな思い」とか「幻想曲」
を聞いたらきっと考え直すかも知れない
でもブルックナーの本質は
あのピアノ曲の聞きやすい方向性を求めなかった点で
とっつきにくい音楽こそが(いったんハマってしまうと逃れられない魅力にみちた)
彼の音楽そのもの
それはゴッホがゴッホになったように
ピカソがピカソになったように
アラベスクのドビッシーが前奏曲のドビッシーになったように
求めたいものを求めてブルックナーはブルックナーになったということ
きっとあのピアノ曲だけのブルックナーだったら並でしかなかった
へんてこなとっつきにくいけど運良くハマることができた人には
人生の喜びのひとつとして感じられる音楽
8番の3楽章は、やはり多くの人が最高の音楽として認めている
あの音楽は聴いていると長いのか短いのか、だんだんわからなくなってくる
田舎のおっちゃんのブルックナー
鈍くさくて、世渡りが下手で、容貌が冴えなくて、、
でも音楽は、自分にとっては、、すばらしい
(でも、ほんと何故女性には理解できないと確信をもって感じるのだろう?)