東北大震災のことを私の中で風化させてはいけない、との思いからイベント名と一般参加可能との告知だけを見て参加を決めたのだが…。
3月23日(土)午後、会場がパークホテルと聞いて少々いぶかしくも思いながら会場に向かったところ、主催が札幌市内16クラブが連合した国際ローターリークラブであった。しかも内実はロータリークラブ会員の研修会的色彩の強いもので、そこに一般参加も認めたという形だった。(一般参加はごく少数だった)

※ 開会前の会場内の様子です。
ロータリークラブ式の開会行事(私にとっては物珍しかった)の後、研修会に移った。
内容は、基調講演と特別報告、そしてシンポジウムからなっていた。
基調講演は国際ロータリーの一員として世界各地の紛争地や自然災害の被災者等の姿を写し伝えるフォトグラファーのアリソン・クウェッセルさんが務めた。
アリソンさんは現在、東京電力福島第一原発から50キロほどしか離れていない福島県新地町を中心に取材しているとのことだ。
新地町の人たちは「自分たちの町は注目されていない、忘れられた町だ」という嘆きの声を聞くことが多いという。確かに私も福島原発により近い双葉町、川内村、浪江町といった名前は良く聞くが、新地町は恥ずかしながら初耳だった。
講演はアリソンさんの英語を翻訳する形で進められていたのだが、途中からは画面に映る日本語を我々が読む形に変えられてしまった。メモすることが難しくなった。しかも途中から伝える方法を変更したことが私の集中力を削いでしまった。彼女の言いたいことが私には伝わってこなかった。残念である。(なぜ途中から変更するようなことをしたのだろう?)
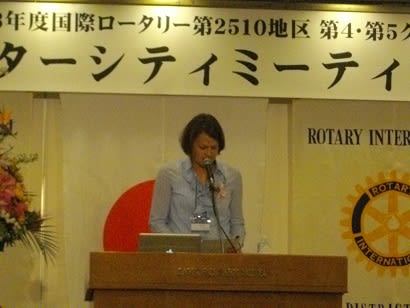
※ 基調講演をするアリソン・クウェッセルさんです。
後半は日本を含めて5ヶ国の比較的若い人たちによるシンポジウムだった。
登壇者は、◇セニア・ネムソフさん(米国 元交換留学生、静岡県在住)◇金昌震さん(韓国 仙台留学中に震災に遭遇、現在北大大学院在学中)◇廉哲さん(中国 札幌大卒業、旅行会社経営)◇中脇まりやさん(日本 みちのくkids代表、道教育大生)◇林素鳳さん(台湾 台湾警察大教授、現在北大招聘教授)の5人である。
それぞれ背景も、立場も異なる5人だが、セニア、金、廉さんたちの発言にはある共通項があった。それは日本に滞在中に、日本の良さ、日本人の優しさに触れ、大震災に襲われた日本に対して自分の立場から応援したいという発言だった。また、台湾の林さんは「日本は台湾人にとっては憧れの国である。だから震災の際にも義捐金が200億円以上も集まった」と述べた。
対する中脇さんは、日本人として何かお手伝いしなくてはという思いから、札幌に避難してきた子どもたちをケアする団体を立ち上げ活動していると話した。

※ シンポジウムに登壇した5人の皆さんです。
世界の平和という話題に移ったとき、韓国の金さんは「自国の教科書が日本のことを事実と異なって記述していることを痛感した。自国へ向けて日本の実状を発信していきたい」と語った。
中国の廉さんは、「世界は交通や情報の発達によってますます小さくなっている。そんな時代に魚釣島とか竹島とか地球規模で見れば小さなこと。小さなことで争っていることは滑稽なこと。紛争地を双方で開発したらどうか」と発言した。
その他、登壇者からはさまざまな発言があったが、正直な感想としてやや表面的かなという思いが残ったが、この集いに参加しいろいろな人の考えを聴くことができたことは私にとって無駄な時間ではなかった。
シンポジウムの最後に、コーディネーターの村山紀昭氏(元北海道教育大学長)がアラスカから日本に留学し、その後陸前高田市で英語指導助手をしていて津波で亡くなった青年のことを紹介した。
彼は司馬遼太郎の言葉「世のために尽くした人の一生ほど美しいものはない」という言葉に出会い、その言葉を実践し生徒たちからとても慕われていたという。その彼が志半ばで亡くなったことはとても残念なことである。
村山氏は、その青年モンゴメリィ・ディクソンさんの思いを受け継いでいくことを若い人たちに望みたい、と結んだ。
3月23日(土)午後、会場がパークホテルと聞いて少々いぶかしくも思いながら会場に向かったところ、主催が札幌市内16クラブが連合した国際ローターリークラブであった。しかも内実はロータリークラブ会員の研修会的色彩の強いもので、そこに一般参加も認めたという形だった。(一般参加はごく少数だった)

※ 開会前の会場内の様子です。
ロータリークラブ式の開会行事(私にとっては物珍しかった)の後、研修会に移った。
内容は、基調講演と特別報告、そしてシンポジウムからなっていた。
基調講演は国際ロータリーの一員として世界各地の紛争地や自然災害の被災者等の姿を写し伝えるフォトグラファーのアリソン・クウェッセルさんが務めた。
アリソンさんは現在、東京電力福島第一原発から50キロほどしか離れていない福島県新地町を中心に取材しているとのことだ。
新地町の人たちは「自分たちの町は注目されていない、忘れられた町だ」という嘆きの声を聞くことが多いという。確かに私も福島原発により近い双葉町、川内村、浪江町といった名前は良く聞くが、新地町は恥ずかしながら初耳だった。
講演はアリソンさんの英語を翻訳する形で進められていたのだが、途中からは画面に映る日本語を我々が読む形に変えられてしまった。メモすることが難しくなった。しかも途中から伝える方法を変更したことが私の集中力を削いでしまった。彼女の言いたいことが私には伝わってこなかった。残念である。(なぜ途中から変更するようなことをしたのだろう?)
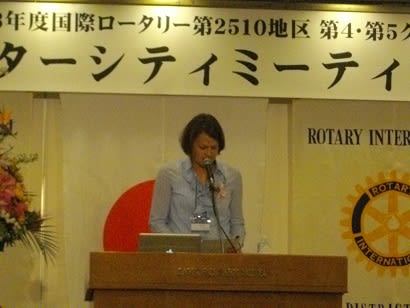
※ 基調講演をするアリソン・クウェッセルさんです。
後半は日本を含めて5ヶ国の比較的若い人たちによるシンポジウムだった。
登壇者は、◇セニア・ネムソフさん(米国 元交換留学生、静岡県在住)◇金昌震さん(韓国 仙台留学中に震災に遭遇、現在北大大学院在学中)◇廉哲さん(中国 札幌大卒業、旅行会社経営)◇中脇まりやさん(日本 みちのくkids代表、道教育大生)◇林素鳳さん(台湾 台湾警察大教授、現在北大招聘教授)の5人である。
それぞれ背景も、立場も異なる5人だが、セニア、金、廉さんたちの発言にはある共通項があった。それは日本に滞在中に、日本の良さ、日本人の優しさに触れ、大震災に襲われた日本に対して自分の立場から応援したいという発言だった。また、台湾の林さんは「日本は台湾人にとっては憧れの国である。だから震災の際にも義捐金が200億円以上も集まった」と述べた。
対する中脇さんは、日本人として何かお手伝いしなくてはという思いから、札幌に避難してきた子どもたちをケアする団体を立ち上げ活動していると話した。

※ シンポジウムに登壇した5人の皆さんです。
世界の平和という話題に移ったとき、韓国の金さんは「自国の教科書が日本のことを事実と異なって記述していることを痛感した。自国へ向けて日本の実状を発信していきたい」と語った。
中国の廉さんは、「世界は交通や情報の発達によってますます小さくなっている。そんな時代に魚釣島とか竹島とか地球規模で見れば小さなこと。小さなことで争っていることは滑稽なこと。紛争地を双方で開発したらどうか」と発言した。
その他、登壇者からはさまざまな発言があったが、正直な感想としてやや表面的かなという思いが残ったが、この集いに参加しいろいろな人の考えを聴くことができたことは私にとって無駄な時間ではなかった。
シンポジウムの最後に、コーディネーターの村山紀昭氏(元北海道教育大学長)がアラスカから日本に留学し、その後陸前高田市で英語指導助手をしていて津波で亡くなった青年のことを紹介した。
彼は司馬遼太郎の言葉「世のために尽くした人の一生ほど美しいものはない」という言葉に出会い、その言葉を実践し生徒たちからとても慕われていたという。その彼が志半ばで亡くなったことはとても残念なことである。
村山氏は、その青年モンゴメリィ・ディクソンさんの思いを受け継いでいくことを若い人たちに望みたい、と結んだ。









