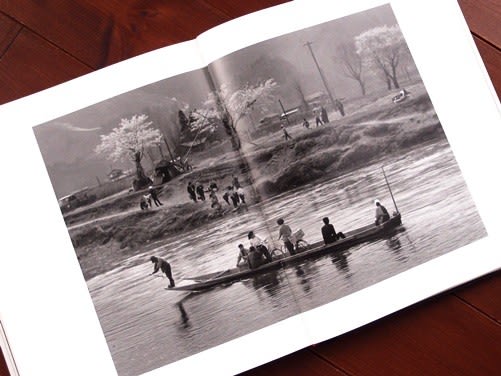ケンミンショーで、超田舎(笑)の家のなかでの寒さを話題にしていた。寒冷地の冬季は部屋による温度差があり、屋外にあるトイレ・風呂場への行き来のこと等、懐かしい気持ちで見入った。なかでも掛布団が重い、いや重くなければ駄目という話は亡くなった祖母や母がよく口にしていたし、感覚的に十分理解できた。
東北や北陸出身タレントが、「昔は部屋の戸の開け閉めをしっかりしないと怒られた」と言った時、妙に記憶がよみがえり、家人とつい声を合わせたのが「ト―シメレ(戸を閉めれ)」だった。何度も何度も耳にした一言だ。今は家中が適温というのが普通で、そこに行けば暖かいという場がなくなったと改めて気づく。
「マズ、アダレ」とストーブや炬燵のそばに招き入れられることも少なくなった。まったくの郷愁と言えるかもしれない。しかし何でもフラットを目指す今の世が果たして良いものなのか、つい考えてしまう。寒さがあり暑さがある、厳しさがあり優しさがある…自然に限らず、人間社会でも当然のことだったのに。
とひとしきり妄想をして…今年は地区内の班長で広報配りなどの役目を月数回行っているが、冬場に廻るとまた面白い場に出くわす。融雪溝が整備されていない道沿いの住居はやはり除雪が大変で、玄関へのアプローチは両脇に雪を積みながら通すことになる。その「壁」の高さが人の背に近く、そこでまた思い出す。
昔はこんな住まいが多かった。それより地面近くまで除雪せず、雪で階段を作っていたではないか。裏出口はそんなふうに作るのが自分の役目だった時もあったなあ。山間地の教員住宅に泊まった時は連日そんな繰り返しだった。その寒さ、冷たさが部屋や教室のストーブでほどける瞬間を思い出す。幸せの一瞬だ。
東北や北陸出身タレントが、「昔は部屋の戸の開け閉めをしっかりしないと怒られた」と言った時、妙に記憶がよみがえり、家人とつい声を合わせたのが「ト―シメレ(戸を閉めれ)」だった。何度も何度も耳にした一言だ。今は家中が適温というのが普通で、そこに行けば暖かいという場がなくなったと改めて気づく。
「マズ、アダレ」とストーブや炬燵のそばに招き入れられることも少なくなった。まったくの郷愁と言えるかもしれない。しかし何でもフラットを目指す今の世が果たして良いものなのか、つい考えてしまう。寒さがあり暑さがある、厳しさがあり優しさがある…自然に限らず、人間社会でも当然のことだったのに。
とひとしきり妄想をして…今年は地区内の班長で広報配りなどの役目を月数回行っているが、冬場に廻るとまた面白い場に出くわす。融雪溝が整備されていない道沿いの住居はやはり除雪が大変で、玄関へのアプローチは両脇に雪を積みながら通すことになる。その「壁」の高さが人の背に近く、そこでまた思い出す。
昔はこんな住まいが多かった。それより地面近くまで除雪せず、雪で階段を作っていたではないか。裏出口はそんなふうに作るのが自分の役目だった時もあったなあ。山間地の教員住宅に泊まった時は連日そんな繰り返しだった。その寒さ、冷たさが部屋や教室のストーブでほどける瞬間を思い出す。幸せの一瞬だ。