
この地は、戊辰戦争の時の白河口古戦場の跡地で、「戊辰の役古戦場碑」や会津藩主松平容保題字の大きな「鎮魂碑」などが建っています。


戊辰の役古戦場
市内の九番町の西端、ここ松並にあり、南は水田が開け、北は稲荷山の小丘を慶応4年(1868)奥羽諸藩鎮定のために、薩摩大垣等西軍が大挙して三方から白河を攻めた。
東軍の会津、仙台、棚倉の兵は、白河城の南西の山に陣し、これを迎え撃った。この地は白河口での激戦地で、潤4月25日、会津兵は一旦西軍を退けたが、5月1日、再び来襲したので、西郷頼母、横山主税等が稲荷山に陣し迎え撃ったが、激戦、数十合、弾尽き刀折れ、戦死者数しれず遂に敗退のやむなきに至り小峰城は遂に落城、城郭は焼失した。
戦後両軍は、各戦死者の碑を建て、霊を慰めた。
この白河街道の左曲する南側に、長州藩三名大垣藩三名の墓、北側に会津藩戦死者の墓と会津藩主松平松容保の題字の鎮魂碑がある。
白河市教育委員会
注:明治新政府軍と奥羽越列藩同盟との戦いを西軍、東軍と言い表しているところにいまだに続く「白河」の気概があるようです。


長州大垣藩六人之墓(松並地内)
慶応4年(1868)閏4月25日、新政府軍が白河を初めて攻めた際に戦死した長州、大垣藩将藩士(3名)と大垣藩士3名の墓である。
当初は薩摩藩兵7名も埋葬されており、「薩長大垣千戦死十三人之墓」と刻まれていたが、薩摩藩が大正4年(1916)に小峰城東側の丘陵(鎮護神山)に戦死者を合葬したため、現在のの姿となった。
明治9年6月に明治天皇が、同41年9月には皇太子時代の大正天皇が立ち寄り、戦死者の霊を弔った。
白河観光物産協会

そこから道の向こう側を望む。

白河口の戦い
戊辰戦争における戦いの1つ。戊辰戦争の戦局に大きな影響を与えた。
慶応4年閏4月20日から7月14日(1868年6月10日から8月31日)にかけて、南東北の要地白河小峰城(白河城)を巡る奥羽越列藩同盟側(仙台藩・会津藩・旧幕府歩兵隊・米沢藩・棚倉藩など)と新政府軍(薩摩藩・長州藩・大垣藩・忍藩)との戦い。
仙台藩・米沢藩などを主力とした列藩同盟軍は、会津藩・庄内藩と提携し新政府と敵対する軍事同盟成立に際し白河城を攻撃し、新政府軍から白河城を奪い取った。ここに戊辰戦争の東北地域での戦闘・東北戦争が勃発した。しかし新政府軍は約700名程度で列藩同盟側約2500名の駐屯していた白河城を奪還した。同盟軍は白河を経由した関東への進軍を意図し約4500名まで増援を行い7回にわたって攻撃したが、新政府軍は劣勢な兵数で白河城を守りきった。
白河は奥州街道沿いの要地であった。小峰城(白河城)は寛永6年(1629年)に丹羽長重によって改築された城で、仙台藩をはじめとする東北諸藩を仮想敵として設計されていたため、南方は比較的手薄となっていた。
慶応4年閏4月20日、二本松藩兵が守備していた白河城へ田中玄清の息子左内が率いる会津兵と新選組が侵攻しこれを占領した。
新政府東山道軍は宇都宮城の戦いに勝利し、宇都宮を拠点として確保していた。新政府軍は薩摩藩兵を中心とし、大垣藩兵、長州藩兵、忍藩兵で形成されていた。新政府軍は宇都宮から大田原まで進軍していたが、会津による白河城占拠を知った江戸からの指令で、そのまま白河へと前進した。
25日払暁に新政府軍の先遣隊数百名は白坂口へ奇襲をかけて、会津藩遊撃隊と新選組は新政府軍と激しく交戦をした。
新政府軍は長雨でぬかるんだ田地に足をとられ、宇都宮城の戦いでの死闘による疲労と弾薬不足、そして宇都宮からの無理な強行軍の疲労と土地勘の無さも重なり損害を出して芦野へ撤退した。
新政府軍は宇都宮城の土佐藩兵に協力を仰ぎたい所だったが、土佐藩は今市の戦いの最中であった。そこで東山道軍に伊地知正治率いる薩摩藩と長州藩と大垣藩と忍藩の部隊を合流させ増員した。兵力は新政府軍が約700名、列藩同盟軍が2,000から2,500名であった。新政府軍は28日に激しい銃撃戦を展開させて会津兵を撃退させて翌29日に白坂口に本陣を置き、5月1日に白河城の攻略にかかった。
新政府軍は稲荷山を包囲する形となり山上から銃撃を加え、兵力を展開して城下へと突入し白河城を占領した。同盟軍は横山をはじめ幹部多数を失い、約700名の死傷者を出したが、新政府軍の死傷者は20名前後と伝えられ、新政府軍の圧勝に終わった。
この頃新政府軍は関東を完全に制圧できていなかったため、白河城へ増援する余裕が無く、黒川藩によってわずかに兵力を増強できたに過ぎなかった。一方、列藩同盟軍も連携が悪く兵力の集結や総攻撃の決断ができずに、5月16日から17日に小規模の攻撃を行った程度であった。こういった状況の中、仙台藩士細谷直英(十太夫)は、須賀川で奥州の大親分を含む東北地方の侠客・博徒・農民などを糾合して「衝撃隊」を結成し、黒装束に身を包んで長脇差で夜襲攻撃を繰り返した。衝撃隊は新政府軍から「鴉組(からすぐみ)」と呼ばれて恐れられた。
26日、列藩同盟軍はようやく兵力の再集結を終え、約2,000の兵力をもって白河城へ総攻撃をかけた。雨中であり両軍とも小銃の着火に手間取ったが、特に列藩同盟軍では旧式の小銃が多く戦力の大きな低下を招いた。列藩同盟軍はさらに27日、28日と連続して攻撃をかけたが、新政府軍はこれを撃退した。6月に入ると、新政府軍は5月6日の今市の戦いや15日の上野戦争での勝利によって関東から旧幕府勢力を駆逐できたため戦力に余力が生じ、板垣退助率いる土佐藩兵や江戸の薩摩藩兵が白河城へ増援された。列藩同盟軍は6月12日にも白河城へ攻撃を仕掛けたが失敗に終わった。
16日、平潟に新政府軍1500名が上陸。続々と派兵され7月中旬には3000の兵を擁するようになった。平潟の上陸軍に呼応し24日に白河から板垣退助率いる新政府軍が棚倉城攻略のため800の兵を率いて南東へ出発した。棚倉藩は白河と平潟の中間に位置し両新政府軍が提携するために確保する必要があったからである。新政府軍の動きを列藩同盟軍は予期していたが、むしろ白河城奪取の好機と見て白河へ兵力を集結させ、棚倉藩への増援は行われなかった。棚倉城はその日のうちに落城して棚倉藩は降伏した。
25日、列藩同盟軍は予定通り白河城へ攻撃をかけたが失敗。更に7月1日の攻撃にも失敗し、戦況は新政府へ傾き、8日に庄内藩は白河口救援のため大隊を派遣したが、その途上で秋田藩および新庄藩などが列藩同盟から離反したとの報が入ったため、派遣を取りやめ同部隊を新庄藩攻撃の任にあてた。また13日、平潟の上陸軍は平城を占領し、以後軍を再び2つに分け海岸沿い及び内陸へ進軍を開始、三春にて板垣の白河軍と合流した。
列藩同盟軍の白河城への攻撃は14日が最後となった。以降、周辺地域で戦闘が続いたが、白河より北の中通り・浜通りが新政府軍の支配下となったため、これに狼狽した列藩同盟軍は会津藩領を経由し白河周辺から撤退し、白河口の戦いは終結した。
白河口での敗北によって列藩同盟軍は勝機を失い、東北戦争の大勢は決した。
(以上、「Wikipedia」参照)
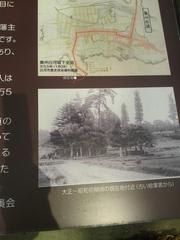 大正、昭和初期のようす。
大正、昭和初期のようす。
奥州街道と白河城下
白河宿は、江戸日本橋を起点とする奥州街道の27番目にあたります。
現在城下を通る街道は、寛永4年(1627)初代白河藩主丹羽長重が、城下町を整備した時の形がほぼ乗っているものです。町境ごとに残る鈎型(かぎがた)は、的の侵入に備えた防備のくふうであり、江戸時代の絵図と現在の街道はそのまま重なります。
記録によれば、寛文年間(1661~73)の白河城下の町人は7千5百人余りで、武家人口と合わせた城下の総人口は1万5千人程と推定されます。
ここ松並は白河城下の入口にあたり、絵図を見ると道の両側には土塁が築かれ、直角に曲がって町に入る形になっています。丹羽長重入封以前には、直線だったと推測される城切り口を敵からの防御を重視して長重が作り替えたものです。
白河市教育委員会
 稲荷山公園。
稲荷山公園。戊辰役古戦場のすぐ先、左側に、戊辰戦争の激戦地だった稲荷山があり、現在は公園となっています。
「奥州街道」は、古代からの官道として、鎌倉期の源義経、江戸期の芭蕉、さらには「明治維新」(戊辰戦争)と歴史・文化のダイナミックな動きに位置する史跡の豊富な地であったことを実感させられます。
「九番町」に入ると、家屋が並び、次第に市街地となります。


(11:29)「谷津田河」に架かる「南湖橋」を渡って、宿場の中心地へ向かいます。


宿内には、宿場らしい古い建物や史跡が残っています。
つるべ井戸。




























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます