あの怖~い山親爺の話である。生物多様性が叫ばれる今、私たちは怖~いヒグマとも共存を図らねばならない。札幌市が主催した「SAPPOROヒグマフォーラム」に参加し、研究者たちの話に耳を傾けた。
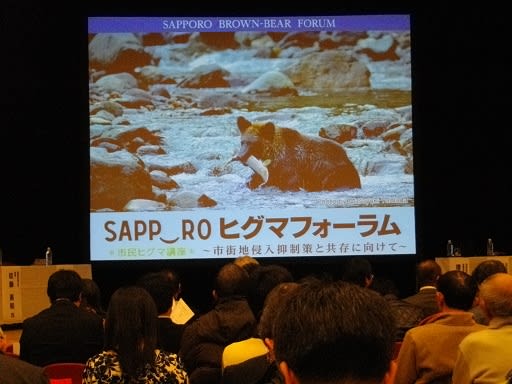
登山愛好者と云えるほど山に登っているわけではないが、それでも時々山に登るときはヒグマの動向が気になる私である。平成23年のときなど、札幌近郊にヒグマが出没したというニュースに接したときには、山へ向かう意欲が萎えてしまった経験もある。
2月1日(月)午後、札幌エルプラザにおいて「SAPPOROヒグマフォーラム 市民ヒグマ講座」が開催され、参加した。フォーラムは2部構成となっていた。
第1部が「知床のヒグマ事情 ~知床世界自然遺産における保護管理~」と題して、知床財団事務局長の増田泰氏が基調講演をされた。
続いて第2部では、「市街侵入抑制策と共存に向けて」と題するパネルディスカッションに5名が登壇され、さまざまな角度からテーマに迫った。
基調講演において増田氏は概略次のように語った。
世界自然遺産管理区域におけるヒグマは基本的には保護される動物である。したがって、知床財団としてはヒグマと人間の接触を避けるように努めている。
その対策方針(ヒグマ保護管理方針)は、「ゾーニング」と「行動段階」によって対策を行っているとした。
ゾーニングとは、知床地域を段階的に5つのゾーンに分類しているという。
それは、1~国立公園奥地など。2~森林。3~国立公園遊歩道など。4~農村地域。5~市街地の5つに分類しているそうだ。
さらに行動段階を4段階に設定し、0段階~回避・逃走。1段階~逃げない。2段階~実害。4段階~攻撃の4段階に設定しているという。
この二つの要素を組み合わせて、最善の対策を講じているということだった。
次に、ヒグマとの共存を目指すための「知・守・伝」について触れた。
「知」とは,クマを知ることである。そのための調査研究は欠かせないとした。
「守」とは、クマを守る。人を守ることである。そのために(1)誘引物などの除去などの「予防対策」。電気柵の設置などの「防御対策」。威嚇や追い払い、捕獲などの「直接的対策」を進めているということだった。
「伝」とは、地域住民、知床観光客へのヒグマのことを伝える啓宣・啓発活動を地道に進めることも大切であるとした。
最後に増田氏は、ヒグマは優れた環境対応能力があるとした上で、人が変わることで回避できることもあると指摘して講演を終えた。
続いてパネルディスカッションに移ったが、こちらもなかなか興味深いディスカッションだったので、詳しくレポしたいと思うので、明日に続けたいと思う。
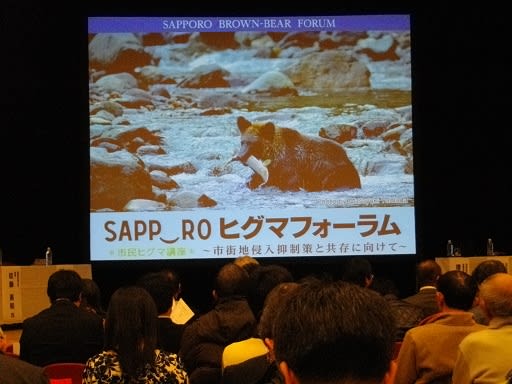
登山愛好者と云えるほど山に登っているわけではないが、それでも時々山に登るときはヒグマの動向が気になる私である。平成23年のときなど、札幌近郊にヒグマが出没したというニュースに接したときには、山へ向かう意欲が萎えてしまった経験もある。
2月1日(月)午後、札幌エルプラザにおいて「SAPPOROヒグマフォーラム 市民ヒグマ講座」が開催され、参加した。フォーラムは2部構成となっていた。
第1部が「知床のヒグマ事情 ~知床世界自然遺産における保護管理~」と題して、知床財団事務局長の増田泰氏が基調講演をされた。
続いて第2部では、「市街侵入抑制策と共存に向けて」と題するパネルディスカッションに5名が登壇され、さまざまな角度からテーマに迫った。
基調講演において増田氏は概略次のように語った。
世界自然遺産管理区域におけるヒグマは基本的には保護される動物である。したがって、知床財団としてはヒグマと人間の接触を避けるように努めている。
その対策方針(ヒグマ保護管理方針)は、「ゾーニング」と「行動段階」によって対策を行っているとした。
ゾーニングとは、知床地域を段階的に5つのゾーンに分類しているという。
それは、1~国立公園奥地など。2~森林。3~国立公園遊歩道など。4~農村地域。5~市街地の5つに分類しているそうだ。
さらに行動段階を4段階に設定し、0段階~回避・逃走。1段階~逃げない。2段階~実害。4段階~攻撃の4段階に設定しているという。
この二つの要素を組み合わせて、最善の対策を講じているということだった。
次に、ヒグマとの共存を目指すための「知・守・伝」について触れた。
「知」とは,クマを知ることである。そのための調査研究は欠かせないとした。
「守」とは、クマを守る。人を守ることである。そのために(1)誘引物などの除去などの「予防対策」。電気柵の設置などの「防御対策」。威嚇や追い払い、捕獲などの「直接的対策」を進めているということだった。
「伝」とは、地域住民、知床観光客へのヒグマのことを伝える啓宣・啓発活動を地道に進めることも大切であるとした。
最後に増田氏は、ヒグマは優れた環境対応能力があるとした上で、人が変わることで回避できることもあると指摘して講演を終えた。
続いてパネルディスカッションに移ったが、こちらもなかなか興味深いディスカッションだったので、詳しくレポしたいと思うので、明日に続けたいと思う。









