7月2日の朝日歌壇とともに進めます。 3日小国川へ行ってきました。
いやあ、さすが山形県、さくらんぼだけでなく天気まで素晴らしい!!快晴です。 東根市から村山あたりでは朝の7時10分くらいというのに、暑いのです。まるで真夏、盛夏を思わせる暑さ。猛暑を感じたくらいです。 これぞ夏!です。
もっとも北上するにつれて、薄曇りとはなりましたが、うすら寒い天気はどこえやら、水に入っても全く寒さを感じることはありませんでした。 小国川の朝の水温は20.5度でした。
囮屋さんの話を聞くと、解禁日と翌日はヤマセが吹いて肌寒く、全く釣りにならなかったようです。28日の調査釣りでの爆釣は、きょう(3日)のようにいい天気だったからということです。
しかも水量は極端に少なかったようです。 きのう(2日)に雨が降って何とかよくなったとか。
ということは、気温も水量もきょう(3日)が一番いい条件であるということになりそうです。
鮎釣り大会のメイン会場となる「一関大橋」の下流側の様子です。

上下の2枚は朝方8時前後の様子です。 駐車場には県外ナンバーの車がかなりありました。

以下の写真は午前10時頃の写真です。

釣り人は大会のようにずらーと並んでいたのですが、見ていてもなかなか掛かりません。そのうち2,3人は移動を始めたり。

橋の上流側です。 水量が少ないのがお分かりでしょう。これでも前日よりは増えています。 川の中のいしの頭が真っ白になっている石が結構あります。

小国川の釣行目的は殊勝にも8日のシマノの大会の為の下見、事前準備です。 上流側から下流側へ移動しようと考えました。
最初は上流の砂利工場の向かい側付近の、深さ腰下のとってもいい平瀬に入りました。 下流側に地元の人、上流側に福島の人(車の番号で判別)が竿を出していました。 福島の釣り人は大変です。地元で竿を出せないなんて、気の毒極まりないです。
『アユ・ウグヒ阿武隈川にセシウムの検出されて瀬音さびしき』 (福島県:谷口 修作さん)
地元の人にあいさつをしても返事がなかったのですが、福島の人とは話をしながら竿を出しました。 2時間でやっと1匹掛かったという。 川を見るとアユが跳ねています。目印の付近でピョンとやられると頭にきますよね。
二人の間に入って竿を出しました。8時50分スタートです。9時12分頃軽い当たりが伝わりました。そもそも型が小さいから当たりも小さいだろうという心構えをしていましたので、細心の注意をしながら引き抜きました。 今年度初めての掛かりアユです。囮よりも小さいですが、綺麗です。 15センチくらいですか。 掛かってくれただけでもありがたい。 アユに感謝です。


(左側) (上側)
『美しき鮎は風土記の昔より良き匂ひもてこの川上る』 (日立市:加藤 宙さん)
小国川の鮎は昔から「松原鮎」として大切にされてきました。将軍家に献上したとか。
ここで30分で何と3匹も掛かってしまいました。さらに10分竿を出しましたが当たりなし! でも根がかりが2かもありました。 川底には枝の切れ端等が結構沈んでいるようです。 気を付けないと。 といっても見えませんので如何ともしがたいですが。
40分で上がって、こんどは経壇原へ。大岩や大石がごろごろあるところですが、5,6人釣り人がいました。釣り人の間隙をぬって、流れの芯を超えて右岸側へ。いつも大会でも掛かっているところに入れました。 さてここではどれだけ掛かることやらと内心期待していたのですが、・・・。
結果はゼロ!坊主です!!一体どういうことでしょうか??周りの人も掛かっていなかったようですが、下流側の芯を釣っていた人に1匹掛かったのを見ました。1時間竿を出して釣果ナシ!!でも最後の方でおとり鮎を空中輸送してポイントへ入れたら、ほとんど着水と同時ガツーンという強い当たり。引き込まれます。右岸の草むらに持って行かれないように必死に竿を寝かせて、こちら側に寄せようとしたのですが、敵も然るもの、少し寄ってはまた戻ります。少し水中の魚が見えました。もうこれは鮎ではありえない、二ゴイだろうと思ったのですが、もしかしたらサクラマスかもとも思いました。
水中で見えた魚体はずんぐりむっくりしているように見えたので、二ゴイではなかったのかもしれません。二ゴイにしては小さいし、力も強くない感じ。 まあどちらにしても下の点け糸から切れてしまいました。水深もあり水量も流れもあるので無理だとは思っていたのですが。
その後一関大橋の様子を観察しました。 今度は下流側へ移動です。
障害者用トイレのあるところにはテトラポットがあり、手前は長い瀬に、右岸側は浅いトロ場から急瀬へとつながります。それぞれのところに一人ずつ竿を出していたので車から見ていました。 掛かっている様子はなかったのですが、ポイントとしてはいい感じなので実際に川に入って見てきました。食み跡はあります。
あとで瀬で釣っていた岩手県の人に聞いたのですが、それぞれのポイントで2匹くらいしか掛からなかったようです。
次に釣りの用意をして下流R13号線下へ向かいました。R13の上流側は浅いトロ場で、昼過ぎればナイロン糸での泳がせ釣りには面白いところです。
R13の下流は幅10メートルくらいに絞られてカーブしています。去年のダイワのときかなここで一人だけバカ釣れしている人がいました。私も鉄橋下から戻ってくるとき人がいなくなったここで竿をだし、4匹入れがかりでした。
竿の操作がしにくいのが辛いところです。9メートルの竿ではR13の橋にぶつかってしまいます。 約1時間で何とか3匹掛かりました。 掛かると小気味よい引きが感じられ、これが鮎釣りなんだと実感します。
ということで十分下見とはとても言えませんが一応それなりに最下流部まで見てきました。R13の下流に奥羽本線(山形新幹線)の鉄橋があるのですが、新庄駅が近くのためやまびこは減速して走ります。 往復で3回見ました。いいものですね、まじかに川から見上げるというのも。
『腸(わた)を抜き輪切りにしたり若鮎の瀬ごし言ふは刃の切れ味』 (長野県:沓掛 喜久男さん)
鮎は義父に持って行きました。
































 たった1匹でした。
たった1匹でした。


























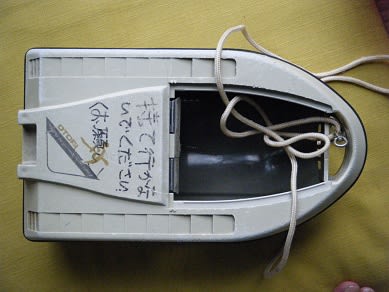


 ゲンゴロウですか、
ゲンゴロウですか、


 7月8日(日)開催
7月8日(日)開催 

























 (カモも困ってしまいます。)
(カモも困ってしまいます。)



 20センチくらいの鮎です。
20センチくらいの鮎です。















 (最後の2枚は我が家のあじさいです)
(最後の2枚は我が家のあじさいです)
 (ウミドリが逃げません。)
(ウミドリが逃げません。)














