「体は棺桶の中に入ってても、魂は、シュウちゃんのところに行くからよ」
2017読了16
『峠うどん物語(下)』(重松 清 講談社文庫)
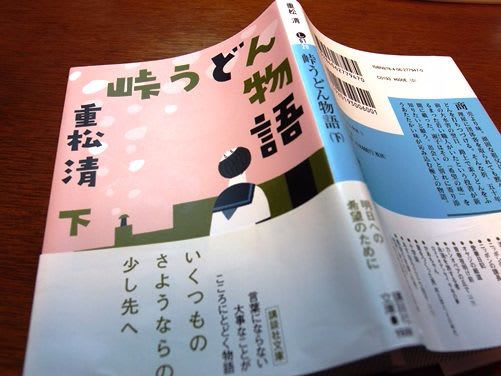
上巻同様、連作短編の形をとっているが、下巻は作ごとの関連が少し強くなっている。うどん職人の祖父に関わる人物が複数登場し、祖父の姿がより鮮明になると言ってもいいだろう。一途に仕事を続けてきた者には必ず矜持があり、その魂を見失わず全うし続ける重みが伝わってくる。「導き」という言葉が浮かぶ。
上巻には「軽食設定」という趣を書いた。下巻を読了すると、ちょっと質が違ってくる。一杯のうどんが持つ温かさ、陳腐な表現だが、その一杯には「葬」と向き合った心を解す力がある。「斎場のすぐ近くにある小さなうどん屋」を舞台にすると、それだけを作者は書き出す前から決めた。その設定で人が動くのだ。
物語の中に込められている作者の社会批評的な目がひしひしと感じられた。斎場に大型店のチャーターするバスが行き交うようになったこと、個人医院と大型病院における終末期医療の問題など、私達の身近にもある現象が、一種の仕組みのようにして現れてくる。生死の問題までシステム化が浸透している社会だ。
「あとがき」に、この話が小説誌への不定期連載という形で書かれ、全篇完結に五年半かかったと記されている。こんな連作は初めてで、今後もないだろうとあった。それだけの時間を費やしたのは、手打ちのうどん屋商売とも似ている。つまりはそこでしか出せないもの、自動化、量産化への抵抗であると見たい。
2017読了16
『峠うどん物語(下)』(重松 清 講談社文庫)
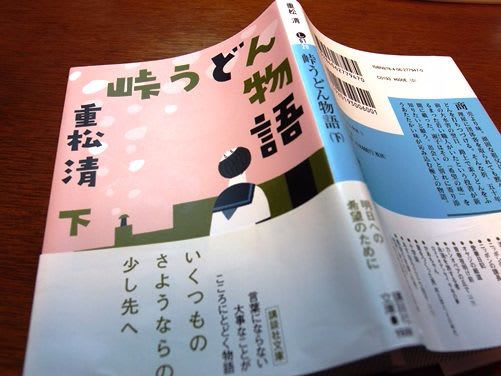
上巻同様、連作短編の形をとっているが、下巻は作ごとの関連が少し強くなっている。うどん職人の祖父に関わる人物が複数登場し、祖父の姿がより鮮明になると言ってもいいだろう。一途に仕事を続けてきた者には必ず矜持があり、その魂を見失わず全うし続ける重みが伝わってくる。「導き」という言葉が浮かぶ。
上巻には「軽食設定」という趣を書いた。下巻を読了すると、ちょっと質が違ってくる。一杯のうどんが持つ温かさ、陳腐な表現だが、その一杯には「葬」と向き合った心を解す力がある。「斎場のすぐ近くにある小さなうどん屋」を舞台にすると、それだけを作者は書き出す前から決めた。その設定で人が動くのだ。
物語の中に込められている作者の社会批評的な目がひしひしと感じられた。斎場に大型店のチャーターするバスが行き交うようになったこと、個人医院と大型病院における終末期医療の問題など、私達の身近にもある現象が、一種の仕組みのようにして現れてくる。生死の問題までシステム化が浸透している社会だ。
「あとがき」に、この話が小説誌への不定期連載という形で書かれ、全篇完結に五年半かかったと記されている。こんな連作は初めてで、今後もないだろうとあった。それだけの時間を費やしたのは、手打ちのうどん屋商売とも似ている。つまりはそこでしか出せないもの、自動化、量産化への抵抗であると見たい。









