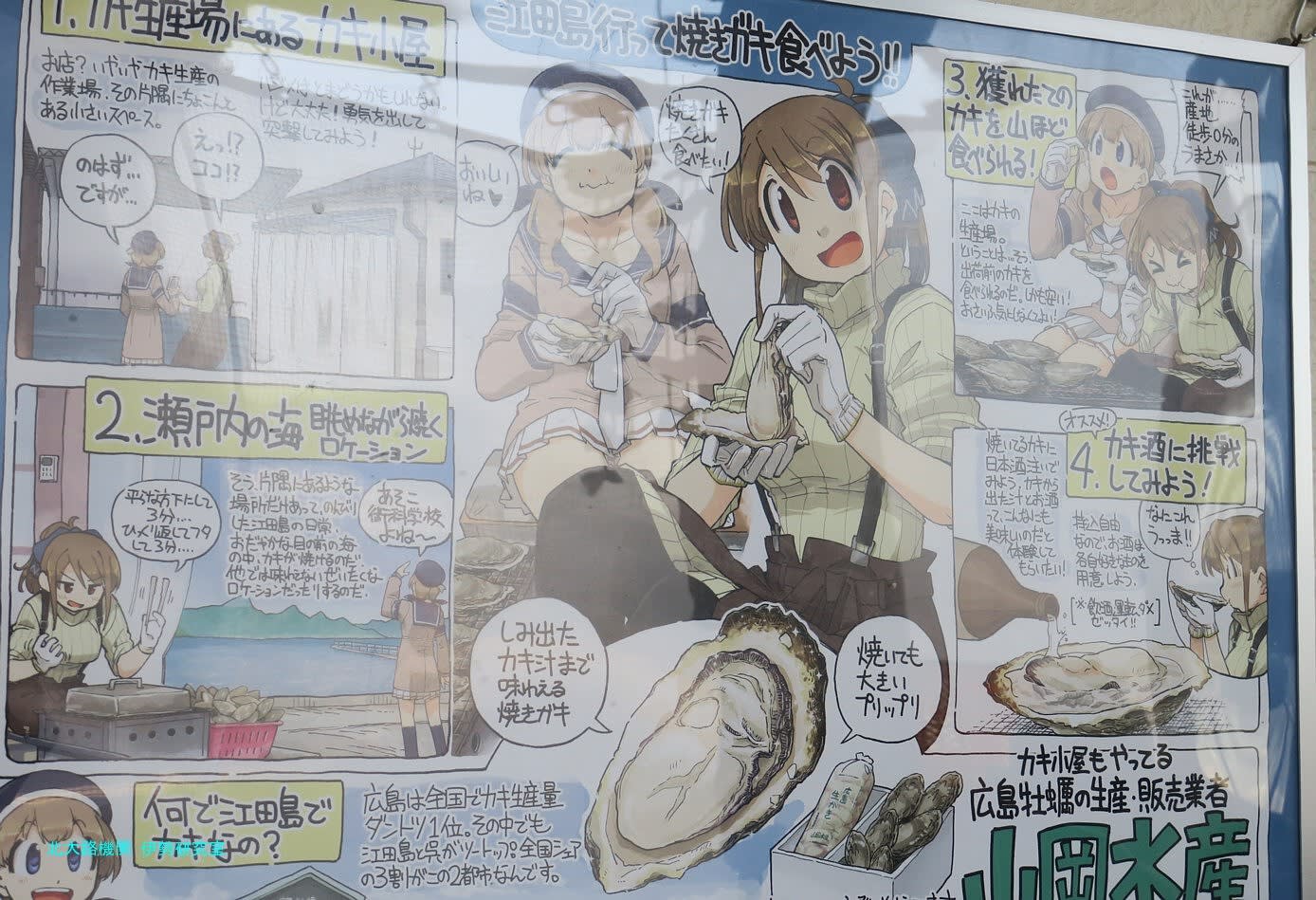■梅花そして桜花
京都市でも山科区は梅花の開花が遅い方なのですが今年は異常な早咲きと云えました、けれどもそれに続く桜花の開花はまだ先か。

勧修寺、梅花の名所、と明記されているわけではなくこのあたりでは隨心院の梅林が有名となっています。梅林を眺めるならば隨心院、なのかもしれませんが、隨心院さんの梅林は三月中旬まで非公開となっていて、しかし梅花開花は待ってくれません。

隨心院で梅林を昨年は眺められたものの、今年の梅花は開花が早く、しかし寒の戻り、特に寒さが戻るとともにかなりの風雨が定期的に梅林を洗い流してしまいましたから、思ったのはこれ、隨心院さんが梅林を公開するころはもう梅花、散っているだろうなあ。

氷室池のまわりに梅花が咲き誇っていましたのは、嬉しい誤算というべきでしょうか、これも西日が強く逆光のように白梅の真白さを強調してくれましたので、若干陽光がレンズに影響を及ぼしはしたものの、これは幻想的な情景、春を感じさせる一瞬と思う。

応仁の乱により荒廃した寺院ですが、江戸時代に入りますと本格的に復興します。安土桃山時代の間には豊臣秀吉の街道整備により氷室池が半分以上埋め立てられるなど郊外に追い打ちを掛けられてしまいますが、江戸時代に本堂などが復興されることになって。

本堂再建は寛文12年こと西暦1672年のことでして、霊元天皇仮内侍所が下賜されることとなり、本尊千手観世音菩薩立像を奉じています。ここ、春の特別公開では内部が御開帳となるのですが、この日は梅花の先にご本尊を思い浮かべこうべたれるのみ。

観音堂と梅花、これが京都らしい情景と思うのですが、この観音堂は昭和初期の再建という。もっとも再建というからには初代があるはずなのですが、当地に観音堂が情景に溶け込んだ始まりの時代がいつなのかは、ちょっとしらべられるにはいたっていません。

雪景色、そう雪は少なかった、というのは暦の上での冬には暖冬であって、これも異常気象だとかスキー場がたいへんとか、もう梅が咲いたというような、暖冬を印象づける話題が続いていて、三月中旬には桜が咲きそうな、そんな熱気がこもっていまして。

熱い冬、なんて考えたものですが今度は寒い春が来ました。沈黙の春、レイチェルカーソンの大著ではないのですが寒すぎて立春の日には寒の戻りを痛感したものですが、一過性と思っていて桜花開花の季節も三月中旬を過ぎたあたり、と予想されていました。

桜花を考えれば昨年こそ寒い冬の先に熱い春が来た、なにしろ平野神社の桜花祭のころには全て葉桜で観桜を当て込んだ観光業が二週間も外れてぎゃくに閑古鳥なんてCOVID-19から立ち直りつつある京都の景気にまた沁みて痛い一撃を加えたものでしたが。

寒の戻り、しかし考えると開花の時期は一か月半は長く咲いていましたので、もちろん、満開の絶景、という期間は短く、特に早咲きと遅咲きの梅花満開の時機が大きく間が開いてしまいましたので、割いている様子は長く楽しめたが満開は中々愉しめなかった。

春の訪れ、そういえば昨年は梅花から桜花への転換に合間が無かったようにもおもえるのですけれども、今年は、来週に開花という。すると見ごろは四月に入ったあたりか。異常気象異常気象と言っていたのは立春までで、桜花は例年通りという。不思議ですね。

熱い冬と寒い春、さてこれから春本番となるのですが昨年は熱い春の先に灼熱の夏という表現でさえ甘いほどの40度越えの真夏がやってきました、気象庁の長期予報では例年より熱いという予報がでましたが、さてさて、異常気象が平常となるのか気懸りです。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)
京都市でも山科区は梅花の開花が遅い方なのですが今年は異常な早咲きと云えました、けれどもそれに続く桜花の開花はまだ先か。

勧修寺、梅花の名所、と明記されているわけではなくこのあたりでは隨心院の梅林が有名となっています。梅林を眺めるならば隨心院、なのかもしれませんが、隨心院さんの梅林は三月中旬まで非公開となっていて、しかし梅花開花は待ってくれません。

隨心院で梅林を昨年は眺められたものの、今年の梅花は開花が早く、しかし寒の戻り、特に寒さが戻るとともにかなりの風雨が定期的に梅林を洗い流してしまいましたから、思ったのはこれ、隨心院さんが梅林を公開するころはもう梅花、散っているだろうなあ。

氷室池のまわりに梅花が咲き誇っていましたのは、嬉しい誤算というべきでしょうか、これも西日が強く逆光のように白梅の真白さを強調してくれましたので、若干陽光がレンズに影響を及ぼしはしたものの、これは幻想的な情景、春を感じさせる一瞬と思う。

応仁の乱により荒廃した寺院ですが、江戸時代に入りますと本格的に復興します。安土桃山時代の間には豊臣秀吉の街道整備により氷室池が半分以上埋め立てられるなど郊外に追い打ちを掛けられてしまいますが、江戸時代に本堂などが復興されることになって。

本堂再建は寛文12年こと西暦1672年のことでして、霊元天皇仮内侍所が下賜されることとなり、本尊千手観世音菩薩立像を奉じています。ここ、春の特別公開では内部が御開帳となるのですが、この日は梅花の先にご本尊を思い浮かべこうべたれるのみ。

観音堂と梅花、これが京都らしい情景と思うのですが、この観音堂は昭和初期の再建という。もっとも再建というからには初代があるはずなのですが、当地に観音堂が情景に溶け込んだ始まりの時代がいつなのかは、ちょっとしらべられるにはいたっていません。

雪景色、そう雪は少なかった、というのは暦の上での冬には暖冬であって、これも異常気象だとかスキー場がたいへんとか、もう梅が咲いたというような、暖冬を印象づける話題が続いていて、三月中旬には桜が咲きそうな、そんな熱気がこもっていまして。

熱い冬、なんて考えたものですが今度は寒い春が来ました。沈黙の春、レイチェルカーソンの大著ではないのですが寒すぎて立春の日には寒の戻りを痛感したものですが、一過性と思っていて桜花開花の季節も三月中旬を過ぎたあたり、と予想されていました。

桜花を考えれば昨年こそ寒い冬の先に熱い春が来た、なにしろ平野神社の桜花祭のころには全て葉桜で観桜を当て込んだ観光業が二週間も外れてぎゃくに閑古鳥なんてCOVID-19から立ち直りつつある京都の景気にまた沁みて痛い一撃を加えたものでしたが。

寒の戻り、しかし考えると開花の時期は一か月半は長く咲いていましたので、もちろん、満開の絶景、という期間は短く、特に早咲きと遅咲きの梅花満開の時機が大きく間が開いてしまいましたので、割いている様子は長く楽しめたが満開は中々愉しめなかった。

春の訪れ、そういえば昨年は梅花から桜花への転換に合間が無かったようにもおもえるのですけれども、今年は、来週に開花という。すると見ごろは四月に入ったあたりか。異常気象異常気象と言っていたのは立春までで、桜花は例年通りという。不思議ですね。

熱い冬と寒い春、さてこれから春本番となるのですが昨年は熱い春の先に灼熱の夏という表現でさえ甘いほどの40度越えの真夏がやってきました、気象庁の長期予報では例年より熱いという予報がでましたが、さてさて、異常気象が平常となるのか気懸りです。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)