
リバーサイド修景事業で整備された茨城百景記念公園と常夜灯。境河岸は、かつて江戸中期より明治にかけて、主に江戸と東北を結んだ利根川水運において大きな役割を果してきました。
その境河岸の主役的存在であったのが高瀬舟です。高瀬舟は、かつて利根川、江戸川と共に「河岸の街”さかい”」の繁栄を担ってきました。
当時を偲び高瀬舟(さかい丸)を、観光船として現代風に復元しました。

※現在、運航していません。(「境町HPより)
「茨城県稲敷郡境町」。今回のように街道歩きをして初めて知ったところです。
境町はどこに? 

橋を渡って信号を左折します。
電柱に利根川が氾濫したときの水没の高さが赤い線で示されています。見上げるほど高さで、7.1㍍と標示されています。
2階屋根の高さ。 対岸の埼玉県でも見かけたことがあります。
対岸の埼玉県でも見かけたことがあります。
正面、突き当たりを左に曲がれば利根川の土手。渡し場になっています。右折すると、境町の中心となります。

利根川土手方向。
利根川付近の今昔。






1880年代のようす。渡し場がある。繁栄する境町。 2010年代のようす。利根川の改修で様変わり。
右角にある古びた建物。

旧街道沿いの街並み。
人通りもなく、静か。
昔を偲ばせるものはあまりなさそうです。
興味深いバス停が。 自動運転バスのりば。
自動運転バスのりば。
境町で運行している自動運転バスは、仏ナビヤ社製の「ナビヤ アルマ(NAVYA ARMA)」で乗車定員は最大15人。境町での実際の走行時には、定員は11人と定めて運行している(新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴い現在はオペレーター除き8人まで)。また、運行をサポートするオペレーターが常に1人同乗する(定員に含む)。運行当初は、オペレーターに加えて、安全を確認する役割の監視員も同乗させていたが、途中から監視員を置かず運用できるようになった。
実際に乗り込んでみると、社内はさほど広くはないが、窓が大きく閉塞感は少ない。最高速度が低く抑えられていることもあり、スタートや停止などはスムーズで、乗り心地は悪くない。もちろん加速感や減速感はそれなりにあり、「横に動くエレベーターという感じだと思っていただきたい」(橋本町長)という言葉も納得できる。
車内は窓が大きく開放感がある。車内後方にはオペレーターが同乗し安全監視や緊急時の操作などを行う(写真右)。手にしているゲーム機のようなコントローラーで操作する(写真:高山透)
バスは、あらかじめ登録された地図情報とGPSによりルートの位置情報を把握し、そのルートに沿って走る。バスの外に設置されたセンサーにより、障害物がないか360度周囲の状況をリアルタイムで感知しながら走っている。
運行は信号待ちからの再発進などのときを除き基本的に自動だが、オペレーターは乗客の乗り降りの安全確認や、赤信号の停止状態から交差点を通過する際の発進を確認したりする。また、全体の運行状況をリアルタイムで監視する遠隔監視センターも設置されており、同時に走る2台の自動運転バスの現在の状況をチェックしている。
バス内のモニターにあらかじめ組み込まれた路線データが映し出される。モニターには障害物センサーがリアルタイムに検出している周囲の建物や障害物の映像を表示することもできる(写真:高山透)
遠隔監視センターでは運行中の2台の自動運転バスの状況を車載カメラの映像を通じてリアルタイムで監視している(写真:高山透)
郵便局や病院、役場など主要施設を結ぶ“旧道”を運行
自動運転バスが走る路線は2系統あり、ともに「道の駅さかい」をターミナルとしている。1つは、東京との直行バスの発着する高速バスターミナルを結ぶ約8㎞のルートで、ショッピングセンター(エコス)、境高校などを経由する。もう1つはシンパシーホール(勤労青少年ホーム)を結ぶ約6㎞のルートで、医療施設や育児施設を通っている。ともに、銀行や町役場、小学校を経由する。
運行路線は2つある。1つは高速バスターミナル行き路線(左)でショッピングセンターのエコスや境高校を経由する。もう1つは市民ホールのシンパシーホール行き路線(右)で郵便局や医療施設を経由する(資料:境町)
境町の主要施設を結ぶ自動運転バスのルートは、町内を南北に走る県道17号線や、東西に走る県道137号線は通らない。交通量の多い幹線道路を避け、いわゆる市街地の“旧道”を選んでいる。利用者として想定している高齢者などがよく使う場所を考えたのはもちろんだが、自動運転バスは、最高速度が20㎞で運用されているため、片側2車線ある幹線道路を走ると他の車両との速度差が大きくなり、他の車両に与える影響や危険が増すと考えたためだ。
運行しているルートは、片側1車線の対面通行の道路がほとんどだ。信号のある交差点は少ないものの、町の主要生活道路であり、普段から自動車の通行量はそれなりにある。さらに従来からあるバス路線もそこを通っている。その中を、最高速度が20㎞の自動運転バスが走ると、後続の自動車による渋滞も発生する。
運用開始当初は、渋滞が多く発生したり、後続の自動車が無理に追い越すというケースも多かったが、バス停の間隔を狭めて停車時に後続が追い越す場所を増やしたり、バス停付近の停止位置を変えて追い越しやすくするなど、最高速度は変えずに渋滞を減らす工夫を重ねていった。
商店街の中を走る自動運転バス。運行ルートは片側1車線・対面通行の道路がほとんどだ(写真:高山透)
自動運転バスのバス停。法規上は既に営業している路線バスと同じ場所にバス停を置けないため独自に設置している。なるべく停車スペースを取って後続のクルマが追い越しやすいように配慮している
渋滞がさほど問題にならなくなってきたのは、「自動運転バスが町民の中に定着してきたことが大きい」と、自動運転バスの運行業務を受託しているボードリーの佐治友基社長は言う。
佐治社長は、自身もオペレーターとして実際に運行中のバスに乗り込んだ経験があり、自動運転バスに対する町民の受容の変化について、実感を込めてこう語る。
自動運転バスの運行システムや運用を担うボードリーの佐治友基社長(写真:高山透)
「どのルートを通っているか認知されてきたことで、急ぐ必要があるクルマは別の道路を使うといったことで自発的に渋滞を回避してくれていると感じます。よく利用する高齢者は、道ですれ違っても挨拶してくれるようになったり、病院の前を通るときには、入院している患者さんが手を振ってくれたりすることもあります」
1年間の利用者は約5300人、2年間で約7億円の効果
前述のように、運用開始から1年を経て安全性については問題が起きていない。自動運転バスを町の新しい交通インフラとして導入した成果を橋本町長に聞いた。
「まだ路線は限られているとはいえ、町内の交通弱者に自力で移動できる手段を1つ提供できた意味は大きいと考えています。また、副産物として、この小さな町がメディアに取り上げられたり、自動運転バスに関心を持つほかの自治体や研究機関からの視察が増えたりしたことで、境町のブランド力は大きく向上したと思います。これが、ふるさと納税の伸びや移住促進にも貢献していると考えています」
境町の自動運転バスのこの1年間の経緯と実績については、運用を受け持つボードリーが「2021年度 安定稼働レポート」として公表している。それによると、自動運転バスの運用にかかる費用は、2020年4月から2025年3月までの運行準備期間を含む5年間で約5.2億円。2021年度からは事業費の2分の1は地方創生推進交付金が交付されるため、残りは境町の予算でまかなっている。
この出費に対して、生じた経済効果は、メディアに取り上げられたことによる知名度向上による広告効果や視察や寄付の増加による効果などを金銭換算すると2年間で約7億円になるとボードリーは試算している(同社が2月8日に発表したリポートでは6億円と試算していたが現在は約7億円に修正)。
これを受けて、境町では自動運転バスの運行路線をさらに拡大していくことを計画している。現在の2路線に加えてさらに第3期、4期、5期と町内のカバー範囲を広げるよう新たに路線を増やす計画だ。人口が少ない地域へ路線を広げると、利用者数や利用頻度が低下することが予想されるが、そこは、スマートフォンアプリによるオンデマンドで車両を予約できるようにするなどで、効率化を図る考えだ。路線の拡大とアプリの導入については、令和3年度中に着手する。利用料金はこの先も現在と変わらず無料を維持したいと考えている。
今後の自動運転バスの路線延長計画。現在の第2期にまでのルートに加えて保育園までのルートなど境町全域に広げていく計画だ(資料:境町)
自動運転バスは住民が育てるもの
定常運航から1年を経て、自動運転バスはどんな変化を境町にもたらしたのだろうか。 まず、多くのメディアに取り上げられることによって町の知名度向上に貢献したことは間違いないだろう。前述のように町への視察件数が1年間で100件を超えたことからも、知名度アップは明らかだといえるだろう。自動運転バスが新しく町の名物になったことは、自動運転バスにちなんだお土産品が売られるようになったことからもうかがえる。
境町の観光スポットの1つである河岸の駅さかいでは、自動運転バスをモチーフにしたお土産品が売られるようになった。
町民の受容も進んだ。自動運転バスの「スピードの遅さ」は交通渋滞を引き起こす要因となるが、ボードリーのリポートによると、交通渋滞は1年間で9割減少したという。これは、自動運転バスの運行に協力的な町民が増えたということだ。運行に関する工夫やPR活動が奏功したのはもちろんだが、町民の間に自動運転バスの運行事情に対する認知が進んだ結果、街の暮らしの中に自動運転バスの存在が馴染んできたということだろう。また、様々なメディアで報じられ高い評価を受けたことも、住民のシビックプライド醸成につながり、そのことが運行に協力的な姿勢へとつながったと考えられる。
橋本町長は「まだすべての町民に完全に受け入れられたわけではないが、これからさらに広く町民が恩恵を受けられるよう実績を重ねていきたい」と語る。自動運転バスをスムーズに走らせて交通弱者である高齢者などがその利便性を十分に享受するためには、単に、ハードとソフトを地域に導入するだけでなく、そこに暮らす町民全体がその役割を認識し、運行に協力する姿勢を持つことが重要といえそうだ。
自動運転バスは、やはり「住民が育てる大きなペット」のようなものかもしれない。
この記事のURL https://project.nikkeibp.co.jp/atclppp/PPP/434167/022100208/
(この項、「 」HPより)
」HPより)
向こうからやってきます。 けっこう人が乗っています。
けっこう人が乗っています。
通りを歩いていて二度ほど出会いました。
ユニークな取り組みで期待できます。

昔ながらの商家。
ここにも「想定最大水深」。6.6㍍。 人の背丈の3倍以上。
人の背丈の3倍以上。
この辺が商店街の中心。
「境中央名店街」バス停。
境車庫までけっこう歩きます。



今回はここで終了。「境車庫」から朝日バスで東武線「東武動物公園駅」まで出ました。
 堂々たる長屋門。
堂々たる長屋門。
 「五三の桐」の紋が。
「五三の桐」の紋が。
 「作ノ谷」交差点。
「作ノ谷」交差点。





 「吉田用水」が右手から近づいてきます。
「吉田用水」が右手から近づいてきます。



 吉田用水。
吉田用水。

 水戸線の踏切が前方に。
水戸線の踏切が前方に。




















 遠くに筑波山。
遠くに筑波山。










 明治維新の戦乱に翻弄された宿場でした。
明治維新の戦乱に翻弄された宿場でした。







 馬頭観音。判読不能です。
馬頭観音。判読不能です。









 戊辰戦争に関わるもののようです。
戊辰戦争に関わるもののようです。


 シャープ結城太陽光発電所。
シャープ結城太陽光発電所。 「大戦防」交差点。
「大戦防」交差点。
 「諸川」交差点。
「諸川」交差点。 「諸川宿」には、古い家並みが残っています。
「諸川宿」には、古い家並みが残っています。





 奥に工場が広がっています。
奥に工場が広がっています。



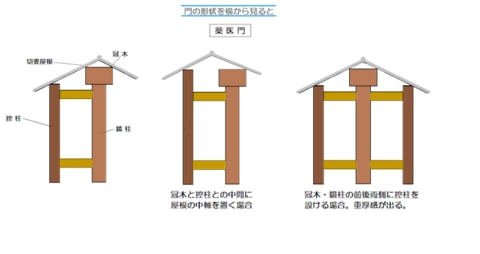










 1880年代のようす。宿らしい街並み。
1880年代のようす。宿らしい街並み。


 2010年代のようす。里山風景は変わらない。
2010年代のようす。里山風景は変わらない。






 門内のようす。
門内のようす。















 「仁連」交差点。
「仁連」交差点。

 諸川交差点。
諸川交差点。
 「圏央道」。
「圏央道」。 門から母屋まで遠い。
門から母屋まで遠い。




 「谷貝」。宿場があったところです。
「谷貝」。宿場があったところです。
 麦畑。
麦畑。




 「初見関吉翁事蹟」」碑。
「初見関吉翁事蹟」」碑。 

 「初見肥料店」。
「初見肥料店」。 



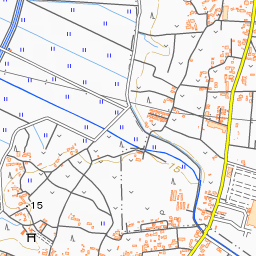








 対岸の埼玉県でも見かけたことがあります。
対岸の埼玉県でも見かけたことがあります。 











 自動運転バスのりば。
自動運転バスのりば。








 」HPより)
」HPより) けっこう人が乗っています。
けっこう人が乗っています。

 人の背丈の3倍以上。
人の背丈の3倍以上。






 「鈴木貫太郎翁終焉之地」碑(吉田茂謹書)。
「鈴木貫太郎翁終焉之地」碑(吉田茂謹書)。


 左手遠くに「関宿城博物館」。
左手遠くに「関宿城博物館」。





 富士山。
富士山。














 正面。
正面。










 「長命庵」。
「長命庵」。 (「長命庵」HPより)
(「長命庵」HPより) 
 その下に
その下に
 町の花ボタン。
町の花ボタン。 町の木イチイ。
町の木イチイ。









 1880年代のようす。両岸の賑わいぶりが知れる。
1880年代のようす。両岸の賑わいぶりが知れる。


 2010年代のようす。○が「関所跡」碑の付近。
2010年代のようす。○が「関所跡」碑の付近。 






 朝礼中のお店。
朝礼中のお店。
 ちょっと弱々しい印象。
ちょっと弱々しい印象。
 「柏寺」バス停。
「柏寺」バス停。 東葛飾病院。
東葛飾病院。

 →関宿城埋門案内。
→関宿城埋門案内。














 「新宿(あらじゅく)」交差点。
「新宿(あらじゅく)」交差点。

 「いちいのホール」。
「いちいのホール」。






 3月始め以来の江戸川土手。
3月始め以来の江戸川土手。






 「船形」地区。
「船形」地区。


 「中里宿」とありました!
「中里宿」とありました! 本陣だったおうち?
本陣だったおうち?
 モッコウバラ。
モッコウバラ。 「関宿」の地名が。
「関宿」の地名が。




 この道が旧道?
この道が旧道?





 大きな墓地。
大きな墓地。 そこで休憩しよう。
そこで休憩しよう。


 野馬土手。
野馬土手。


 左手が野馬土手。
左手が野馬土手。




 旧道は左へ曲り、さらに右に曲がります。
旧道は左へ曲り、さらに右に曲がります。

















 約2㎞。
約2㎞。 船形まで続く。
船形まで続く。 炎天下だと参りそう。
炎天下だと参りそう。
 「檜溜(ひのきだめ)」バス停。
「檜溜(ひのきだめ)」バス停。 曽田香料(株) 野田支社。
曽田香料(株) 野田支社。
 (「同社」HPより)
(「同社」HPより) 赤い線が日光東往還。
赤い線が日光東往還。



 1880年代のようす。
1880年代のようす。  2010年代のようす。
2010年代のようす。
 歌川広重画『富士三十六景 下総小金原』(1858年・安政5年)
歌川広重画『富士三十六景 下総小金原』(1858年・安政5年) 野田市まめバス「野馬込(のまごめ)」バス停。
野田市まめバス「野馬込(のまごめ)」バス停。


 右手に「もりのゆうえんち」。
右手に「もりのゆうえんち」。




 2010年代のようす。周囲の市街地化にあって保存されているようす。
2010年代のようす。周囲の市街地化にあって保存されているようす。

 奥深い散策路。
奥深い散策路。  「中央の杜」。
「中央の杜」。





