高層ビルが立ち並ぶ新宿にあって、広大な公園はオアシスそのものといった感じだった。園内の桜もちょうど満開の時期とあって短い時間ながら寛ぐことができた。ただし、由緒ある公園としてセキュリティチェックが厳重な公園でもあった。
当初、新宿御苑を訪れる予定はなかったのだが、ネット上の「お花見人気スポットランキング」で上昇していることを知り、急遽行ってみようと予定に加えたところだった。
4月6日(日)朝一番に駆け付けたところ開園前(開園時間9時)だったが、すでに開場を待つ人たちが並んでいた。
入園料は200円と北大植物園よりは低額なのだが、酒類の持ち込みを禁止しているため、入園の際に職員による荷物チェックが厳しく行われた。

新宿御苑の広さは58.3ヘクタールとのことだが、広さの感覚はなかなか伝わらない。しかし、周囲が3.5キロメートルといわれるとその大きさが想像つくだろう。
新宿御苑は、大きく〔日本庭園〕、〔イギリス風景式庭園〕、〔フランス式整形庭園〕の三つの庭園から成っている。
その中でもやはり最も面積を割いている〔日本庭園〕が見事だった。桜の木も主として日本庭園に多かった。
帰宅してからカメラに収めた写真をチェックしてみると、昨日投稿した三大お花見人気スポットの写真が意外に数も少なく、見栄えの良い写真が意外に少なかった。その点、新宿御苑は桜の木ばかりではなく、さまざまな樹種と共に桜の木があったのだが、私から見るとそれなりに良く撮れていたのではと思う。それでは新宿御苑の見事な桜をたっぷりとご覧あれ!!







[フランス式整形庭園]は、御苑の奥まったところに造成されていた。
目立ったのは、プラタナスの並木である。葉がまだ出ていないプラタナスの木はちょっと異様にも見えたが、葉が生え揃う時期は見事だと思われる。また、整形庭園と称されるように生垣が徹底して人の手を加えた様がそれはそれで見事だった。


そして御苑の中央部分に位置するのが〔イギリス風景式庭園〕である。解説によるとゆったりと、広がる芝生と自然のままにのびのび育った巨樹が特徴であるというのがイギリス風景式庭園の特徴とか…。広々とた芝生が親子や若い人たちが自由に憩っていたのが印象的だった。


この日は天候も良く、花見には絶好の天気だった。多くの人たちが、グランドシートを敷いて食事を楽しみ、あるいはペンチで夫婦仲良く寛ぐ人ありと、都心の中にポッカリと浮かんだオアシスで楽しむ光景を眺めながら、私も心楽しくなったひと時だった…。
桜の開花時期に東京へ行く所要があった。そこで東京のお花見人気スポットランキングのベスト3のところを巡ってみた。三つのスポットは都民の楽しみ方にそれぞれに個性があって、見比べてみるのが楽しかった。
私は東京へ行く前(4月3日)に調べたところ、関東の〔お花見人気スポットランキング〕は、第1位 千鳥ヶ淵公園、第2位 目黒川、第3位 上野恩賜公園となっていた。
そこでせっかくの機会なので3ヵ所を巡ってみようと計画した。
4月5日(土)、順位どおりに3ヵ所を巡ることができた。
まず、千鳥ヶ淵公園である。
千鳥ヶ淵は、一方が皇居のお濠、もう一方をイギリス大使館の広い敷地に挟まれたところに位置し、大使館の背後には麹町のビル群が広がるハイソな雰囲気が漂う一帯である。
公園内の桜は、さすが第1位の人気スポットとあって公園内は桜の木が頭上を覆い、満開の時を迎えていた。特にお濠端に咲く桜が見事だった。
そして、桜を愛でる人たちは比較的年配の人が多く、静かに桜を楽しんでいる雰囲気だった。



続いて、地下鉄で中目黒駅に移動し、目黒川沿いの桜を楽しんだ。
目黒川の桜は、それほど川幅が広くない両側にびっしりと並んでいて、桜の花が川面を覆っているような光景だった。
川沿いとあって、広く陣取ってお花見をするといった光景はなく、人々は川沿いをそぞろ歩きをしながら桜を楽しんでいた。
ここの特長は、周辺の業者が出店をたくさん出店していたことだ。それもなぜかワインを売る店が目立った。中でもピンク色のスパークリングワインを売り物にしている店が多く、若者などはワイングラスを片手に桜を楽しんでいる人が多かった。目黒っておしゃれな街なのかな?



そして最後は上野公園に移動した。
駅に着いたときから大変な人の数だった。
さして上野公園に着くと、そこは人、人、人の波だった。さらには、空き地と思えるところは全て埋め尽くされているかのような花見客(宴会客?)でごったがえしていた。
花は満開の峠を越えていたようだったが、花見客にとっては文字どおり“花よりだんご”といった感じで、その賑わいの凄いこと凄いこと…。
わたしはこの日は上野公園の桜を愛でた後、国立博物館を見学する予定にしていたので早々にそちらへ移動した。そして、博物館の壁に〔博物館でお花見を〕という垂れ幕が下がっており、ふだんは解放されていないという博物館の庭園の桜を楽しんだ。



※ 国立博物館の庭園に建つ重文級の茶室の背景を彩る桜です。
ところで旅行中のブログでも触れたが、ちょうどこの時期に皇居内の乾通りの桜が一般公開されているとニュースが流れていて、私もせっかくの機会と思い、この日いの一番に駆け付けた。しかし、現地に到着した時にはすでに長蛇の列ができており、入場できるまでどれくらいの時間がかかるのかまったく読むことができなかった。後のスケジュールを考えると、これは諦めるのが賢明と判断し、その列から離れたのだった。
おそらく、長い時間を要して入場できたにしても、あの人の多さではゆっくりと桜を愛でることなどできなかったものと思われる。

※ 地下鉄駅からこうした人の群れが延々と続いていた…。
と、この日はお花見人気スポットランキングの上位を占める桜の名所を巡ったのだが、北海道の人間からすると、その規模の大きさと、鮮やかさに驚いた思いだ。
あれだけの規模と鮮やかさを見るとき、私たち日本人がことのほか桜を愛でるということを再認識した思いだった…。
車も通れないような細い坂道に料亭などが立ち並ぶ…。私にとっては異空間を見る思いだった。私が訪れたのは午前中とあって、まだまだ前日の眠りから明けていない感じだったが、飲み屋街の不潔感はなく上品な雰囲気に包まれた街だった。
今夜、札幌に帰ってきた。
帰札を前に、最後の東京街巡りで「神楽坂」を訪れた。
ガイドブックが神楽坂の小路を意識的に設定したこともあり、車一台がようやく通れるくらいの細い道、中には人が行き交うのに肩が擦れ合うのではないかと思われるほどの細い道もあった。
そんなところに、料亭や小料理屋などがずらーっと並んでいた。
夜になると、どんな雰囲気になるのだろう?私には無縁の想像のつかない世界だった。
神楽坂のコースを終え、まだ少し時間があったので、私がホテルを取った門前仲町まで戻り、「深川不動堂」と「富岡八幡宮」を訪れてきた。
慌ただしくも、東京の街をあちこちと巡った3日間だった。
明日から写真を添えながら、少し振り返ることとしたい。
東京巡り三日目の今日、私は典型的なお上りさんを演じたのだった。「国会議事堂(衆議院)」見学、「日本銀行」見学、そしてランチに銀座の老舗洋食店「煉瓦亭」でのポークカツレツとくれば、これはもう立派なお上りさんである。
昨日、一昨日の私の東京での行動も、他人から見れば十分にお上りさん的行動に見えただろう。しかし、今日の行動と比べるとまだ一つの目的を持った行動だった。
しかし、今日の選択は地方に住むグループや団体が東京に来たときに最も選択しそうなポイントなのでは、と思われる。事実、国会でも、日銀でも、団体さんと一緒の見学となった。
さて、簡単にその印象を記すと…。
最初に訪れた衆議院だったが、正直に言ってガッカリだった。
担当者は定められたコースをただ引率するだけで、何の説明もないのだ。委員会室が並ぶ廊下を通り、本会議場を見て、外へ出て正面から議事堂を見て、ハイ終わりといった感じだった。
当初、見学時間は1時間と伝えられていたのだが、わずか30分で見学は終わってしまった。
あるいは、国会開会中ということで簡略化されたコースだったのかもしれない。
午後に訪れた日本銀行の方は、国会と違い、非常に懇切丁寧だった。
初めに20分ほどの日銀について紹介するフィルムを観た後、20名弱のグループごとに案内担当者が日銀内の各所を説明しながら回ってくれた。(約40分間)
その後、担当者が入れ替わってレクチャールームで約30分にわたって、フィルムとは違う日銀の役割などについて分かりやすく説明してくれた。
国会とは何と違う対応だろう。
銀座の煉瓦亭は明治28(1895)年創業の老舗洋食レストランということでガイドブックなどに紹介されているレストランである。
銀座中央通りの裏通りの飲食店や専門店が並ぶ通りに、歴史を感じさせるような外観で建っていた。
内装はどこにでもある洋食レストランという感じで、特にオシャレという感じでもなかった。
名物メニューのポークカツレツ(1,600円 withライス)は、競争の激しい銀座で110数年生き抜いてきただけに、十分に納得できる味だった。
その後、私はせっかくの機会だったので銀座1丁目から6丁目まで銀ブラ(この表現もかなり古いねぇ)を楽しんだのだが、聞こえてくるのは声高にしゃべり合う中国語ばかり…。なんだか、様変わりした銀座を見る思いだった…。
この日私はこの他に、国会見学を終えた後、日銀見学までの間に「駒込~王子」コースを巡った。(そのレポートは後で)
昨年の夏に続き、「東京下町巡り」を主に楽しんだ。主に、ということは今日の最初に「新宿御苑」のサクラを楽しんだ後に、下町に回ったからだ。ガイドブックの標記によると「御茶ノ水・神田・秋葉原」コースと、「森下・清澄」コースを巡った。
「新宿御苑」は私の当初予定にはなかった。しかし、以前から気になっていた公園であるし、「お花見人気スポットランキング」のベスト3にランクインしているのを知り、急遽訪れてみることにした。
この選択は正解だった。都心に残された貴重な公園は訪れるに十分の価値ある公園だと思った。(詳しくは写真と共に後日に)
続いて地下鉄〔御茶ノ水〕駅に移り、「御茶ノ水・神田・秋葉原」コースを巡った。「神田明神」とか「湯島聖堂」などの由緒ある建物があるかと思うと、派手な装飾を施した秋葉原の街がある、といったように激しく街の表情を変えるコースだった。
次は隅田川を本所深川界隈を巡る「森下・清澄」コースを歩いた。
このコースは俳人松尾芭蕉にゆかりの深い街だった。「芭蕉記念館」・「芭蕉庵史跡展望公園」・「芭蕉稲荷神社」・「芭蕉俳句の散歩道」というように芭蕉づくしだった。
その他にも興味ある公園や施設がたくさんあったコースだった。
それにしても意外なほど体力が落ちていることを痛感した。
二つのコースを歩き終えた時には疲労困憊の状態だった。
やはり加齢による衰えと,冬場の運動不足がその原因なのではと思う。
これは良い警告ととらえたい。加齢による衰えは仕方がないとしても、日常的に運動することを心がけねばならないことを教えてくれたのだと考えたい。
帰札したら心を入れ替えて、少し意識的に運動しようかな?
思わぬ形で東京のサクラを愛でることができることになった。今日、私はネット上で東京のサクラスポット人気№1位から3位までの3ヶ所を巡ってきた。3ヶ所それぞれに個性があって、十分に楽しめたサクラスポット巡りだった。
所用があって昨日から東京に来ている。
用件の方は昨日中に終えることができた。
折角東京に出た機会なので、昨年に続いて少し東京で遊ぶことにした。
そこで今が旬の東京のサクラを愛でることにしたのだ。
「さて、どこへ行こうか」とネットで調べてみると東京にはサクラの名所がけっこう多いようだ。
すると同じページに「お花見スポット人気ランキング(関東)」という記事があった。
それによると、第1位 千鳥ケ淵公園(東京都)、第2位 目黒川(東京都)、第3位 上野恩賜公園(東京都)となっていた。(先ほど、改めて確認すると第3位が新宿御苑に変わっていたが…)
そこで地下鉄を縦横に使って、3ヶ所を全て巡ってみることにした。
巡る順も、順位どおりに巡るように計画を立てた。
結果、それぞれのスポットでゆっくりとサクラを楽しんだとは言えないが、計画通りに3ヶ所を巡ることができた。
東京のサクラはやや峠を越えたかな?という感じはあったが、まだまだ満開と言ってよい状態だった。
面白いと思ったのは、サクラの状態ではなく、そこで楽しむ人たちにそれぞれ個性が感じられたことだった。
例によって旅先からは写真の添付が困難なので、帰宅してから写真と共にその辺のことに触れたいと思っている。
ところで、今東京のサクラのことで話題なのは、4日から皇居内の乾通りのサクラ並木が公開されているということである。
実は、私も話題のところをチェックしようと、東京メトロの【千代田線】で〔二重橋〕駅に降り立って、皇居のサクラを愛でようと思ったのだが、その人の多さにビックリしてしまった。こんな言葉を私は使ったことがないのだが、「ハンバない」人の数だった。
一応、列には並んでみたのだが、「これでは乾通りに辿り着くまでに午前中かかってしまうのでは」と思うと、計画しているところを回ることができなくなると判断し、列から抜け出し、私は千鳥ケ淵公園へ向かったのだった。
この判断がはたしてどうだったのか、まあ人それぞれ、私は私の判断をヨシとしょう。
某日、久しぶりに以前からお付き合いしているK氏と一献傾ける機会をもった。互いの近況を語り合う中で、自然と拙ブログの話題となっていった。K氏は以前から拙ブログを愛読してくれている。
歓談する中で、K氏が突然のように「あなたのブログはカラフルである」と発言した。「カラフル?いったい何のこっちゃ?」と思ったのだが、聞いているうちに「ブログの内容が多彩である」ということのようだった。
「それならマルチと言ってほしいなぁ」と私が言ったのだが、K氏は「いや、カラフルだ」と言って譲らないのである。
「カラフル」or「マルチ」…、どちらでもいいんだけれど、「カラフル」というイメージはどちらかというと“軽い”イメージである。
それに対して「マルチ」という言葉には、マルチな才能とか、マルチプレイヤーなどという使われ方をして、「多彩」というよりは「多才」というイメージがあるではないか。
私は自分自身を多才などと思ってはいないが、そうでないだけに「マルチ」というイメージに憧れるのだが、K氏に言わせると、まだまだそんなイメージではないということなのだろう…。
いつかK氏から「マルチなブログ」と呼ばれるように精進しましょうか。
※ 今日はちょっと事情があり、いつもとは違い朝の投稿になりました。

※ 「青少年体験活動奨励制度」について説明する松田東京学芸大教授です。
3月30日(日)午後、札幌大学において教育支援人材認証協会というところが主催する「大学が地域の教育支援人材育成に果たす役割」という名称のシンポジウムが開催され、参加してきた。
シンポジウムは教育支援人材認証協会の理事の方が「青少年体験活動奨励制度について」の説明が冒頭にあった。その趣旨は、青少年が様々な体験活動を自主的に継続した実績に応じて、その達成を表彰する仕組みを全国、さらには世界的にも通ずる顕彰システムとして確立することを目ざした取り組みの一環ということだ。

※ シンポジウムにおいて、ボランティアの体験を発表する札大の学生です。
続いて、札幌大学の三つのゼミにおいて、地域の教育機関や団体の活動にボランティアで関わっている実践の報告がなされた。
障害のある子どもたちに対する支援活動、地域の幼児の親子を対象とした野外活動、通信制高校や私立小学校の行事への応援活動、などなど…。
それぞれ教師がそのねらいを説明し、参加した学生が感想や成果を発表する形でシンポジウムは進められた。
そして私が何より驚いたのは、学生の発表の様子だった。
ボランティアを体験する中で悩み、苦しんだこと、そこを乗り越え成長できたこと、などを自らの言葉で堂々と発表していたことだった。
発表した伊藤俊輔君をはじめ三人はゼミの代表として発表だったから、優秀な学生には違いないと思う。それにしても自分は学生の時に彼らのように人前でしっかりと発表することなどできたろうか?と振り返ってみたとき、彼らの素晴らしさを思うのである。
コーディネーターの方が、「大学が地域の教育支援人材育成に果たす役割」というよりは、地域や教育機関に学生が育てられている事例の発表となったが…、と断りを入れていたが、
シンポジウムに参加した私は、今どきの大学の学生の育成法に一端に触れることができた有意義なひと時だった。
頑張っているぞ!札幌大学
この歳になって改めて気付いた思いである。北海道の春って、春の足音が聞こえたかなと思ったとたん、ぐんぐんと近づいてくる感じである。
あれだけ雪深かった街中の雪もアッという間に消えていった。
雪が消えると私にとってはボランティアシーズンが到来したという思いである。
近代美術館に近い現在のところに居を定めてから、同じマンションの人たちと語らって始めた近代美術館前の美化活動も今年で5年目を迎える。
春先には花壇の整美作業があるが、その後は2週間に1度くらいの割合での路上の清掃活動がその中心である。
わずか1時間程度の活動なのだが、昨年あたりから年齢からくる衰えだろうか、活動を終えた後に足腰が重く感ずることが多くなってきた。
それでも、まだまだ今程度の活動は続けられるだろうと思う。
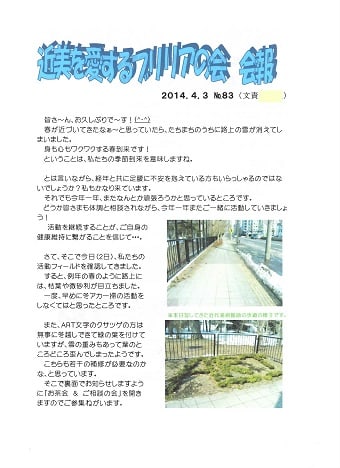
そこで早速、今日久しぶりに「近美を愛するブリリアの会 会報」�83を発行し、会員の皆さんに届けたところだ。
内容は「今年も頑張りましょう!」ということと、活動の相談のためのお茶会のお知らせである。
今年も自分たちの住まいの周りの美化にちょこっとだけお役にたとうと思っている。
北大の山口二郎教授が主宰する「フォーラム in 札幌時計台」の最終フォーラム(第31回)が3月6日(木)夜に開催された。これまでも何度か参加し、日本の知性といわれる方々の発言に耳を傾けてきたのだが、最終回というのは少し寂しい思いである。
最終回となるのは、主宰する山口教授が4月より法政大学に転じることにより札幌を離れてしまうためである。
その最終回ゲストが哲学者の柄谷行人氏と作家の佐藤優氏だった。
テーマは「グローバル化に抗する人間とコミュニティ」だったが、知性派といわれる二人の発言は凡人の私には難しかった。彼らの発言は私の中に留まることなく彼方へ通り過ぎていくばかりだった。だからここでは、かろうじて私の中に残った二人の語った単語について反芻し、二人の想いに迫ってみたい。

※ 柄谷行人氏のポートレートです。
最初に柄谷氏が、「日本の国民の現状は、私化と原子化がほとんどを占める」と発言した。
私にとっては「私化」とか「原子化」などという言葉は恥かしながら初耳だった。こうしたフォーラムに参加する者としては当然知っていなければならない言葉のようだった。
「私化」とか「原子化」とは、政治学者である丸山眞男が唱え始めた言葉のようである。
この二つの言葉をごくごく簡単に言うと、現代においては国民の中に「個人主義」が主流を占めつつあり、政治に無関心な層が増えてきているという。そうした層の関心事は自分のことやせいぜい家庭のことなど私的事柄に関心を向けるタイプを丸山は「私化」と称した。私もその一人なのかもしれないが…。
もう一つの「原子化」は政治に無関心ということでは「私化」と同じタイプなのだが、権威主義的リーダーシップをとる権威者に扇動されれば、簡単になびいてしまって、そのリーダーの言動にファナテック(狂信的)に帰依してしまうような、権威に左右される浮動層を指すとのことだ。
柄谷氏はこの「原子化」の層の増大に危機感を抱いているような論調に聞こえた。

※ こちらは佐藤優氏のポートレートです。
一方、佐藤氏も日本の現状には相当な危機感を抱いているようだ。
佐藤氏の発言の中で、現政権の安部首相は選挙で選ばれた王様のようにふるまっている。その点ではプーチンも、オバマも同様であるとした。そして、彼らは立憲主義を知らないのではないかとし、民主主義的統制ができないリーダーであると指摘した。
佐藤氏は現在の日本が1930年代に近い空気を感じるとし、戦争が勃発する可能性までも指摘したことに聴いていた私は戦慄をおぼえたのだった。
断っておきたい。紹介した言葉はあくまでもスピーチの中のごくごく一部の言葉である。彼らは多方面にわたって論を展開したのであるが、私が咀嚼できなかったということである。
二人の発言を一方の見方とする考えもあるだろうが、つねに日本全体を俯瞰しながら思索する立場の人の発言だけに無視できない見方ではないのか、と私は思った。
私個人としては、せめて「原子化」した人間にならぬように留意しなくては、と思うのが精一杯だった…。









