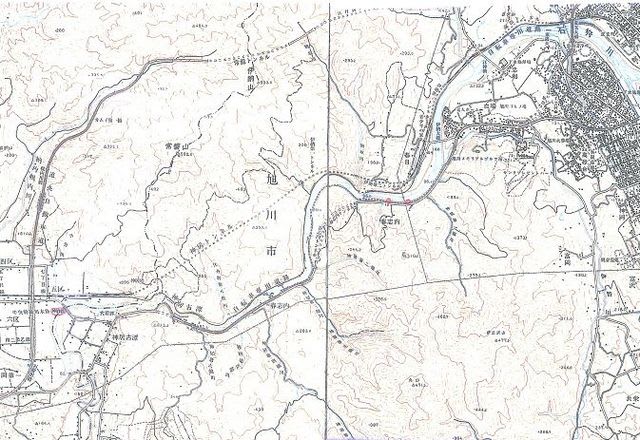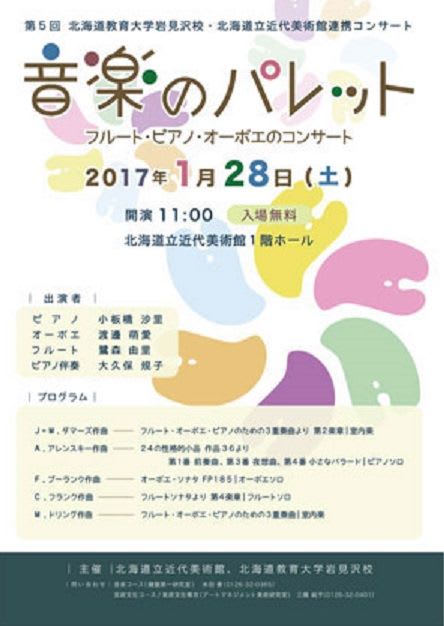※ フォーラムそのものは写真撮影がNGだったが、フォーラム後冬季アジア大会マスコットの「エゾモン」
とパネリストが写記念撮影をしていたので、その様子をパチリと。
2月4日(土)午後、道新ホールにおいて「スポーツ!北海道フォーラム ~北の大地をスポーツの大地に~」と題するフォーラムがあった。
最初の広瀬社長の挨拶は聴き応えがあった。広瀬氏は、昨年の日本ハムファイターズを応援する道民の姿を見て「スポーツは地域を一つにする大きな力がある」とした。さらには、スポーツは北海道が躍進するうえで背骨のような役割があるとして、スポーツの持つ可能性の大きさに言及したことには説得力がある、と感じた。
プログラムは、基本トークとして「スポーツが持つ可能性」と題して、長野冬季五輪スビートスケート500m金メダリストの清水宏保さんと、シドニー五輪水泳メドレーリレー銅メダリストの田中雅美さんが、道新のスポーツ担当部長の質問に答えるかたちで進められた。

※ 清水宏保さん
しかし、いつも感ずることだが清水宏保さんは何を言いたいのかよく分からないことが多い。この日も彼の発言には、「北海道は運気が上がっている」とか、「札幌は雪を活かしきれていない」とか、「アスリートの知識を国民の財産にせよ」というような発言をしたのだが、今一つ言おうとしていることが伝わってこない。もっと簡潔・明瞭な発言ができないのだろうか。
後のパネルディスカッションで、岡崎朋美さんから「自らの仕事のPRをしているように聞こえた」と揶揄していたが、私にもそう聴こえてきた。

※ 田中雅美さん
対して田中氏雅美さんは、「スポーツは“する”側にも“見る”側にも目標・目的がある。それが生きがいになるのがスポーツの良さだ」とし、「スポーツ選手の財産は、最後まであきらめずに挑戦したり、苦しんだりしたからこそ、それを皆に伝えられることがある」とした。
田中さんの方がはるかにテーマに沿った発言をしている。
続いて前記した二人に、長野冬季五輪スケート500m銅メダリストの岡崎朋美さん、リレハンメル冬季五輪複合リレー金メダリストの阿部雅司さん、バンクーバー冬季五輪アイススレッジホッケーの銀メダリストの永瀬充さんの5人が登壇して「スポーツで北海道を元気に」と題してのパネルディスカッションが行われた。

※ 岡崎朋美さん

※ 阿部雅司さん

※ 永瀬充さん
期待したパネルディスカッションだったが、コーディネーター役の北海道新聞社の佐々木氏の聞き出し方がいかにも不味いと思われた。質問が散漫的過ぎて、それぞれの発言がテーマに向かっていないのだ。私が懸命にとったメモにも印象的な言葉が一つもないという寂しい結果になってしまった。
そんな中、私の記憶に残ったのは岡崎朋美さんの天然ぶりと、阿部氏が昨日と同じエピソードを話されたときに涙腺が緩んでしまったことくらいだった。
皮肉にも、コーディネーターというのがいかに重要か、ということを認識させてくれたパネルディスカッションだった。