「美家古(みやこ)」他にも古くからの料亭が点在しています。
「壱松(いちまつ)」、「市山(いちやま)」、「入舟(いりふね)」、「きよし」、「櫻茶ヤ(さくらちゃや)」、「すみ多(すみだ)」、「千穂(せんすい)」、「千代田(ちよだ)」、「月笛(つきぶえ)」、「道成寺(どうじょうじ)」、「波むら(なみむら)」、「ふ多葉(ふたば)」、「美家古(みやこ)」。
(以上、「向嶋墨堤組合」HPで紹介されている料亭)
おもてなしの心
料亭と言う響から連想される「贅を尽くした雅やかで高貴な処」と評されることが多々あります。実際はそれほど敷居は高くありません。お客様のご予算、内容に応じてご利用いただけるのも料亭の仕組みです。風情を重んじ、旬の素材で季節を食彩共に愛でる料理と落ち着きのある部屋、さりげなく置かれている調度、床の間、おもてなしの心。全ての纏まりが醸し出す無形の演出、日本の食文化,、伝統を受け継ぎ次世代に継承する事が私共の使命と考えております。
門口を通ると広がる和の空間、粋と寂の趣を控えめにしつらえた佇まい、お客様の心へさりげない癒しへのいざない。これから繰り広げられようとする宴へのときめきをお部屋にお通しするまでも家人の立ち居振る舞いの淑やかさ、言葉遣い、手の動き、目くばり、気くばり、その一つ一つに「もてなしの心」を感じていただけることでしょう。そして、お料理。季節、厳選された素材、彩り、調理の技、器との競演、ここで大事なもてなしをする家人の気くばり、美味しいお料理をより美味しくお召し上がり頂くための「間」※タイミング。ご酒をお召し歓談をされているお客さまへ、どの「間」で次のお料理をお出しするかも「もてなしの心」なのです。宴が終わりお客様をお見送りするまでの心の緊張。
「また、寄らせてもらうよ」のお言葉。感謝と緊張の糸がとける瞬間です。時代は変われど歴史ある日本文化、伝統、作法を重んじた料亭の文化を末永く継承すると共に、より一層、「もてなしの心」を求道、邁進いたします。
お座敷と芸者さん
江戸時代前期、松尾芭蕉の登場により江戸中期以降、俳諧、連歌などの会席が料理茶屋で開かれるようになり、舞踊、邦楽で宴席に興を添え、客をもてなす女性の職業として芸妓の形が出来ました。時代が替わり会席の形も色々と変化をしてきましたが、料亭のお座敷と芸妓、伝統芸能の取り合わせは今の時代でも遺っています。
日本の伝統芸能は長い歴史と共に様々な唄、器楽、舞、演者、流儀、流派、と広域でとても語り尽くすことが出来ません。花街向島では現在も技術の伝承者と共に継承されている奥深い文化である伝統芸能を遺すためにも、芸妓衆の習い事として日々お稽古を各分野のお師匠さんに付けていただいております。
邦楽を介して学ぶ作法も重要ですが「呼吸」「間」「情緒」そして「粋」を音曲の調べと共に情感で表現する奥深い日本の伝統芸能を身につけなければ一流の芸妓にはなれない重要な教養の一つでもあります。
現在、邦楽の範囲としては浄瑠璃(義太夫、常磐津、清元)、器楽(三味線、笛、小鼓、大鼓、大皷※おおかわ、締太鼓)が主な演練演目としてあり、一つを昇華するにも大きな時間を費やします。自己の教養を高めることが客をもてなす才色兼備の芸妓に育っていくのです。
芸妓の身のこなしや立ち居振る舞いは邦舞、邦楽の基礎をしっかりとしたお稽古を続け身につけることが感性の現れとなります。現在、向島花街では日本舞踊として200流派を超える流派の中から「西川流」と「猿若流」のお師匠さんよりお稽古を付けていただいております。
西川流
日本区内には200を超える日本舞踊の流派がありその中でも5大流派と言われる中の一つに数えられているのが初代創始は江戸三座の櫓付振 付師としても活躍し、三百有余年の歴史を有し現在も多くの門弟を世に送り出しています。
猿若流
江戸三座に入り、江戸歌舞伎の始祖と伝えられている。寛永元年(1624年)初代猿若(初代中村勘三郎)により猿若座(後、中村座)の櫓をあげ、現在まで約400年の歴史と伝統を継承し日本舞踊の発展に努めています。
お座敷の遊び
金比羅船々
芸妓と向い合い善の上に椀のような道具を真ん中に「金比羅ふねふね・・・」を歌いながらジャンケンの形で椀のような物を片方が取ったらグー、そのままならパーを出す。間違えたら負けの反射神経が問われるゲーム。
投扇興
流派もある伝統的対戦ゲームで、桐箱の台座にたてられた「蝶」と呼ばれる的へ扇を投擲して落ちたときの形により得点を算出し点数を競う。
とらとら
体を使ったジャンケンで和唐内(やりでつく格好)、虎(よつんばい)、お婆さん(杖をつく格好)の組み合わせで、勝敗は和唐内は虎には強いがお婆さんには弱い。虎は、お婆さんには強いが和唐内に弱い。お婆さんは、和唐内に強いが虎には弱い。
おまわりさん
芸妓と2人でジャンケンをして勝った方は太鼓をたたき、負けた方は1回転してまたジャンケンをするゲーム。
お食事だけでもご予約いただき気軽にご利用頂けるのも花街向島の魅力です。
・・・
見番とは
俗称:見番 正式名:向嶋墨堤組合
花街の成り立ちからご説明、向島に料亭街の集合地域として繁栄し歴史も古くからの痕跡を残している。ここでは終戦後から現在の見番 (向嶋墨堤組合)になるまでをご説明させていただきます。
向島は隅田川の東岸に位置しており、春は桜、夏は花火、秋は向島百花園、冬は隅田川七福神巡りと四季折々の情景と風情の趣を醸す地域故に人々の往来も多くなり、花街の成り立ちを要する置屋、料理屋、待合の三業種の営業が許可された三業地と呼ばれるようになりました。
昭和61年11月15日、芸妓組合、料亭組合、料理店組合が合併し、見番(向嶋墨堤組合)として現在に至っています。主な業務は料亭への芸妓の手配、料亭の予約手配、置屋、他花街の統括管理が主な業務、また、芸妓の育成、お稽古、等々、伝統文化継承の貢献も行ってる花街では重要な組織が見番です。
置屋とは
自店に登録されている芸妓を料亭へ斡旋したり新人芸妓を育てたりと花街には無くてはならない業態。花街向島では50件近くの置屋があります。
と、以上「向嶋墨堤組合」HP)より引用。


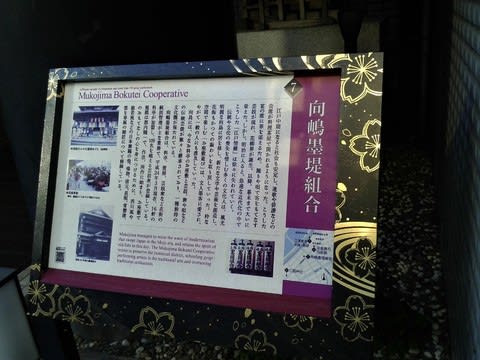 「向嶋墨堤組合(見番)」解説板。
「向嶋墨堤組合(見番)」解説板。
江戸中期になると社会も安定し、連歌や俳諧などの会席が料理茶屋で開かれるようになった。こうした宴の席に華を添えるため、踊りや唄で客をもてなす芸妓が現れ、花柳界が誕生。以降、幕末まで大いに栄えた。しかし、明治に入ると、急速な近代化の中でこうした「江戸情緒」は徐々に失われていく。
伝統や文化を惜しむ多くの文化人は、風光明媚な向島に居を移し、新たな文学や芸術を創造し、花街もかつての賑わいを取り戻していった。粋な空間で楽しむ「お座敷遊び」は、文人墨客に愛され、やがて一般の人にも波及していった。
向島には、今なお料亭のお座敷と芸妓、舞や唄などの伝統芸能が脈々と継承されており、一種独特の文化圏が保たれている。
向嶋墨堤組合は、料亭、置屋、芸妓衆など花街の統括管理が主な業務で、平成24年3月現在、16軒の料亭が加盟し、100名を越える芸妓衆が登録している。規模は都内随一で、作法、所作に始まり、お座敷でのおもてなしの心を身につけるために、西川流や猿若流などの日本舞踊の他、鳴り物、清元、長唄、常磐津、笛を専属の師匠について修練している。
やはり小生には敷居の高い、無縁の世界ですね。「縁無き衆生は度しがたし」。
せめて料亭の写真だけでも。
 「櫻茶ヤ」。
「櫻茶ヤ」。
 「桜まつり」の提灯が掲げられています。
「桜まつり」の提灯が掲げられています。
シダレザクラはほんの一輪ほど。
注:コロナ騒動で、「桜まつり」も中止になり、隅田川土手の提灯も一部、26日には取り外されました。
 「ふ多葉」
「ふ多葉」
「多」は「 」。
」。
「葉」は「 」。
」。
 「入舟」。
「入舟」。
 「波むら(なみむら)」。
「波むら(なみむら)」。
 「「すみ多(すみだ)」。
「「すみ多(すみだ)」。
「だ」は「 」に濁点。
」に濁点。
この界隈は料亭ばかりではありません。歴史と文化を感じる建物やお店が存在します。次は、その紹介を。
「壱松(いちまつ)」、「市山(いちやま)」、「入舟(いりふね)」、「きよし」、「櫻茶ヤ(さくらちゃや)」、「すみ多(すみだ)」、「千穂(せんすい)」、「千代田(ちよだ)」、「月笛(つきぶえ)」、「道成寺(どうじょうじ)」、「波むら(なみむら)」、「ふ多葉(ふたば)」、「美家古(みやこ)」。
(以上、「向嶋墨堤組合」HPで紹介されている料亭)
おもてなしの心
料亭と言う響から連想される「贅を尽くした雅やかで高貴な処」と評されることが多々あります。実際はそれほど敷居は高くありません。お客様のご予算、内容に応じてご利用いただけるのも料亭の仕組みです。風情を重んじ、旬の素材で季節を食彩共に愛でる料理と落ち着きのある部屋、さりげなく置かれている調度、床の間、おもてなしの心。全ての纏まりが醸し出す無形の演出、日本の食文化,、伝統を受け継ぎ次世代に継承する事が私共の使命と考えております。
門口を通ると広がる和の空間、粋と寂の趣を控えめにしつらえた佇まい、お客様の心へさりげない癒しへのいざない。これから繰り広げられようとする宴へのときめきをお部屋にお通しするまでも家人の立ち居振る舞いの淑やかさ、言葉遣い、手の動き、目くばり、気くばり、その一つ一つに「もてなしの心」を感じていただけることでしょう。そして、お料理。季節、厳選された素材、彩り、調理の技、器との競演、ここで大事なもてなしをする家人の気くばり、美味しいお料理をより美味しくお召し上がり頂くための「間」※タイミング。ご酒をお召し歓談をされているお客さまへ、どの「間」で次のお料理をお出しするかも「もてなしの心」なのです。宴が終わりお客様をお見送りするまでの心の緊張。
「また、寄らせてもらうよ」のお言葉。感謝と緊張の糸がとける瞬間です。時代は変われど歴史ある日本文化、伝統、作法を重んじた料亭の文化を末永く継承すると共に、より一層、「もてなしの心」を求道、邁進いたします。
お座敷と芸者さん
江戸時代前期、松尾芭蕉の登場により江戸中期以降、俳諧、連歌などの会席が料理茶屋で開かれるようになり、舞踊、邦楽で宴席に興を添え、客をもてなす女性の職業として芸妓の形が出来ました。時代が替わり会席の形も色々と変化をしてきましたが、料亭のお座敷と芸妓、伝統芸能の取り合わせは今の時代でも遺っています。
日本の伝統芸能は長い歴史と共に様々な唄、器楽、舞、演者、流儀、流派、と広域でとても語り尽くすことが出来ません。花街向島では現在も技術の伝承者と共に継承されている奥深い文化である伝統芸能を遺すためにも、芸妓衆の習い事として日々お稽古を各分野のお師匠さんに付けていただいております。
邦楽を介して学ぶ作法も重要ですが「呼吸」「間」「情緒」そして「粋」を音曲の調べと共に情感で表現する奥深い日本の伝統芸能を身につけなければ一流の芸妓にはなれない重要な教養の一つでもあります。
現在、邦楽の範囲としては浄瑠璃(義太夫、常磐津、清元)、器楽(三味線、笛、小鼓、大鼓、大皷※おおかわ、締太鼓)が主な演練演目としてあり、一つを昇華するにも大きな時間を費やします。自己の教養を高めることが客をもてなす才色兼備の芸妓に育っていくのです。
芸妓の身のこなしや立ち居振る舞いは邦舞、邦楽の基礎をしっかりとしたお稽古を続け身につけることが感性の現れとなります。現在、向島花街では日本舞踊として200流派を超える流派の中から「西川流」と「猿若流」のお師匠さんよりお稽古を付けていただいております。
西川流
日本区内には200を超える日本舞踊の流派がありその中でも5大流派と言われる中の一つに数えられているのが初代創始は江戸三座の櫓付振 付師としても活躍し、三百有余年の歴史を有し現在も多くの門弟を世に送り出しています。
猿若流
江戸三座に入り、江戸歌舞伎の始祖と伝えられている。寛永元年(1624年)初代猿若(初代中村勘三郎)により猿若座(後、中村座)の櫓をあげ、現在まで約400年の歴史と伝統を継承し日本舞踊の発展に努めています。
お座敷の遊び
金比羅船々
芸妓と向い合い善の上に椀のような道具を真ん中に「金比羅ふねふね・・・」を歌いながらジャンケンの形で椀のような物を片方が取ったらグー、そのままならパーを出す。間違えたら負けの反射神経が問われるゲーム。
投扇興
流派もある伝統的対戦ゲームで、桐箱の台座にたてられた「蝶」と呼ばれる的へ扇を投擲して落ちたときの形により得点を算出し点数を競う。
とらとら
体を使ったジャンケンで和唐内(やりでつく格好)、虎(よつんばい)、お婆さん(杖をつく格好)の組み合わせで、勝敗は和唐内は虎には強いがお婆さんには弱い。虎は、お婆さんには強いが和唐内に弱い。お婆さんは、和唐内に強いが虎には弱い。
おまわりさん
芸妓と2人でジャンケンをして勝った方は太鼓をたたき、負けた方は1回転してまたジャンケンをするゲーム。
お食事だけでもご予約いただき気軽にご利用頂けるのも花街向島の魅力です。
・・・
見番とは
俗称:見番 正式名:向嶋墨堤組合
花街の成り立ちからご説明、向島に料亭街の集合地域として繁栄し歴史も古くからの痕跡を残している。ここでは終戦後から現在の見番 (向嶋墨堤組合)になるまでをご説明させていただきます。
向島は隅田川の東岸に位置しており、春は桜、夏は花火、秋は向島百花園、冬は隅田川七福神巡りと四季折々の情景と風情の趣を醸す地域故に人々の往来も多くなり、花街の成り立ちを要する置屋、料理屋、待合の三業種の営業が許可された三業地と呼ばれるようになりました。
昭和61年11月15日、芸妓組合、料亭組合、料理店組合が合併し、見番(向嶋墨堤組合)として現在に至っています。主な業務は料亭への芸妓の手配、料亭の予約手配、置屋、他花街の統括管理が主な業務、また、芸妓の育成、お稽古、等々、伝統文化継承の貢献も行ってる花街では重要な組織が見番です。
置屋とは
自店に登録されている芸妓を料亭へ斡旋したり新人芸妓を育てたりと花街には無くてはならない業態。花街向島では50件近くの置屋があります。
と、以上「向嶋墨堤組合」HP)より引用。


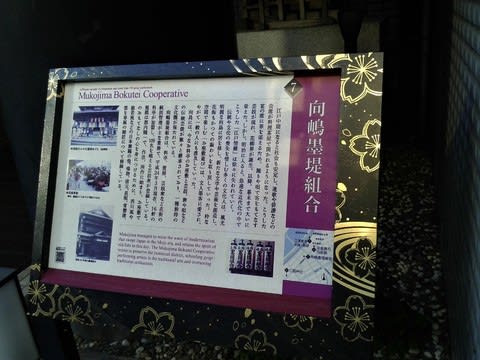 「向嶋墨堤組合(見番)」解説板。
「向嶋墨堤組合(見番)」解説板。江戸中期になると社会も安定し、連歌や俳諧などの会席が料理茶屋で開かれるようになった。こうした宴の席に華を添えるため、踊りや唄で客をもてなす芸妓が現れ、花柳界が誕生。以降、幕末まで大いに栄えた。しかし、明治に入ると、急速な近代化の中でこうした「江戸情緒」は徐々に失われていく。
伝統や文化を惜しむ多くの文化人は、風光明媚な向島に居を移し、新たな文学や芸術を創造し、花街もかつての賑わいを取り戻していった。粋な空間で楽しむ「お座敷遊び」は、文人墨客に愛され、やがて一般の人にも波及していった。
向島には、今なお料亭のお座敷と芸妓、舞や唄などの伝統芸能が脈々と継承されており、一種独特の文化圏が保たれている。
向嶋墨堤組合は、料亭、置屋、芸妓衆など花街の統括管理が主な業務で、平成24年3月現在、16軒の料亭が加盟し、100名を越える芸妓衆が登録している。規模は都内随一で、作法、所作に始まり、お座敷でのおもてなしの心を身につけるために、西川流や猿若流などの日本舞踊の他、鳴り物、清元、長唄、常磐津、笛を専属の師匠について修練している。
やはり小生には敷居の高い、無縁の世界ですね。「縁無き衆生は度しがたし」。
せめて料亭の写真だけでも。
 「櫻茶ヤ」。
「櫻茶ヤ」。 「桜まつり」の提灯が掲げられています。
「桜まつり」の提灯が掲げられています。シダレザクラはほんの一輪ほど。

注:コロナ騒動で、「桜まつり」も中止になり、隅田川土手の提灯も一部、26日には取り外されました。
 「ふ多葉」
「ふ多葉」「多」は「
 」。
」。「葉」は「
 」。
」。 「入舟」。
「入舟」。 「波むら(なみむら)」。
「波むら(なみむら)」。 「「すみ多(すみだ)」。
「「すみ多(すみだ)」。「だ」は「
 」に濁点。
」に濁点。この界隈は料亭ばかりではありません。歴史と文化を感じる建物やお店が存在します。次は、その紹介を。

















