古井由吉さんが亡くなりました。この方の作品はけっこう読みましたが、このブログでは二冊取り上げました。その二つを再掲。
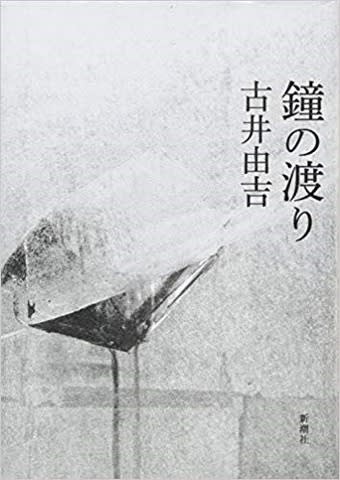
《読書 2014・5・30掲載》
時・空を、あるいは人称を越えた語り口。これが、この方の小説作法なのだろう。夢うつつ、その端境に聞こえる声、声、声・・・。鳥の、赤子の、老人の、両親の、兄弟の、・・・。そして、晩鐘の。否、外界の音だけではない、自らの内から聞こえてくる音。これらの深みに対しては、彩りをなす花々は、どれもこれも「淡い」イメージ、もっといえば、セピア色、さらにいえば、無色透明さえも感じ取らせる。
死者は、息を引き取る際、五感のうちの聴覚が最後まで残っていると聞いたことがある。生者と死者との交流は声をもって終わりとなすか。そして、さまざまな、肉親を含めて人間を看取る主人公。いつか自分も。
老いてますます研ぎ澄まされる聴覚、そして視覚、嗅覚、・・・五感。身体へ心へ染み渡り、醸し出される、不思議(思議せず)な「小説」世界。登場人物たちは、自在に己の世界を紡いでいく、その語り部としての作者に徹底する姿勢は、読者をうならせる魅力にあふれている。
「窓の内」から始まる八つの連作。騒然と、何かにせかされるように生きる(しかない)現代人に静寂をかぎ取る感性というものの豊かさを気づかせる見事な語り口でした。
「鐘の渡り」。3年ばかり暮らした女をついふた月ほど前に亡くした友人に誘われて晩秋の山にでかける男。自身は春には女と暮らすことになるだろうと思っている。
「―鐘の音に目を覚まして、ひさしぶりにぐっすり眠った気がした。思うことも尽きたように鳴り止んだ。明日からは物も考えなくなるだろう。」
山から帰った晩、女の部屋を訪ね、目の前の女にのめりこんでいく男。山で聞いた鐘の音は二人の幻聴だったのか、とも。
「朝倉のつぶやきが隣でまどろむ自分の内に鐘の音を想わせ、余韻の影を追いきれなくなり目をさました自分の声が朝倉の内に、幻聴ながらおそらくくっきりとした、鐘の音を響かせた。これはつかのまながら交換になりはしないか。暮らした女を亡くした男と、これから女と暮らす心づもりの男との間の。」
こうして、幽冥の世界が描き出される。過ぎ去った者の生の声、声、声。連作を通して通奏低音のごとくに響いてくる。

《つぶやき 2005・2・14 掲載》
最近読んだ本でおもしろいのないかって
いろいろ適当に読んでるからね
小説から歴史物まで
もっぱら図書館が多いね
あまり買わないね、立ち読みはするけど
そう、新刊本もけっこうすぐに書棚に並んでるし
どういう基準なのかわからないこともね
マニアックな本なんかが紹介されているし
職員が選んでるのかな
リクエストもあるのか
オンラインっていうの
なければ他の図書館から取り寄せてくれるしね
ホントあまり買わなくなった
一度読めばもう一回読もうってこともないしね
もっぱら近所の図書館だな
でもほとんど小説みたいなものが多い
いわゆる読まれているやつ、予約が一杯だものね
流行を追っているって思うけど
もっと骨身に染みるような硬派の本もあって欲しいよね
そうそう、最近読んだ小説か
古井由吉さんの「仮往生伝試文」っていうのがおもしろかった、これは
「仮」があってさらに「試文」っていうんだから
随分持って回ったような題名だけど
いずれにせよ「往生」することがテーマさ
古井さんが「昔」書いたものの新装版
でもなかなか読み応えのあった内容でしたよ
久々に硬派の小説を読んだってところですか
エッセーともつかず小説ともつかず
人の死に様に関わる(生き様でもあると)
それをさまざまな人間模様として描いたんだな
作者が50歳頃にね
それが15年後にまた出版されたってこと
「老いるということは、しだいに狂うことではないか。おもむろにやすらかに狂っていくのが
本来、めでたい年の取り方ではないのか。」
なんてすごみがあるけど、滑稽な感じの表現があって
実におもしろかったよ
ところで「昔」っていつのころをさしているのかな
何だかつい1、2年前くらいのことまで
昔はさあなんて言っている人多くないか、最近
昔はそれこそ10年一昔って言ってたよね
だんだん昔の期間が短くなっているような気がしてさ
何だかみんなそうしてすべてを昔の事にして
死に急いでいる、っていうか生き急いでいるような気がしてならないんだけど
昔はむかしはって何だかもうじき往生する人のような口振りで
こうだった、ああだったって若い人までも言っている
ふとこの小説を読んでいてさ
僕等にとってはさ、今も昔もこれからも次第に混沌とした意識の中に
取り込まれていくような
そういうところにしかたなく身を置きつつ生きている・・・
何かさびしい思いになったね
でも死の現実は逃れられないんだから
せいぜい生きた証としての人生を全うしたいよね
それにしてもさ
作者が50歳のころに
こうしたさまざまな晩年を描いていたとはね
一度読んでみてよ、若い人にぜひ勧めるね
厚くて重い本だけど、その分、読み応えがあると思うから
注:本の写真は、二冊とも「アマゾン」からお借りしました。
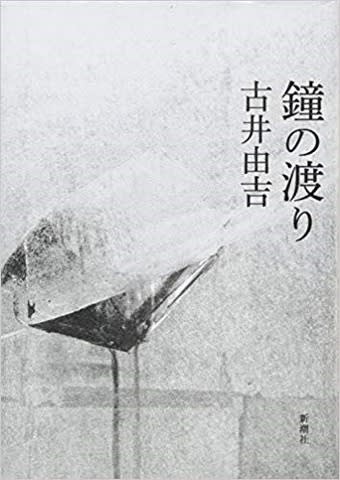
《読書 2014・5・30掲載》
時・空を、あるいは人称を越えた語り口。これが、この方の小説作法なのだろう。夢うつつ、その端境に聞こえる声、声、声・・・。鳥の、赤子の、老人の、両親の、兄弟の、・・・。そして、晩鐘の。否、外界の音だけではない、自らの内から聞こえてくる音。これらの深みに対しては、彩りをなす花々は、どれもこれも「淡い」イメージ、もっといえば、セピア色、さらにいえば、無色透明さえも感じ取らせる。
死者は、息を引き取る際、五感のうちの聴覚が最後まで残っていると聞いたことがある。生者と死者との交流は声をもって終わりとなすか。そして、さまざまな、肉親を含めて人間を看取る主人公。いつか自分も。
老いてますます研ぎ澄まされる聴覚、そして視覚、嗅覚、・・・五感。身体へ心へ染み渡り、醸し出される、不思議(思議せず)な「小説」世界。登場人物たちは、自在に己の世界を紡いでいく、その語り部としての作者に徹底する姿勢は、読者をうならせる魅力にあふれている。
「窓の内」から始まる八つの連作。騒然と、何かにせかされるように生きる(しかない)現代人に静寂をかぎ取る感性というものの豊かさを気づかせる見事な語り口でした。
「鐘の渡り」。3年ばかり暮らした女をついふた月ほど前に亡くした友人に誘われて晩秋の山にでかける男。自身は春には女と暮らすことになるだろうと思っている。
「―鐘の音に目を覚まして、ひさしぶりにぐっすり眠った気がした。思うことも尽きたように鳴り止んだ。明日からは物も考えなくなるだろう。」
山から帰った晩、女の部屋を訪ね、目の前の女にのめりこんでいく男。山で聞いた鐘の音は二人の幻聴だったのか、とも。
「朝倉のつぶやきが隣でまどろむ自分の内に鐘の音を想わせ、余韻の影を追いきれなくなり目をさました自分の声が朝倉の内に、幻聴ながらおそらくくっきりとした、鐘の音を響かせた。これはつかのまながら交換になりはしないか。暮らした女を亡くした男と、これから女と暮らす心づもりの男との間の。」
こうして、幽冥の世界が描き出される。過ぎ去った者の生の声、声、声。連作を通して通奏低音のごとくに響いてくる。

《つぶやき 2005・2・14 掲載》
最近読んだ本でおもしろいのないかって
いろいろ適当に読んでるからね
小説から歴史物まで
もっぱら図書館が多いね
あまり買わないね、立ち読みはするけど
そう、新刊本もけっこうすぐに書棚に並んでるし
どういう基準なのかわからないこともね
マニアックな本なんかが紹介されているし
職員が選んでるのかな
リクエストもあるのか
オンラインっていうの
なければ他の図書館から取り寄せてくれるしね
ホントあまり買わなくなった
一度読めばもう一回読もうってこともないしね
もっぱら近所の図書館だな
でもほとんど小説みたいなものが多い
いわゆる読まれているやつ、予約が一杯だものね
流行を追っているって思うけど
もっと骨身に染みるような硬派の本もあって欲しいよね
そうそう、最近読んだ小説か
古井由吉さんの「仮往生伝試文」っていうのがおもしろかった、これは
「仮」があってさらに「試文」っていうんだから
随分持って回ったような題名だけど
いずれにせよ「往生」することがテーマさ
古井さんが「昔」書いたものの新装版
でもなかなか読み応えのあった内容でしたよ
久々に硬派の小説を読んだってところですか
エッセーともつかず小説ともつかず
人の死に様に関わる(生き様でもあると)
それをさまざまな人間模様として描いたんだな
作者が50歳頃にね
それが15年後にまた出版されたってこと
「老いるということは、しだいに狂うことではないか。おもむろにやすらかに狂っていくのが
本来、めでたい年の取り方ではないのか。」
なんてすごみがあるけど、滑稽な感じの表現があって
実におもしろかったよ
ところで「昔」っていつのころをさしているのかな
何だかつい1、2年前くらいのことまで
昔はさあなんて言っている人多くないか、最近
昔はそれこそ10年一昔って言ってたよね
だんだん昔の期間が短くなっているような気がしてさ
何だかみんなそうしてすべてを昔の事にして
死に急いでいる、っていうか生き急いでいるような気がしてならないんだけど
昔はむかしはって何だかもうじき往生する人のような口振りで
こうだった、ああだったって若い人までも言っている
ふとこの小説を読んでいてさ
僕等にとってはさ、今も昔もこれからも次第に混沌とした意識の中に
取り込まれていくような
そういうところにしかたなく身を置きつつ生きている・・・
何かさびしい思いになったね
でも死の現実は逃れられないんだから
せいぜい生きた証としての人生を全うしたいよね
それにしてもさ
作者が50歳のころに
こうしたさまざまな晩年を描いていたとはね
一度読んでみてよ、若い人にぜひ勧めるね
厚くて重い本だけど、その分、読み応えがあると思うから
注:本の写真は、二冊とも「アマゾン」からお借りしました。
















