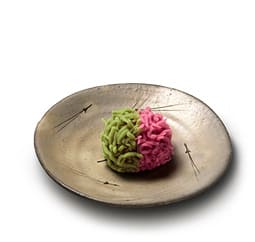バッハよりちょうど100年前生まれたハインリッヒ・シュッツ
その音楽を聴いたことが無いわけではなかったが、
特に印象に残っているわけでもなかった
ところが聴くタイミング、時期というのはあるもので
昨日義理の兄から借りた「カンツィオネ・サクレ(宗教合唱曲集)」の
レコードをかけた瞬間からそのおおらかな音楽に惹かれてしまった
これは思いの外心地よい
バッハみたいに濃密で窮屈ということはない、
モンテヴェルディほど古いって感じはしない
何よりも懐が深くておおらかでゆったり構えて
響きに浸ることができる
例によって聴き方はほとんど歌詞は無視、
レコード解説の対訳は面倒で音楽だけに浸る
音楽に浸ると言う行為は作曲された作品を味わうのと
演奏自体を味わう両面があるが今日の時点では
音楽作品の方に関心がいっている
合唱曲自体めったに聴かないが
合唱曲でもブルックナーの静謐な感じとも
フォーレの清潔な音色とも違う
とにかく響きに身を任せることができる
他の作曲だってそうなのだが
シュッツには何故か大きく包まれるような感じがする
レコードは3枚組
しばらくは楽しめそう
※演奏はドレスデン十字架合唱団
指揮 ルドルフ・マウエンスベルガー
その音楽を聴いたことが無いわけではなかったが、
特に印象に残っているわけでもなかった
ところが聴くタイミング、時期というのはあるもので
昨日義理の兄から借りた「カンツィオネ・サクレ(宗教合唱曲集)」の
レコードをかけた瞬間からそのおおらかな音楽に惹かれてしまった
これは思いの外心地よい
バッハみたいに濃密で窮屈ということはない、
モンテヴェルディほど古いって感じはしない
何よりも懐が深くておおらかでゆったり構えて
響きに浸ることができる
例によって聴き方はほとんど歌詞は無視、
レコード解説の対訳は面倒で音楽だけに浸る
音楽に浸ると言う行為は作曲された作品を味わうのと
演奏自体を味わう両面があるが今日の時点では
音楽作品の方に関心がいっている
合唱曲自体めったに聴かないが
合唱曲でもブルックナーの静謐な感じとも
フォーレの清潔な音色とも違う
とにかく響きに身を任せることができる
他の作曲だってそうなのだが
シュッツには何故か大きく包まれるような感じがする
レコードは3枚組
しばらくは楽しめそう
※演奏はドレスデン十字架合唱団
指揮 ルドルフ・マウエンスベルガー