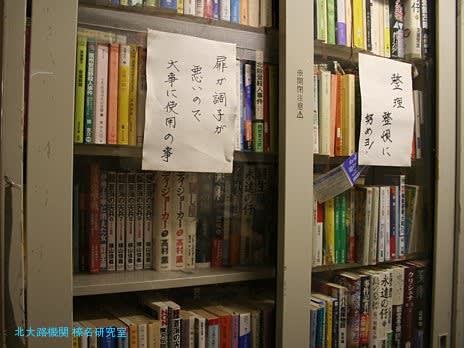■8.15
太平洋戦争の終戦が1945年8月15日、そして今日は2008年8月15日である。幸いにしてというべきか、あの世界大戦を最後に世界の諸国家が二つに分かれての世界大戦は生じず今日に至る。
 空襲と空腹というものが、日本本土における太平洋戦争の大きなシンボルとなっているように思うのだが、幸いにして文民を巻き込んだ本格的な地上戦は、沖縄本島や慶良間、サイパン島など限られた範囲にて展開されたことで限られ、今日の歴史として知ることが出来る欧州の東部戦線と、それに続く都市攻防戦のような悲劇は、ごく限られた範囲に収められた。
空襲と空腹というものが、日本本土における太平洋戦争の大きなシンボルとなっているように思うのだが、幸いにして文民を巻き込んだ本格的な地上戦は、沖縄本島や慶良間、サイパン島など限られた範囲にて展開されたことで限られ、今日の歴史として知ることが出来る欧州の東部戦線と、それに続く都市攻防戦のような悲劇は、ごく限られた範囲に収められた。
 沖縄戦に関する史的事実は、防衛省防衛研究所の戦史研究などによりかなり克明に進められており、特に文民を巻き込んだ大規模な戦闘は、悲惨の一言に尽きる。しかしながら、その災厄の記憶が刻印として日本国の国際関係の展開に大きな影響を行使し、いわゆる憲法9条に基づく平和主義、非核三原則を筆頭とする反核兵器の外交関係展開は、少なくとも日本国民が日本国内で戦火に追われるという事態を防ぐことに寄与したといえる。
沖縄戦に関する史的事実は、防衛省防衛研究所の戦史研究などによりかなり克明に進められており、特に文民を巻き込んだ大規模な戦闘は、悲惨の一言に尽きる。しかしながら、その災厄の記憶が刻印として日本国の国際関係の展開に大きな影響を行使し、いわゆる憲法9条に基づく平和主義、非核三原則を筆頭とする反核兵器の外交関係展開は、少なくとも日本国民が日本国内で戦火に追われるという事態を防ぐことに寄与したといえる。
しかしながら、専守防衛や交戦権の否認という諸政策は、ともすれば大きな誤解を招くのではないかという点を、今回は問題として提起したい。
■武力を考慮しないという平和主義への疑問
日本国憲法は、強く平和を希求し、なおかつ軍事力そのものの存在を否定した世界唯一の憲法であり、国家による戦争動員という暴力からの自由を銘記した稀有な憲法である。
 付け加えるならば、日本国憲法は憲法24条において、いわゆる父権主義を否定することにより男女同権を銘記した、これも世界唯一の憲法である。意外に思われるかもしれないが、現時点で男女同権を銘記した憲法は男女同権が強く叫ばれる欧米諸国には皆無であり、日本国憲法が唯一のものである。したがって、国家からの戦争動員という暴力からの自由に加え、家庭内での父権主義という構造的暴力を排した世界に誇れる憲法である。
付け加えるならば、日本国憲法は憲法24条において、いわゆる父権主義を否定することにより男女同権を銘記した、これも世界唯一の憲法である。意外に思われるかもしれないが、現時点で男女同権を銘記した憲法は男女同権が強く叫ばれる欧米諸国には皆無であり、日本国憲法が唯一のものである。したがって、国家からの戦争動員という暴力からの自由に加え、家庭内での父権主義という構造的暴力を排した世界に誇れる憲法である。
 しかしながら、軍事力の存在を否定したものの、国際の平和と安全は諸国家の努力により担保されるという状況は替わらず、武力紛争は恒常的な存在として国際関係の主たる問題に挙げられている。こうした中で、日本は、軍事力により担保される防衛という問題に対応するべく1954年に自衛隊を創設し、専守防衛を国是として軍事安全保障への政策を展開している。
しかしながら、軍事力の存在を否定したものの、国際の平和と安全は諸国家の努力により担保されるという状況は替わらず、武力紛争は恒常的な存在として国際関係の主たる問題に挙げられている。こうした中で、日本は、軍事力により担保される防衛という問題に対応するべく1954年に自衛隊を創設し、専守防衛を国是として軍事安全保障への政策を展開している。
 他方で、マハンを挙げるまでも無いが、日本は諸国家との交易により経済を稼動させており、原材料、化石燃料から食料に至るまでの産品を交易により入手して経済活動を営んでいる。いわば、諸国家の安全と海洋の自由通行に依拠した国家であり、これが防衛即本土決戦というべき専守防衛と必ずしも合致するのかについて、明確な国家戦略にあたるものは、残念ながら存在せず、暫時必要な政策を適宜法整備のもとで実施している。
他方で、マハンを挙げるまでも無いが、日本は諸国家との交易により経済を稼動させており、原材料、化石燃料から食料に至るまでの産品を交易により入手して経済活動を営んでいる。いわば、諸国家の安全と海洋の自由通行に依拠した国家であり、これが防衛即本土決戦というべき専守防衛と必ずしも合致するのかについて、明確な国家戦略にあたるものは、残念ながら存在せず、暫時必要な政策を適宜法整備のもとで実施している。
 また、攻撃を受けて初めて自衛権を発動するという防衛政策は、つまり国境が海洋を隔てている地政学上の要件から、必ずしも大陸国家が行うような専守防衛即本土決戦という政策は妥当とは言えず、海洋の自由というシーコントロオルの概念に依拠するべきではないのか。少なくとも、攻撃を受けるまで自衛権を発動し得ないという専守防衛の体系では、結果的に自国民の居住する本土を戦域とすることで、言い換えれば、期せずして自国民を盾とすることを強いる防衛戦略となっている。
また、攻撃を受けて初めて自衛権を発動するという防衛政策は、つまり国境が海洋を隔てている地政学上の要件から、必ずしも大陸国家が行うような専守防衛即本土決戦という政策は妥当とは言えず、海洋の自由というシーコントロオルの概念に依拠するべきではないのか。少なくとも、攻撃を受けるまで自衛権を発動し得ないという専守防衛の体系では、結果的に自国民の居住する本土を戦域とすることで、言い換えれば、期せずして自国民を盾とすることを強いる防衛戦略となっている。
防衛と安全保障という国際関係の展開。これには必ずしも軍事力を必要としない局面もあるのだが、軍事力を念頭に置いた上での総合的な安全保障問題の難題を解決し、諸国家との友好な関係を展開してゆくという政策が、主体的に展開されているかといわれれば、これは著しくバランスを欠いている状態の下で実施されているといわざるを得ないのではないかと考える。
■恒常的に選択される武力行使
日本は外交関係において少なからず武力行使、という選択を採ってきている。意外に思われるかもしれないが、こういう事は可能だ。かなり混乱するかもしれないが、国際法では武力行使(Used force)と、武力攻撃(Armd Attack)というように区分されており、このForce(スターウォーズでいうところのフォースの力)の強制力には、いわゆる経済制裁なども含まれると解されるので、例えばアパルトヘイトに伴う南アへの経済制裁や、ココムによる共産圏への輸出規制も含まれ得る(曖昧に表現したのは、学説により分かれる為) 。
武力行使そのものは国連憲章二条四項において禁止されており(ちなみに憲章に明記されている武力行使は“use of force”)、例外として国連によるuse of force、そして国連憲章51条に基づく自衛権の発動としてのuse of forceが挙げられている。Armd AttackとUsed forceであるが、Armd Attackの定義は、比較的明瞭であるものの、Used forceについては解釈が分かれ、参考として国連憲章25条に拘束力を有するとされた安全保障理事会決議に基づく、国連憲章40条の“停戦命令や軍の撤退の要求”、国連憲章41条の“経済封鎖、外交関係の断絶”がUsed force、国連憲章42条の“秩序の回復の為の陸海空軍の派遣”がUsed forceとArmd Attackに含まれると考えることが出来る。
42条に関して派遣=戦闘による強制力行使、とは言い切れないので、解釈の余地が残るが(演習により圧力を掛ける、包囲して特定の行動を強いるのがUsed force、直接介入することをArmd Attack)、同じように経済封鎖、外交関係の断絶を銘記したいわゆる非軍事的措置にも“全面か部分的かについての解釈の余地”が残る。この点に依拠すれば、日本はUsed force、つまり強制力の行使という意味での、武力行使を行っているといえる。
二条四項で、武力行使は禁止されているが、武力行使にあたるかは、国連憲章39条に“安全保障理事会は平和に関する脅威(中略)を決定し・・・”という文言がある為、Used forceのforceが全て禁止されていると読むのは早計である。無論、悪い、という訳では全く無いのだが、国際法上のUsed forceを、日本は外交関係の展開に際して、恒常的に行っているという事を記憶しておく必要はあるのではないか。
■世界の安全保障の根幹部分に関与
国際の平和と安全、というと、やはり防衛、つまり軍事としての安全保障を筆頭として連想する方が多いのではないかと思う。根拠は、国際貢献=PKOという広範な解釈の類型だ。
 しかしながら、予防外交という、武力紛争を未然に防ごうという国際関係の展開においては、軍事力の展開による武力紛争の抑止はあくまでも最終的な手段として用いられており、軍備管理、信頼醸成という手法が、その一つ前にあり、さらにその一つ前に広範な外交関係の展開による紛争や係争の平和的解決などが用いられる。なるほど、深刻な武力紛争に軍事力をもって介入して平和な状態を取り戻すよりは、そもそも武力紛争の要因となる紛争や係争を平和的に解決する方が、労力は少なくてすむ。
しかしながら、予防外交という、武力紛争を未然に防ごうという国際関係の展開においては、軍事力の展開による武力紛争の抑止はあくまでも最終的な手段として用いられており、軍備管理、信頼醸成という手法が、その一つ前にあり、さらにその一つ前に広範な外交関係の展開による紛争や係争の平和的解決などが用いられる。なるほど、深刻な武力紛争に軍事力をもって介入して平和な状態を取り戻すよりは、そもそも武力紛争の要因となる紛争や係争を平和的に解決する方が、労力は少なくてすむ。
 こうした中で、国際金融の安定化に、日本は大きな影響力を有している。第二次大戦以降の国際経済体制の再建以来今日に至るまで、ブレトンウッズ体制に基づく、ドルを国際通貨とした国際金融の体制が維持されているが、ドルが金と交換出来るというドル体制にあって、1968年、アメリカの経済収支赤字によってドル体制に危機が生じたことがあった。この際、既に経済大国への道を歩んでいた日本は、ドル体制を支える為の金プール協定に参加しており、その後、通貨切下げや切上げなどの面でドル体制を支えてきた。
こうした中で、国際金融の安定化に、日本は大きな影響力を有している。第二次大戦以降の国際経済体制の再建以来今日に至るまで、ブレトンウッズ体制に基づく、ドルを国際通貨とした国際金融の体制が維持されているが、ドルが金と交換出来るというドル体制にあって、1968年、アメリカの経済収支赤字によってドル体制に危機が生じたことがあった。この際、既に経済大国への道を歩んでいた日本は、ドル体制を支える為の金プール協定に参加しており、その後、通貨切下げや切上げなどの面でドル体制を支えてきた。
 以後、国際通貨ドルを支えたのは、インフレ率が低く、経常収支赤字の度合いが少ない日本円とドイツマルクであり、特に比較的早い時期に地域為替媒介通貨としての地位に至ったドイツマルクを、牽引しドル体制の維持に注力したのは日本である。国際金融体制の防衛による国際経済の安定化には、日本が払った努力は非常に大きく、少なくとも経済安全保障の展開においては、日本はその根幹的な位置にある。近年、競争力を伸ばす中華人民共和国の存在はあるものの、いまだ固定相場制を維持しており、ドルを支える位置に昇華することは不可能であるため、当分はこの位置は不変であろう。
以後、国際通貨ドルを支えたのは、インフレ率が低く、経常収支赤字の度合いが少ない日本円とドイツマルクであり、特に比較的早い時期に地域為替媒介通貨としての地位に至ったドイツマルクを、牽引しドル体制の維持に注力したのは日本である。国際金融体制の防衛による国際経済の安定化には、日本が払った努力は非常に大きく、少なくとも経済安全保障の展開においては、日本はその根幹的な位置にある。近年、競争力を伸ばす中華人民共和国の存在はあるものの、いまだ固定相場制を維持しており、ドルを支える位置に昇華することは不可能であるため、当分はこの位置は不変であろう。
■一国安全保障の限界
日本はアメリカの世界戦略に利用されている云々という論調を偶に見かけることがある。しかしながら、国際経済の連環からは日本もアメリカも逃れることは出来ず、これは問題視すべき命題というよりは、グローバリゼーションへの再認識以上のものではない。
 相互に影響される諸国家の関係をみれば、日本の国家や国民の生活は国際の平和と安全に依拠したものである。さて、国際金融における日本の位置づけは既に述べたが、少なくとも、日本が一国平和主義という政策目標を実現するには、グローバリゼーションが進む国際関係において、国際政治(もしくは世界政治)において関与し、手段は別としても国際の平和と安全を維持させる努力無くしては、今日の安定と繁栄を維持させることは難しいのではないか、といえる。
相互に影響される諸国家の関係をみれば、日本の国家や国民の生活は国際の平和と安全に依拠したものである。さて、国際金融における日本の位置づけは既に述べたが、少なくとも、日本が一国平和主義という政策目標を実現するには、グローバリゼーションが進む国際関係において、国際政治(もしくは世界政治)において関与し、手段は別としても国際の平和と安全を維持させる努力無くしては、今日の安定と繁栄を維持させることは難しいのではないか、といえる。
 少なくとも、一国平和主義という政策は、国際関係に対する選択肢を前に自ら視野狭窄に陥るのではないか、という問題が挙げられる。近年では、例えばオタワプロセスにおける対人地雷全廃条約、オスロプロセスにおけるクラスター爆弾禁止条約の原動力となったNGOの存在のように、いわゆる“規範起業家”という存在がある。諸国民に受け入れられる国際公序に基づき、規範を提起する存在であるが、一国平和主義を貫けば国際規範との接点が少なくなってしまう訳だ。
少なくとも、一国平和主義という政策は、国際関係に対する選択肢を前に自ら視野狭窄に陥るのではないか、という問題が挙げられる。近年では、例えばオタワプロセスにおける対人地雷全廃条約、オスロプロセスにおけるクラスター爆弾禁止条約の原動力となったNGOの存在のように、いわゆる“規範起業家”という存在がある。諸国民に受け入れられる国際公序に基づき、規範を提起する存在であるが、一国平和主義を貫けば国際規範との接点が少なくなってしまう訳だ。
 また、日本のように集団的自衛権の行使(現在の内閣法制局の統一解釈では、集団的自衛権を有しているが行使は留保している)を否認した一国平和主義に基づきつつ、必要な防衛力を整備するという方策は、結果的にその軍事力が何処へ指向しているかが不透明と成りえる。どちらに指向しているかが明確にされず、加えて、軍事力を憲法上否定したことにより、その行使への分水嶺が明確にし得ないという関係上、その行使が如何なる条件の元で行いえるかが提示されていないことは、何時使われるか、何処へ使われるかが不明確であることを示し、かえって国際関係にマイナスの要素を加えてしまうのではないかという疑問が生じる。
また、日本のように集団的自衛権の行使(現在の内閣法制局の統一解釈では、集団的自衛権を有しているが行使は留保している)を否認した一国平和主義に基づきつつ、必要な防衛力を整備するという方策は、結果的にその軍事力が何処へ指向しているかが不透明と成りえる。どちらに指向しているかが明確にされず、加えて、軍事力を憲法上否定したことにより、その行使への分水嶺が明確にし得ないという関係上、その行使が如何なる条件の元で行いえるかが提示されていないことは、何時使われるか、何処へ使われるかが不明確であることを示し、かえって国際関係にマイナスの要素を加えてしまうのではないかという疑問が生じる。
 少なくとも、国際関係における規範起業家が提示するような諸問題は、兵器、貧困、開発、環境などのグローバルな諸問題に国境に捉われず解決までの手法や問題の緩和への提案が為されており、対して、一国平和主義という視野狭窄な立場に留まれば、かえって諸国家の平和(これは軍事という狭義の平和に留まらず広義の平和を示す)に混乱を来たすのではないか、という危惧も持ち得る。
少なくとも、国際関係における規範起業家が提示するような諸問題は、兵器、貧困、開発、環境などのグローバルな諸問題に国境に捉われず解決までの手法や問題の緩和への提案が為されており、対して、一国平和主義という視野狭窄な立場に留まれば、かえって諸国家の平和(これは軍事という狭義の平和に留まらず広義の平和を示す)に混乱を来たすのではないか、という危惧も持ち得る。
 手段として平和を用いても、結果として平和以外のものが到来しては本末転倒である。いわば、達成できる目的としての平和を希求するには、どのようなものがあるのか。いわゆる、一方的な軍備廃止や強制的停戦というような手段としての平和を用いれば歪が生じて短期間で平和ではない方向に指向する。
手段として平和を用いても、結果として平和以外のものが到来しては本末転倒である。いわば、達成できる目的としての平和を希求するには、どのようなものがあるのか。いわゆる、一方的な軍備廃止や強制的停戦というような手段としての平和を用いれば歪が生じて短期間で平和ではない方向に指向する。
 他方、長期的な平和という目的を達するには、もちろん、ミクロ、マクロの観点から様々な方策があり得、更に試行錯誤があり得る命題だ。整理する間もなく書き連ねた弱み、問題提起に終わることは恐縮であるが、いわゆる、祈るような平和主義と平和祈念から脱却した上での、戦争と平和に関する再検討が必要なのではないか、と考えて終戦記念日の記述としたい。
他方、長期的な平和という目的を達するには、もちろん、ミクロ、マクロの観点から様々な方策があり得、更に試行錯誤があり得る命題だ。整理する間もなく書き連ねた弱み、問題提起に終わることは恐縮であるが、いわゆる、祈るような平和主義と平和祈念から脱却した上での、戦争と平和に関する再検討が必要なのではないか、と考えて終戦記念日の記述としたい。
HARUNA
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
 8月19日、撮影時刻は0920時頃。全通飛行甲板を有する実質的に軽空母といえるヘリコプター護衛艦「ひゅうが」と、ヘリコプター3機を搭載し、対潜掃討を行う対潜作戦中枢艦として建造されたヘリコプター護衛艦「はるな」。設計や運用計画に30年の期間を置くと、海上自衛隊の任務拡大や政治の戦略的転換という背景が垣間見える2隻である。「はるな」の飛行甲板には、SH-60ヘリコプター1機が出ていることが望見出来る。「はるな」型と「しらね」型は、距離が遠いと、一瞬艦影を見間違えることもあるかもしれないが、これだけ違うと、その心配も無い。
8月19日、撮影時刻は0920時頃。全通飛行甲板を有する実質的に軽空母といえるヘリコプター護衛艦「ひゅうが」と、ヘリコプター3機を搭載し、対潜掃討を行う対潜作戦中枢艦として建造されたヘリコプター護衛艦「はるな」。設計や運用計画に30年の期間を置くと、海上自衛隊の任務拡大や政治の戦略的転換という背景が垣間見える2隻である。「はるな」の飛行甲板には、SH-60ヘリコプター1機が出ていることが望見出来る。「はるな」型と「しらね」型は、距離が遠いと、一瞬艦影を見間違えることもあるかもしれないが、これだけ違うと、その心配も無い。 護衛艦「ひゅうが」は満載排水量18000㌧。近年、「はるな」の満載排水量は6800㌧である。4月に掲載したフランス海軍の「ミストラル」のように、各国では国際貢献任務などへの能力充実を期して商船構造を採用するなど極力船価を抑え大型化を行う、いわゆる戦力投射艦が建造されているが、護衛艦「ひゅうが」は、速力や電子機器の配置などから、戦力投射艦というよりは、従来型の水上戦た対潜戦に重点を置いた伝統的な軽空母としての構造を採用している。
護衛艦「ひゅうが」は満載排水量18000㌧。近年、「はるな」の満載排水量は6800㌧である。4月に掲載したフランス海軍の「ミストラル」のように、各国では国際貢献任務などへの能力充実を期して商船構造を採用するなど極力船価を抑え大型化を行う、いわゆる戦力投射艦が建造されているが、護衛艦「ひゅうが」は、速力や電子機器の配置などから、戦力投射艦というよりは、従来型の水上戦た対潜戦に重点を置いた伝統的な軽空母としての構造を採用している。 ミサイル護衛艦「きりしま」と「ひゅうが」。「こんごう」型イージス艦として、「あたご」型の就役まで日本最大の護衛艦の一隻であった「きりしま」の満載排水量は9500㌧とかなり大型なのだが、比べても「ひゅうが」は大きい。「ひゅうが」は全通飛行甲板を採用しているが、試験艦「あすか」にて研究を重ねたFCS-3改と、OQQ-21ソーナーを搭載し、新アスロックやESSM(発展型シースパロー)など対空対潜装備を有している護衛艦でもあるのだ。
ミサイル護衛艦「きりしま」と「ひゅうが」。「こんごう」型イージス艦として、「あたご」型の就役まで日本最大の護衛艦の一隻であった「きりしま」の満載排水量は9500㌧とかなり大型なのだが、比べても「ひゅうが」は大きい。「ひゅうが」は全通飛行甲板を採用しているが、試験艦「あすか」にて研究を重ねたFCS-3改と、OQQ-21ソーナーを搭載し、新アスロックやESSM(発展型シースパロー)など対空対潜装備を有している護衛艦でもあるのだ。 「ひゅうが」と沖留の「むらさめ」型護衛艦。この日は、シンガポール海軍のフリゲイトが寄港するなか、リムパックより帰港する「はるな」、「きりしま」を迎え入れるべく吉倉桟橋では四隻並列係留、「はたかぜ」を隣の船越地区に係留し、それでも横須賀に入りきらない護衛艦は沖留とするなど頻繁に入出港やバースチェンジが行われていた。「ひゅうが」の海上自衛隊の引渡しは来年行われるとされる。
「ひゅうが」と沖留の「むらさめ」型護衛艦。この日は、シンガポール海軍のフリゲイトが寄港するなか、リムパックより帰港する「はるな」、「きりしま」を迎え入れるべく吉倉桟橋では四隻並列係留、「はたかぜ」を隣の船越地区に係留し、それでも横須賀に入りきらない護衛艦は沖留とするなど頻繁に入出港やバースチェンジが行われていた。「ひゅうが」の海上自衛隊の引渡しは来年行われるとされる。