年内には予想される総選挙。さまざまな思惑を秘めて、「熱い・暑い」夏。すでに30日を過ぎても猛暑が続きます。
戦前、関東大震災、世界恐慌、中国・朝鮮情勢などの混沌の中にもかかわらず、「明治憲法」下にあった国会が全く機能せず、今と同じように首相も1年ごとに交代する。当時の二大政党がお互いに権謀術数のあげく、国民の政治不信を増大させ、そのあげく、軍部のクーデター(まがい)によって、政党政治が滅亡していった。その後、戦争、戦争によって崩壊した日本の歴史。いやな感じがしてなりません。
つい興味がそのあたりに集中、といっても搦め手、かつ濫読です。以下、抜き書きで。
 「ヒトラー『わが闘争』がたどった数奇な運命」(アントワーヌ・ヴィトキーヌ)河出書房新社
「ヒトラー『わが闘争』がたどった数奇な運命」(アントワーヌ・ヴィトキーヌ)河出書房新社
「どんなに偏執的で暴力的な政治プロジェクトであれ、過小評価することなく、真剣に対処するということ。その政策が公表されており、実際に実現可能な立場にある者の主張であればなおさらである。・・・言葉には意味がある。言葉によって現実は変わるのだ。しかも、最悪の形で現実化することすらある。」・・・
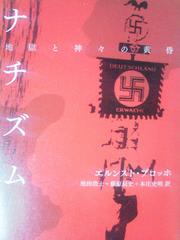 「ナチズムー地獄と神々の黄昏」(エルンスト・ブロッホ)水声社
「ナチズムー地獄と神々の黄昏」(エルンスト・ブロッホ)水声社
池田(浩士)ー・・・本書の魅力をひとことで言えば、ナチズムとの思想的対決ということに尽きると思います。・・・ー
ー・・・もうすでにナチの時代になったあとでも、まだドイツ国内で普通に生きている人間には徴候としてすらも見えてこないような毎日の出来事が無数にあって、それは文字通り「まだ意識されていないもの」なんです。その「まだ意識されていないもの」を思想的にしっかり見ていくということが、ブロッホのナチス批判の方法でもあるんでしょうね・・・ー
(解説としての翻訳者の対談の中から)
 「戦争の甘い誘惑」(クリス・ヘッジズ)河出書房新社
「戦争の甘い誘惑」(クリス・ヘッジズ)河出書房新社
執筆当時(2003年)、筆者は「ニューヨーク・タイムズ」の記者。湾岸戦争、イスラエル・パレスチナ紛争、ボスニア、コソボ、スーダンなど1998年までの15年間、従軍記者として世界各地に派遣された。その体験の上からの戦争論。特に報道姿勢について。
「もし戦争の大義が破産したと見なされるなら、これ以上戦闘を遂行することは難しくなる、というより多分不可能になるだろう。戦争努力にとって、大義の神聖性は不可欠である。大義を護り説明し増進するために、国家は多くの時間を割く。そのなかで最も重要な役割を担うのはリポーターである。・・・国家事業は宗教的オーラに包まれる。プレスも声を合わせて同じ言葉で話しだす。・・・戦争の大義は、神に捧げられた神秘に包まれて、難攻不落である。大義の欺瞞性を暴きたて自家撞着ぶりを明らかにしようとすれば、あしざまに罵られ孤立するだけだ。」・・・
「日韓ナショナリズムの解体」(李建志)筑摩書房
「自分が直接差別行動をしていない(と思っている)としても、『暴力』に参加していないとは限らないということだ。私を含むすべてのひとが『無意識で善意の』ナショナリズムをその行動の内面に宿してしまっている以上、これは避けられない。・・・本書で取り上げたような『複数のアイデンティティを持つもの』は、日常的に『暴力』にさらされているのだということに、気づいて欲しいのだ。」・・・
「複数のアイデンティティを生きる思想」と副題にあります。日本人、在日韓国朝鮮人、中国人、東南アジアなど、さまざまな人間が生活する現実の日本において、日韓、日中の領土問題をきっかけにした「ナショナリズム」のあり方を改めて考える(取り上げる)機会になれば、と思って読み進めています。
戦前、関東大震災、世界恐慌、中国・朝鮮情勢などの混沌の中にもかかわらず、「明治憲法」下にあった国会が全く機能せず、今と同じように首相も1年ごとに交代する。当時の二大政党がお互いに権謀術数のあげく、国民の政治不信を増大させ、そのあげく、軍部のクーデター(まがい)によって、政党政治が滅亡していった。その後、戦争、戦争によって崩壊した日本の歴史。いやな感じがしてなりません。
つい興味がそのあたりに集中、といっても搦め手、かつ濫読です。以下、抜き書きで。
 「ヒトラー『わが闘争』がたどった数奇な運命」(アントワーヌ・ヴィトキーヌ)河出書房新社
「ヒトラー『わが闘争』がたどった数奇な運命」(アントワーヌ・ヴィトキーヌ)河出書房新社「どんなに偏執的で暴力的な政治プロジェクトであれ、過小評価することなく、真剣に対処するということ。その政策が公表されており、実際に実現可能な立場にある者の主張であればなおさらである。・・・言葉には意味がある。言葉によって現実は変わるのだ。しかも、最悪の形で現実化することすらある。」・・・
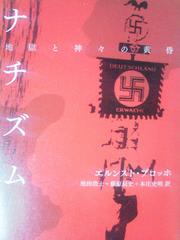 「ナチズムー地獄と神々の黄昏」(エルンスト・ブロッホ)水声社
「ナチズムー地獄と神々の黄昏」(エルンスト・ブロッホ)水声社池田(浩士)ー・・・本書の魅力をひとことで言えば、ナチズムとの思想的対決ということに尽きると思います。・・・ー
ー・・・もうすでにナチの時代になったあとでも、まだドイツ国内で普通に生きている人間には徴候としてすらも見えてこないような毎日の出来事が無数にあって、それは文字通り「まだ意識されていないもの」なんです。その「まだ意識されていないもの」を思想的にしっかり見ていくということが、ブロッホのナチス批判の方法でもあるんでしょうね・・・ー
(解説としての翻訳者の対談の中から)
 「戦争の甘い誘惑」(クリス・ヘッジズ)河出書房新社
「戦争の甘い誘惑」(クリス・ヘッジズ)河出書房新社執筆当時(2003年)、筆者は「ニューヨーク・タイムズ」の記者。湾岸戦争、イスラエル・パレスチナ紛争、ボスニア、コソボ、スーダンなど1998年までの15年間、従軍記者として世界各地に派遣された。その体験の上からの戦争論。特に報道姿勢について。
「もし戦争の大義が破産したと見なされるなら、これ以上戦闘を遂行することは難しくなる、というより多分不可能になるだろう。戦争努力にとって、大義の神聖性は不可欠である。大義を護り説明し増進するために、国家は多くの時間を割く。そのなかで最も重要な役割を担うのはリポーターである。・・・国家事業は宗教的オーラに包まれる。プレスも声を合わせて同じ言葉で話しだす。・・・戦争の大義は、神に捧げられた神秘に包まれて、難攻不落である。大義の欺瞞性を暴きたて自家撞着ぶりを明らかにしようとすれば、あしざまに罵られ孤立するだけだ。」・・・
「日韓ナショナリズムの解体」(李建志)筑摩書房
「自分が直接差別行動をしていない(と思っている)としても、『暴力』に参加していないとは限らないということだ。私を含むすべてのひとが『無意識で善意の』ナショナリズムをその行動の内面に宿してしまっている以上、これは避けられない。・・・本書で取り上げたような『複数のアイデンティティを持つもの』は、日常的に『暴力』にさらされているのだということに、気づいて欲しいのだ。」・・・
「複数のアイデンティティを生きる思想」と副題にあります。日本人、在日韓国朝鮮人、中国人、東南アジアなど、さまざまな人間が生活する現実の日本において、日韓、日中の領土問題をきっかけにした「ナショナリズム」のあり方を改めて考える(取り上げる)機会になれば、と思って読み進めています。

















