約300ページ、しかも文字がページ全体にびっしり詰まっていて段落もない
その気にならないと読みきれない本の最後のページまで昨日到達した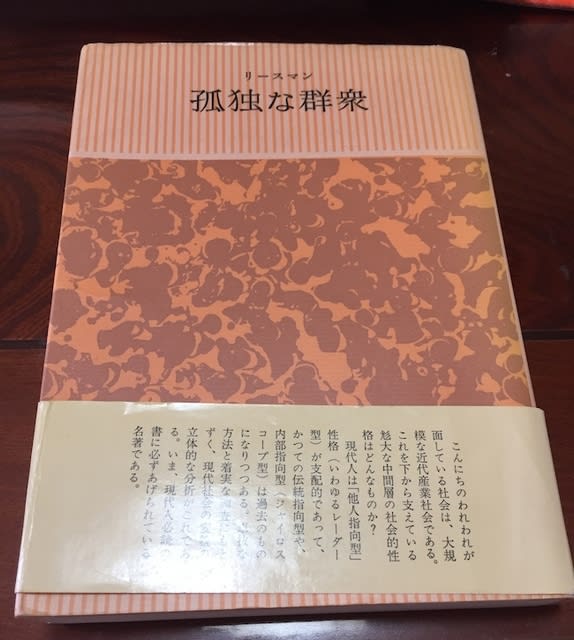
「孤独な群衆」 リースマンの社会学の本だ
むかし読み終えた時に、いつか再読しなくてはならないと感じていたが、最近の読書モードのおかげで
この小さな文字の本に再挑戦、それなりに楽しむことが出来た
文字が詰まっていても、その前に読んだハンナ・アーレントもそうだったので、多少慣れがあったのと
「全体主義の起源」とか「イスラエルのアイヒマン」ほど集中力を要さないで済むために
そんなに手こずった印象はない
しかし、残念なのは「こんな内容だったのか」と思ってしまったことだ(何という記憶力のなさ!)
むかしは、多少興奮して読み終えた
伝統指向型から内部思考型、それから他人指向型へと人の性格の変化と
それに伴う社会の変化がアメリカの実情を例として取り上げられ、まるでそれが
何十年も前のことではなく現在もそのまま通用しそうだった
今回もやはりその現代性は納得でき、ところどころ付箋をつけようと思ったものの
全体としては「社会の解釈のひとつ」みたいな一歩引いたところからの見方が
年齢のせいかできるようになっていた
確かにところどころは洞察力と現実に沿った記述がある
例えば第2部には
政治スタイルから見た3種類として、(1)無関心派・(2)道徳屋・(3)内幕情報屋などという
少しばかり興味をそそるような言葉が使われている
この分類から続いて、政治的説得ー憤慨と寛容
(1)消費の対象としての政治
(2)寛容の教師としてのメディア
(3)メディアは政治から逃げるか
(4)憤慨の貯水池
へと話は続き、さらに権力のイメージの章には
(1)指導者と被指導者
(2)権力を持っているのは誰か
などがマックス・ウェーバーよりは観念的でなく、リアリティをもってイメージができた
特にメディアの力は(この本ではまだテレビも初期で新聞が大きな影響力をもっていた)
相当なものとして扱われている
ただ最後のページに至ってフト感じたことと言えば、内容に関係なくて少しばかり情けないが
何故この人(リースマン)はこんな量の多い(書くための資料も膨大な)
あまり人が読みそうもないものを、書き終えたのだろうか、、という疑問だ
既に彼は社会学の大家として地位を確立されていたのか、誰もが無条件に耳を傾ける存在
であったかどうかは、自分は知らない
だがこれだけのエネルギーを要する本を書き上げるのは、どこかしら使命感がないとできない
これは最終章に自分の思いとして述べられているが、、こういう人がかつてある国にいた
という事実は、とても羨ましい(今の日本にこのような人はいるか?)
厚い本といえばピケティの「21世紀の資本」も相当な分量だったが、
彼も功名心だけでなく何らかの使命感(格差の存在に対する道徳的不満と、それが引き起こす悪い社会変化を避けるような)
に燃えて書き上げられたと感じたことがあった
これらの多くの人には読まれないかもしれないが、何かしらの使命感に導かれて
結果的に人の為になる(人類の宝となる)作品を残す、、、というのは
そして残されたものを同じだけの熱量を持って体験するというのは
本当はとても大事なことだと思うのだが、、現代の日本の社会はと思いを馳せると少しばかり不安になる
そんなことを連想していると「愚民化政策」という言葉を思い出してしまった
「パンとサーカス」が現代の日本では「スポーツとスキャンダル」になってはいないか
なんだかとても不安だな、、
田舎のおっさんのボヤキ


















