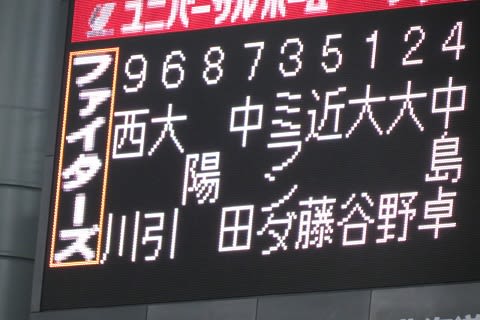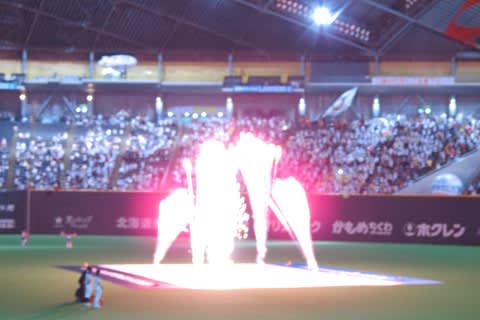今や日本を代表する指揮者の一人となった佐渡裕氏の出発点はPMFだったという。PMFの創始者であるレナード・バーンスタインに師事し、彼に鍛えられ、PMFで貴重な経験を積み、今の佐渡裕があると語る氏の話に耳を傾けた。
5月18日(日)午後、札幌駅前通地下歩行空間(チ・カ・ホ)の北3条広場において「PMF25回記念スペシャルプレイベント」と銘打って、指揮者の佐渡裕氏と音楽評論家(いうよりはスポーツ評論家としての方が名高いが)の玉木正之氏の対談が行われた。

※ 対談中の写真はNGだったのだが、終了後に写しました。
さすがに世に名高い佐渡氏である。会場の北3条広場は開始30分前に行ったところすでに立錐の余地がないほどびっしりと聴衆が集まっていた。もっと対談に相応しい場所でゆっくりと聴きたいと思ったが、立ったまま聴く90分間はかなりの苦行だった。
佐渡氏とPMFの関係は、PMFが始まった1990~1997年までの8年間に及ぶということだ。
そもそもは佐渡氏が1987年のアメリカのタングルウッド音楽祭(PMFと同じ教育音楽祭)でレナード・バーンスタインに認められたことからPMFに関わることになったようだ。
レナード・バーンスタインの提唱で始まったPMFは、彼が第1回目の音楽監督(首席指揮者)務めたが、その際佐渡裕氏をレジデント指揮者に指名している。レジデント指揮者とは首席指揮者を助けるような役割のようである。バーンスタインは1回目の音楽監督を務めた後亡くなってしまったが、佐渡氏はその後6年間もレジデント指揮者を務めている。
レジデント指揮者の主な役割として、PMF参加希望者のオーディションを世界各地で行い、選抜することだそうだが毎年1,000人を超える音楽家の卵の演奏を聴いて選抜することは自身のために大変勉強になったという。
バーンスタインとの思い出、自身のこれからのこと、PMFに対する思い、などなど多方面にわたり雄弁に語った佐渡氏だったが、対談相手が玉木氏だったというのは企画側のヒットだったかもしれない。佐渡氏の多方面にわたる素顔を引き出してくれたように思う。へんに専門的な話に偏らなかったのが良かったように思う。

※ ご覧のように会場は立錐の余地がないほどびっしりでした。
佐渡氏はPMFの今後について「提唱者であったバーンスタインの思いを大切にしながら、札幌の地でいつまでもPMFが続いてほしい。そのためにも多くの人がPMFの演奏会に足を運んでほしい」と結んだ。
私 はこれまでそれほどPMFを盛り上げる力にはなっていなかったが、少しはその力にならなければ、と心を新たにした思いだった。
5月18日(日)午後、札幌駅前通地下歩行空間(チ・カ・ホ)の北3条広場において「PMF25回記念スペシャルプレイベント」と銘打って、指揮者の佐渡裕氏と音楽評論家(いうよりはスポーツ評論家としての方が名高いが)の玉木正之氏の対談が行われた。

※ 対談中の写真はNGだったのだが、終了後に写しました。
さすがに世に名高い佐渡氏である。会場の北3条広場は開始30分前に行ったところすでに立錐の余地がないほどびっしりと聴衆が集まっていた。もっと対談に相応しい場所でゆっくりと聴きたいと思ったが、立ったまま聴く90分間はかなりの苦行だった。
佐渡氏とPMFの関係は、PMFが始まった1990~1997年までの8年間に及ぶということだ。
そもそもは佐渡氏が1987年のアメリカのタングルウッド音楽祭(PMFと同じ教育音楽祭)でレナード・バーンスタインに認められたことからPMFに関わることになったようだ。
レナード・バーンスタインの提唱で始まったPMFは、彼が第1回目の音楽監督(首席指揮者)務めたが、その際佐渡裕氏をレジデント指揮者に指名している。レジデント指揮者とは首席指揮者を助けるような役割のようである。バーンスタインは1回目の音楽監督を務めた後亡くなってしまったが、佐渡氏はその後6年間もレジデント指揮者を務めている。
レジデント指揮者の主な役割として、PMF参加希望者のオーディションを世界各地で行い、選抜することだそうだが毎年1,000人を超える音楽家の卵の演奏を聴いて選抜することは自身のために大変勉強になったという。
バーンスタインとの思い出、自身のこれからのこと、PMFに対する思い、などなど多方面にわたり雄弁に語った佐渡氏だったが、対談相手が玉木氏だったというのは企画側のヒットだったかもしれない。佐渡氏の多方面にわたる素顔を引き出してくれたように思う。へんに専門的な話に偏らなかったのが良かったように思う。

※ ご覧のように会場は立錐の余地がないほどびっしりでした。
佐渡氏はPMFの今後について「提唱者であったバーンスタインの思いを大切にしながら、札幌の地でいつまでもPMFが続いてほしい。そのためにも多くの人がPMFの演奏会に足を運んでほしい」と結んだ。
私 はこれまでそれほどPMFを盛り上げる力にはなっていなかったが、少しはその力にならなければ、と心を新たにした思いだった。