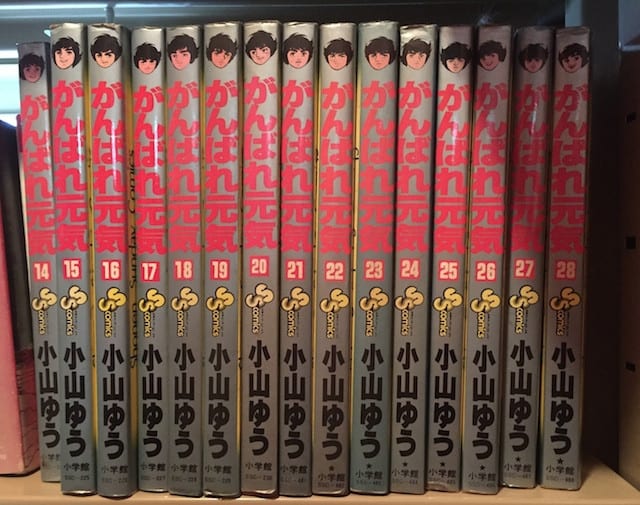長友を始め右サイドでも左サイドでも、問題なくプレイできる
サッカー選手もいるが、普通はどちらかのサイドを専門職として任される
高校時代、自分は最初、右サイドのバックスだった
それが、途中で左に変わるように言われた
変わった最初の日、まるで景色が変わってしまって戸惑った
右と左に変わっただけで、印象として全く違う
サッカー選手の見ている景色
後ろにいる選手が練習ゲームで前目のポジションを任された時
彼は広大な(?)スペースを眼の前にして「何をしたらいいのか!」
と一瞬迷うかもしれない
後ろの選手は前で起きていることを見ながら次の展開を予想して
ポジション取りなり体の向き、走るコースの選択を行う
パスのコースの限定がチームとしてあるとしても、基本的には
前で起こっていることのリアクション的な要素が多い
ところが最前線の選手はリアクションではなく、自分で何か道を
あるいは得点の可能性のある場所を確保するためにしかけなけれればならない
この仕掛は約束ごとのようになっている場合だけでなく、多くの場合個人の
ひらめきとか思いつきとか感性によって行われる
ここからが本日の問題点だが
日本人(選手)は前で起きていることへの対処はできるが
自ら創造的な(ある意味自分勝手な)行動はできないのではないか
とずっと思っていた
日本人は釜本以来、純然たる点取り屋は生まれていない
釜本も今のサッカーでプレイしていたらそれほど得点はできなかったかもしれないが
それでも、得点の入ることの少ないサッカーにおいては、点を取る事ができるというのは
天から与えられた才能(タレント)だと思える
この才能の持ち主は、大概の場合性格的にも変人が多い可能性がある
この点はとるが少し変てこな性格の選手という存在を
日本という国の好みは(空気は)あまり評価しないのではないかと思ってしまう
岡崎慎司選手はそのひたむきさ故に心動かされるが、日本の前目の選手のあるべき姿は
こうあるべきとパターン化されていないだろうか(最近は南野もその部類に入りそう)
その原型を作ったのは中山かもしれない
エネルギッシュに走り守りにも貢献する
そしてその姿を見て日本人は感動する
でも、スポーツは結果が全てだ
そんなにひたむきに走らなくても、結果だけは残す選手がいる
例え結果が残せなかったとしても、彼に任されたプレイ時間においては
完璧に近いことをしそうなことをするそのポジションの職人みたいな人がいる
イブラヒモビッチとかレヴァンドフスキがそうで、
特にイブラヒモビッチは一つ一つの得点がやたらと印象に残るものが多く
そのスーパーな得点に笑ってしまうしかないが、どうも性格的には
変わり者の印象を受ける
だが、そのへんてこな性格ゆえにあのスーパーなプレイができると考えることもできる
現在いろんな所でよく言われる多様性は、サッカーの場でも実現されるべきと思うが
消えてる時間の多そうな「点を取るだけが上手い選手」は日本社会は育てられないような
気がしている
これは社会に通じることで、平均的であること、みんなと同じであること、空気を読むことが
要求される社会は、天才が生まれても育てられないのではないか、、と思ってしまう