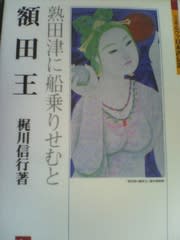「熟田津に 船乗りせむと 月待てば 潮も適ひぬ 今は漕ぎ出でな」
「茜草指す 紫野逝き 標野行き 野守は見ずや 君が袖振る」
「君待つと 吾が恋ひ居れば 我が屋戸の 簾動かし 秋の風吹く」(この著書での表記に基づく。この他にも万葉仮名で表記したものや、漢字を別のものに記した書も多い。)
万葉集には12首(一首は、上の句がどう読むか分からず、万葉仮名のまま)だけ掲載されている女流歌人、宮廷歌人の先駆者として名高い。
しかしこれらの歌、及び詞書き、さらに「日本書紀」での16文字でしか公の文書に記されていない「額田王」の実像に迫った作品。
この女性の生きていた時代は、古代日本の歴史の中でも激動の時代でもあった。七世紀。二人の女帝の時代、朝鮮出兵、白村江の敗北、天皇兄弟の争い、壬申の乱、遷都など、日本国内における天皇支配の確立に向けて大変化の時代であった。 その中にあって、天智(中大兄皇子)、天武天皇(大海人皇子)の両天皇の后として仕え、波瀾万丈の人生を送った女性。
資料がほとんどない中、それでいてこれまでさまざまに描かれてきた、女性の姿と時代背景に目を向けた労作。
実際に関わりのある土地に出むき、実地踏査した時写真や図版を掲載しているのが、興味深い。例えば、「熟田津」(にきたつ)。四国の松山市にある、伝承の地を訪ねて、「にきたつ」の語源・語意からその位置を特定する。
また、近江京とその荒廃、平城京など激しく動く歴史の中で生きる女性の姿を、実証的に浮かび上がらせている。
一般的には二番目の歌のように(あるいは有名な長歌のように)、二人の天皇の愛人として、きらびやかで奔放に生きた女性のように扱われる額田王の晩年の姿などにも迫っている。
「茜草指す 紫野逝き 標野行き 野守は見ずや 君が袖振る」
「君待つと 吾が恋ひ居れば 我が屋戸の 簾動かし 秋の風吹く」(この著書での表記に基づく。この他にも万葉仮名で表記したものや、漢字を別のものに記した書も多い。)
万葉集には12首(一首は、上の句がどう読むか分からず、万葉仮名のまま)だけ掲載されている女流歌人、宮廷歌人の先駆者として名高い。
しかしこれらの歌、及び詞書き、さらに「日本書紀」での16文字でしか公の文書に記されていない「額田王」の実像に迫った作品。
この女性の生きていた時代は、古代日本の歴史の中でも激動の時代でもあった。七世紀。二人の女帝の時代、朝鮮出兵、白村江の敗北、天皇兄弟の争い、壬申の乱、遷都など、日本国内における天皇支配の確立に向けて大変化の時代であった。 その中にあって、天智(中大兄皇子)、天武天皇(大海人皇子)の両天皇の后として仕え、波瀾万丈の人生を送った女性。
資料がほとんどない中、それでいてこれまでさまざまに描かれてきた、女性の姿と時代背景に目を向けた労作。
実際に関わりのある土地に出むき、実地踏査した時写真や図版を掲載しているのが、興味深い。例えば、「熟田津」(にきたつ)。四国の松山市にある、伝承の地を訪ねて、「にきたつ」の語源・語意からその位置を特定する。
また、近江京とその荒廃、平城京など激しく動く歴史の中で生きる女性の姿を、実証的に浮かび上がらせている。
一般的には二番目の歌のように(あるいは有名な長歌のように)、二人の天皇の愛人として、きらびやかで奔放に生きた女性のように扱われる額田王の晩年の姿などにも迫っている。