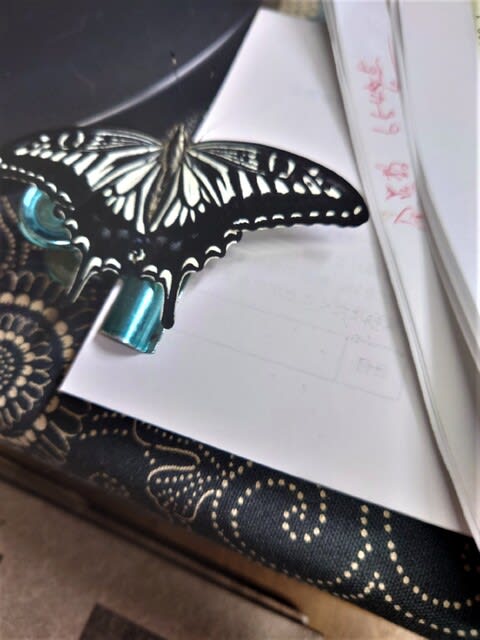▲ナンバンギセル(南蛮煙管)
<ハマウツボ科ナンバンギセル属>
長い柄の先に俯いた様に咲く花の独特な姿を煙管(キセル)に
見立てたのが花の名の由来。
古くは「おもいぐさ(思草)」の名でよばれた。
(ここは矢羽根芒(ヤバネススキ)の下に毎年生えるが、
今年はどうしたことか、こんなに暑い日が続いているのに、異常に花をつけている)
ミョウガや芒の根元に寄り添うように生える寄生植物で、
植物の根から栄養分を吸収している。
葉緑素が無く、全体的に赤紫色で、葉も鱗片状に退化していて、
高さ15~20センチの花茎(はなぐき)が茎のように見える。
※我が家のナミアゲハのイモちゃんズの一匹の蛹から羽化まで。
身体の色が変わってきていた。
お腹の当たりが黒くなってきていた。
初めにお尻をぶるんとふったので「これから始まるぞ!」と思った。
すぐにお腹が割れて、あつという間に頭が出てきた。
翅が出てきた。
身体全体が蛹の殻から抜けた。一瞬だった!
体勢を元に戻した。
翅が伸びてきた。
体液が飛び散って翅は濡れているようで窮屈そうなので、
籠から出してカーテンに留める。
翅を十分に伸ばせるように乾かしてやる。。
やがて、翅を広げると立派なナミアゲハ♂になった。
いつものように、カラスウリの生えている門扉に置いてやる。
元気に飛んで行った!
※雌雄の区別は、腹部先端の形からわかるが、
翅を開いた時、雄(♂)は全体に黒で、
雌(♀)は後翅に赤色と青色がある。
<日記>
今度こそ、羽化の瞬間を見てやろうと思っていた。
あっ”という間の出来事でした。
蛹の色が緑から褐色(胸は黒色に・)に変わってきたら、
要注意して観察しようと思っていた。
前回は失敗して、気が付くと羽化が終わっていました。
今回は動画がよかったのかもしれないが・・
いまいち張り付け方が解らないので、
ワンカットずつのシーンになりました。
蛹が、ぶるっ!と武者震いしたと思ったら、
羽化が始まりました。
もう、あっという間に殻から出てきます。
誕生の見事さ”を見せてもらった感じでした。
やはり、育てるのも楽しいが、この羽化のシーンは
ご褒美のようなものだから、命の誕生”を見ましょう!
そして、元気にはばたたせて送りたいものです。
画像は、はっか(薄荷)の花
《俳句鑑賞は夏の季語蝸牛(かたつむり)》
でで虫・でんでん虫とも使う。

かたつむりのかたるしすはしかしかんたん 山本 敏倖