
▲ロウバイ(蝋梅)
<ロウバイ科ロウバイ属>
落葉低木
葉が出る前に香りのよい透き通ったような黄色の花をつける。
中途半端だけれど・・
只今、静養中です。
また、遊んで下さい。

病棟の窓から
退院しました。
少しづつ、アツプしていきたいです。

▲ロウバイ(蝋梅)
<ロウバイ科ロウバイ属>
落葉低木
葉が出る前に香りのよい透き通ったような黄色の花をつける。
中途半端だけれど・・
只今、静養中です。
また、遊んで下さい。

病棟の窓から
退院しました。
少しづつ、アツプしていきたいです。

▲シャクナゲモドキ(石楠花擬)または、ロードレイア
<マンサク科ロードレイア属>
シャクナゲモドキ(ロードレイア)は、マンサク科の常緑樹。
葉は長さ5センチほどの葉柄を持ち、
長さ11センチ、幅3~6センチほどの卵状楕円形で、枝に互生する。
革質で厚みがあり、濃緑色で表面に光沢がある。
シャクナゲモドキは中国南部から西マレーシアに分布する植物で、
実はマンサクの仲間でもあり、紅色の花を咲かせる。

▲トチノキ(栃木)の冬芽
<トチノキ科トチノキ属>
樹脂が多くよく粘る。
頂芽が大きい。水あめ状の樹脂を分泌しべとつく。
廻りにトチノキの幼木が出ていた。
黒くなった実の中の果肉から幼木が出ていた。
▲ネジキ(捻木)の冬芽
<ツツジ科ネジキ属>
たぶん、伐採された後から元気よく出ていた赤い枝のネジキです。
落葉低木。
幹がねじれていることから、ネジキと呼ばれる。
ネジキの実
花は、白く釣り下がる。
その花後の実です。
赤いネジキの新しい枝にまゆのような???
<日記>
多摩湖の鳥と冬芽観察と言う事で出かけたが、
鳥は遠すぎてよく見えません。
双眼鏡も借りてみましたし、説明して下さる観察員の方のお話はよく解るのですが、
なにしろ、8倍の素晴らしい双眼鏡で見ても遠いので、
結局、見につかなかったのが残念です。
(ああ‥覚えられなかったってことですが)
でも、近場で出会ったら、思い出すこともあるだろうと思いました♪
本当は、オオバンもクイナもカワウもアオサギも見えました。
カンムリカイツブリ、ホウジロガモ、もいました。
遠目ではしろっぽくみえました。?
いいお天気で遠くに富士山が見えました。
遠いけど、ケヤキの古木にコゲラが数匹いました。
私のカメラはここまでです。
背中の黒白模様が特徴です。コゲラ
ツグミに会いました。なかなか逃げません。
どちらかと言えば、警戒心のない鳥だと思いました。
カラスに追いかけられているオオワシも見ました。
写真はありません~。
たくさんの資料もいただいて、次につなげたいです。
《俳句鑑賞は春の季語蕗の薹(ふきのとう)》
少しづつ違ってどれも蕗の薹 松村 幸一

▲キハギ(木萩)
<マメ科ハギ属>
山野に生える落葉低木。
枝に微毛が密生する。葉は3出複葉、小葉は長さ2~4センチの長卵形
または、長楕円形。
葉のわきから総状花序をだし、長さ約1センチの蝶形花をつける。
花は淡紫白色で、黄色を帯びる。

豆果は長さ1~1,5センチの扁平な長楕円形で先は急に尖りまばらに伏毛が
あるそうだが、私はまだ、見た事が無い。
▲ヤハズアジサイ(矢筈紫陽花)
<アジサイ科アジサイ属>
深山に生える落葉低木。高さは1~2,5メートル。
若枝には剛毛が密生する。葉は長い柄があり、対生し長さ12~23センチの広楕円形
で両面とも有毛。上半部は羽状に浅く裂け、縁にはあらく鋭い鋸歯がある。
散房花序をだし、小形の両性花多数と、長い柄のある直径1,5~2センチの
白い装飾花をつける。
両性花には花弁と萼片が4~5個、雄しべが8~10個、
花柱が2個ある。
(葉先が初め2つに裂けることからヤハズ(矢筈)の名がついた。)
<日記>
午前中はO学園まで。終わってから、
いつもの牧野庭園に寄ってみるが人は結構多い。
花は少ない。午後から耳鳴り?がして煩いので、
病院まで。流行っている病院なので1時間待ちだ。
もうここでも、QRコードであと何人と解るので、
4~5人前になるまで買い物して、
夕飯が遅れると面倒なので書き置きして行く。
「魚を焼いて、お惣菜は小鉢に入れて並べて置いて」と。
この頃は、超手抜きご飯です。
医者は血液の流れがよくなる薬を出してくれた。
まだ、シャーツと音はやまないが、
まぁ気にするほどでもなくブログが書けるから大丈夫。
※昆虫・その他コーナー
食草はカラムシで、ちょっと悪戯すると大きく葉を揺らすのが面白い。
フクラスズメ(まだ小さかったがしっかり葉を揺すって威嚇された)
シデムシ
森の掃除屋さんエンマムシかな?
ちょっと遠くて高いところのあった、タラヨウの木にモリアオガエルの卵塊
沼まで落ちるのが大変そうな場所でした。
《俳句鑑賞は、夏の季語立夏(りっか)》
夏たつ・夏来る(なつきたる)・夏に入る(なつにいる)
今朝の夏(けさのなつ)などと使う。
画像はひまわり
炭酸ののしゅわしゅわ笑ふ夏来る 田口 雄作

▲アケボノアセビ(曙馬酔木)
<ツツジ科アセビ属>
花が紅色の馬酔木の品種で、濃紅色のものはベニバナアセビと言うので、
これはベニバナアセビだろう。

▲アセビ(馬酔木)
<ツツジ科アセビ属>
常緑低木~小高木。
葉は互生し、厚い革質。
枝先に円錐花序を出し、白い花が多数垂れ下がる。
花冠はつぼ型で先は浅く5裂する。
有毒植物。
▲サンシュユ(山茱萸)
<ミズキ科ミズキ属>
落葉小高木~高木
樹皮は褐色で鱗片状に剥がれる。
まだ、咲いたばかり。
黄色の小さな花を20~30個密に開く。
花弁と雄しべは4個。
<日記>
インプラントなので、
3か月に一回、クリーニングに行く。
そこで、ここから「一駅散歩」を主人と始めたのだが、
始めはよかったが、だんだん遠くなると
調べて行ってもなかなかうまく行かない時もある。
秋津から一駅歩いて柳瀬川に沿って歩こうと思っていたが、
川のそばに人が歩ける道が無い。
川の向こうには林が続いているのに・・
そこに行けない。
仕方ないので、買ってきたお稲荷さんを神社で食べる。
航空公園に行こうかと言う事になり、
一駅電車に乗って広い航空公園の日本庭園やロウバイ園
等を見て帰宅した。
航空公園
※クモハンドブックは、私には役に立たない~🕷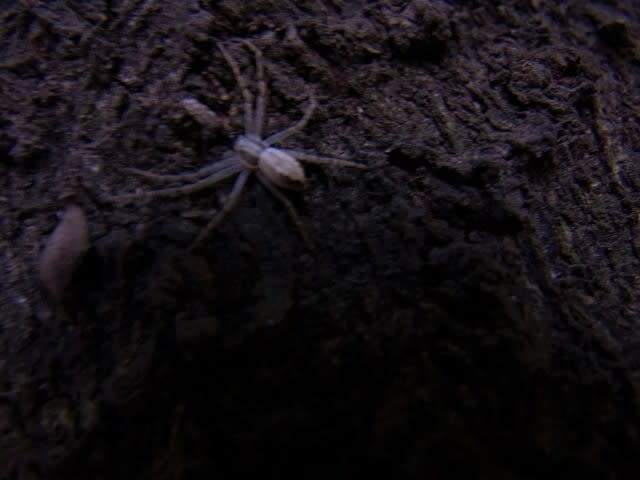
※himesijimiさ~ん
ボケてて悪いんだけど‥何蜘蛛さん?
時間のある時にお願い~
※himesijimiさん、蜘蛛のお名前ありがとう。
アサヒエビグモ♀ですね。
いつも、ありがとう~(=^・^=)
《俳句鑑賞は春の季語雛(ひな)》
雛(ひいな)雛祭り・桃の節句・桃の日
(雛飾・雛人形・雛菓子・吊し雛・折雛等々)

雛よりもさびしき顔といわれけり 大木 あまり
白髪を許されずをる雛かな 大木 あまり
見つめあふことかなはざる雛かな 大木 あまり

▲カワズサクラ(河津桜)
<バラ科サクラ属>
カンヒザクラ系の園芸種。
葉は互生する単葉で楕円形~楕円状卵形で葉の先は尖っている。
蕾は濃い紅紫色。
花は葉腋に出る散房花序に4~5個つき淡い紅紫色の5弁花で、径3センチほど。

花の咲く時期が早い。
早いものでは1月下旬から咲いている。

▲スノウドロップ(待雪草)
<ヒガンバナ科マツユキソウ属>
東ヨーロッパ原産の球根の多年草。
早春を彩る花として好まれる。

内花被片には特徴的な緑の斑蛾が入る。
雄しべは6個、葯は黄色で、雌しべは1個。
花は夜には閉じて蕾のような状態になり、日が差し始めると
開花する。
今日は置いてきぼりなので、
事務所から通りを見ながら帰りを待っまり。
<日記>
昨日はSさんのコンサートで
日本橋まで出かけた。
いつもの花屋で可愛い感じにアレンジしてもらって
花束を持参する。
彼女は、一番初めに薄黄色のドレスを着て「春」を歌った。
歳は重ねても、愛らしさには変わりがない。
懐かしい青春時代を思い出す。
朝まで喋っていたっけね。
帰りに一言声がかけられてよかった。
「今半」で少し並んですき焼き弁当と、
コロッケを買って帰る。
《俳句鑑賞は春の季語桜(さくら)》

画像は関係ないけれど、朝のまりのお散歩途中でモーニング。
桜・染井吉野・朝桜・夕桜・夜桜・老桜(おいざくら)
などと使う。
さくら見にゆこと連れ立ち女の子 西村 和子

▲ロドレイア(石楠花擬)
<マンサク科ロドレイア属>
またはシャクナゲモドキと言う。
常緑樹。
葉は革質で厚みがあり、濃い緑色で光沢がある。
シャクナゲに似た葉で葉裏は白っぽい。
1~1,5センチほどの花柄の先に5個の花が集まり1個の花のように見える
総状花序をだす。
花色は濃桃色、花径は3~3,5センチほどで、花弁のように見えるのは
総苞片。


▲ストレチア(極楽鳥花)
〈ゴクラクチョウカ科ゴクラクチョウカ属>
別名、オーガスタ
バナナの葉っぱに似た観葉植物として鉢植えなどにもする。
極楽鳥のような不思議な花を咲かせ、開花期間が長い。
学名のストレチアはイギリスのガーデン拡大に貢献した、
シュトレーリッツ家にちなんでつけられた。
和名の極楽鳥花は、美しい飾り羽を持つ極楽鳥の雄の姿に例えて名づけられた。
<日記>
予定の時間を間違えてしまったので、
(この頃よくあるミスだ)
30分体操の方に出かけて、買い物をして帰る。
帰宅したら「虫は花のアクセサリー」と言う素敵な
コピーの可愛い絵の招待状が届いていた。
ゆみこさんの絵の展覧会だ。
場所も我が家からお散歩で歩いて行けるコースにある。
3月になったら、まりも連れて(いけるかな?)
見に行くのが楽しみです。
《俳句鑑賞は春愁で春の季語なのだけれど髪が使われてる句を選んでみた>

画像はローズマリー
髪おほければ春愁の深きかな 三橋 鷹女
罌粟ひらく髪の先まで寂しきとき 橋本 多佳子

モクレイシ(木茘枝)
<ニシキギ科モクレイシ属>
海岸近くの林に生える常緑小高木。
葉は対生し、長さ5~9センチの楕円形または卵形で革質。
葉脈に直径約5ミリの緑白色の花を開く。

雌雄異株。
花弁は5個でほぼ円形。雄蕊は5個で、雌花は小さい。
雌しべは1個で、雄花では小さい。
蒴果は今度是非、見てみたいものです。
果皮は革質で熟すと基部から2裂する。
中に大形の赤い種子が1個ある。
ヒサカキ
ヒサカキ(姫榊)
<ツバキ科ヒサカキ科>
常緑小高木。
樹皮は灰褐色。葉脈に直径5~6ミリの白い花を束生する。
雌雄異株。
花弁は5個で雄花には雄しべが10~15個、雌花には雌しべが1個ある。
果実は直径4~5ミリの球形で黒紫色に熟す。

友人はこの花の匂いをシナチクと言い、
ある人は東京ガスの匂いと言う。
ムサシアブミの新芽
ムサシアブミ(武蔵鐙)
<サトイモ科テンナンショウ属>
出たての新芽が面白い。


葉は2枚、小葉は3枚で裏面は白い。
ムサシアブミの実
今日はここまで♪

シデコブシ(四手辛夷)
<モクレン科モクレン属>
別名ヒメコブシ
落葉低木。
白色またはやや淡紅色の芳香のある花が咲く。
花の形がコブシに似て、多数の花被片が「しで」のように見える事から。
花弁と萼片は区別しにくい。
どちらも長さ約4センチの狭倒披針形で、合わせて12~18個ある。

我が家の近くの公園に咲いている。
下はロードレイアまたはシャクナゲモドキ(擬石楠花)
ロードレイア・ヘンリー(または、シャクナゲモドキ(擬石楠花))
<マンサク科ロードレイア属>
毎年、我が家の近くのお散歩コースに咲く。
いつも、シャクナゲモドキ(擬石楠花)では覚えているのだが、
ロードレイア・ヘンリーの名前は忘れる。
常緑樹で葉は長さ5センチ程度の卵状楕円形で枝に互生する。
1~1,5センチ程度の花柄の先に5個の花が集まり1個の花のように見える
総状花序を出す。

花色は濃赤色。
花径は3~3,5センチほどで、花弁のように見えるのは
総額片である。
葉裏は白い。
休憩
ユキヤナギ(雪柳)
<バラ科シモツケ属>
本来なら、枝垂れるところが雪柳らしいのだが、
公園でも都会の庭でも、なかなか枝垂れるまで伸ばしてもらえず、
短い花枝で精一杯咲いている。
川岸や岩場に生えているのは、
背は低いがユキヤナギの本来の姿が見られる。
庭や公園によく植えられています。
川沿いに自生するユキヤナギにはここ暫くお目にかかっていない。
幼い頃は、よくこの枝垂れた枝を髪にピンでとめて
ヘアーバンドにして遊んだものです。
俳句は季語おでんで
飛行機雲消えておでんの卵浮く れんげ
明日、お天気の都合で栃木の星野の節分草と、花の絵の郷に
早春の花に会いに行く予定 だったが、
お天気で、二転三転している状況なので、急遽本日、
これから、おにぎり握って、出かけることにします。(#^.^#)

ミモザ(MIMOSA)
<マメ科アカシア属>
午後からお散歩に出たら、ミモザが咲きだしていた。
朝は冷え込んでいたのに昼過ぎには20度まで上がったらしい。
花は黄色で球状に集まって咲く。
常緑高木で主にオーストリアに産し、観賞用に栽培される。
洋花なのだが、春を代表するような感じの花なので、
春にはよく取り上げている。

フランスでミモザの名で親しまれている。
銀葉アカシアは、名前の通り銀白色を帯びた葉を持ち公園樹に利用される。
ちょっとおしゃれで、春らしい花です。
下はオカメザクラ(阿亀桜)
公園に寄ったら、オカメザクラが咲いていた。
オカメザクラ(阿亀桜)
<バラ科サクラ属>
カンヒザクラとマメザクラをイギリスで交配したものを、
逆輸入したもの。
花色が濃く、早咲きで樹形が大きくならないことから、
人通りの多い場所の街路樹や狭い庭のシンボルツリーとして使われる。
花は小輪で、濃いピンク色であり、下を向いて咲く。
休憩
アズマイチゲ(東一華)
<キンポウゲ科イチリンソウ属>
まだ、咲いたばかりのアズマイチゲ。
★明日、ゆつくり見にいくので今日は一目だけにします(#^.^#)
俳句は季語春愁(しゅんしゅう)
春愁(はるうれい)・春憂うなどとも使う。
春愁の煙草に点す火やくれなゐ 鈴木 しづ子
春愁等間隔の水の音 岡田 恵子
恵子様、句集「ハーブ系」有難うございました。

マンサク(満作)
<マンサク科マンサク属>
早春、山では一番早く花を咲かせる。
春を告げる木。
葉に先立つて黄色の花が咲く。
花弁は4個あり、長さ1~1,5センチの線形。
雄しべは4個で短く、内側に4個の仮雄しべがある。
葯は暗赤色。
雌しべ1個で、花柱は2つに分かれる。
萼は4裂する。
萼片は長さ3ミリの楕円形で反り返り、内側は暗紫色で、外側には褐色の短毛
が密生する。

和名は、黄色い花が枝いっぱいに咲くので、”豊年満作”から来たという説と、
”まず咲く”がなまったという説がある。
下は白梅
ハクバイ(白梅)
<バラ科サクラ属>
何とも・面倒くさい!
実は、図鑑で白梅などと調べても出てこないです。
うめで調べてね(#^.^#)
梅は、薔薇科で桜属なの。

庭や畑で栽培されるが、野生化しているものもある。
落葉小高木。

休憩
コウバイ(紅梅)
★昆虫コーナーと言っても今の時期、
なかなか虫には出会えません。
昨日は雪の中、お買い物に出たら、
エノキの枝に白いものが・・いえまだ雪は積もっておりませんでした。
ちょっともう、抜け殻だからいいかと、
枝付きで戴いてきて、家で写しました。
勿論、アカボシゴマダラの抜け殻ですね。
もうひとつ、以前に撮ったもので(やはり冬)
これも何かの抜け殻だけれど・・
解りません( ;∀;)
ご存じの方はお知らせ頂ければ幸いです ^^) _旦~~

ちょっと、ピンボケですが・
何の抜け殻??(#^.^#)
「折々の言葉」から
「朝日歌壇」より小1のやまぞえそうすけ君の歌
ふうせんが9つとんでいきました
ひきざんはいつもちょっとかなしい
ふ~~ん!と思ったわたし(#^.^#)