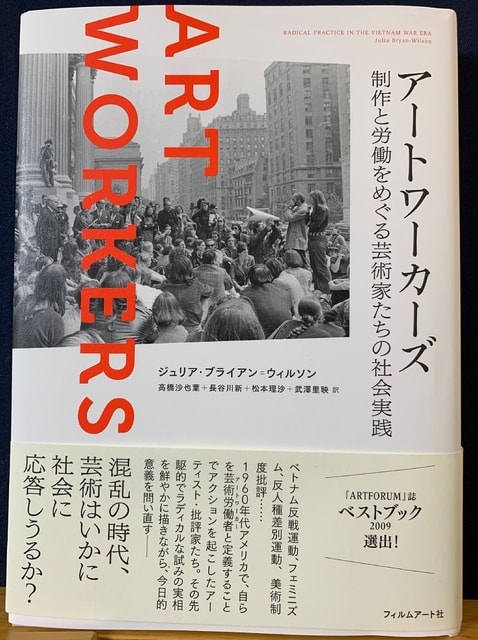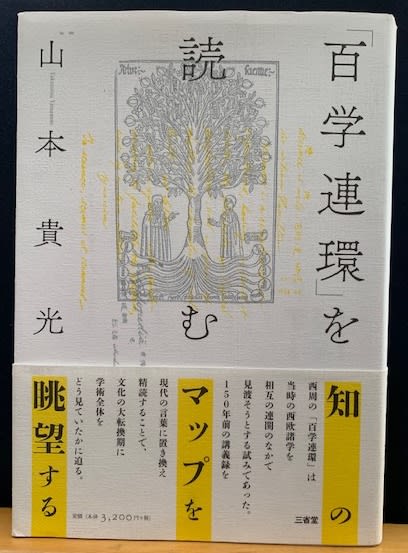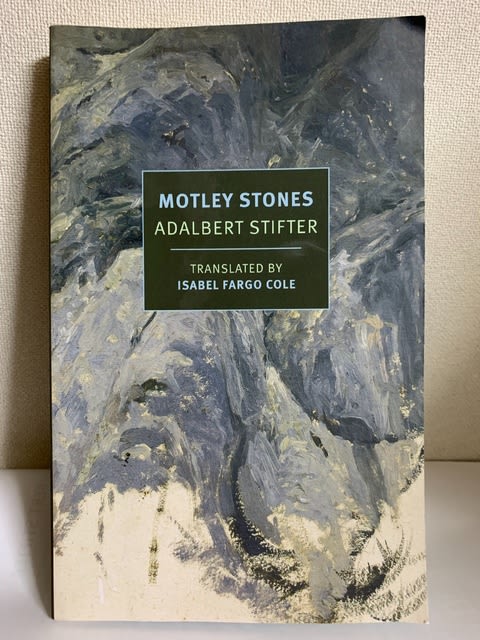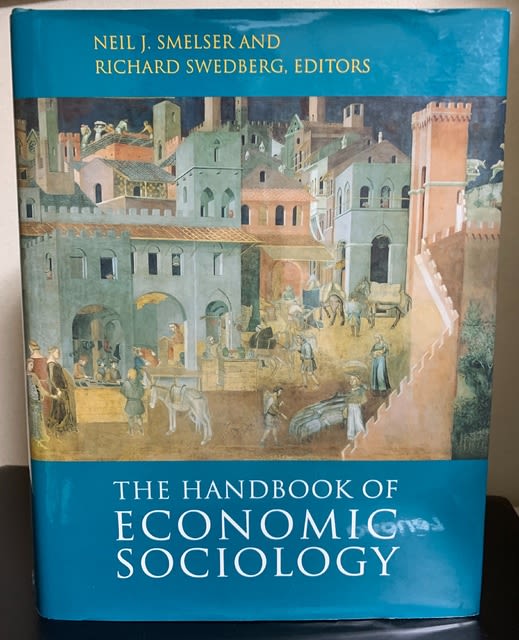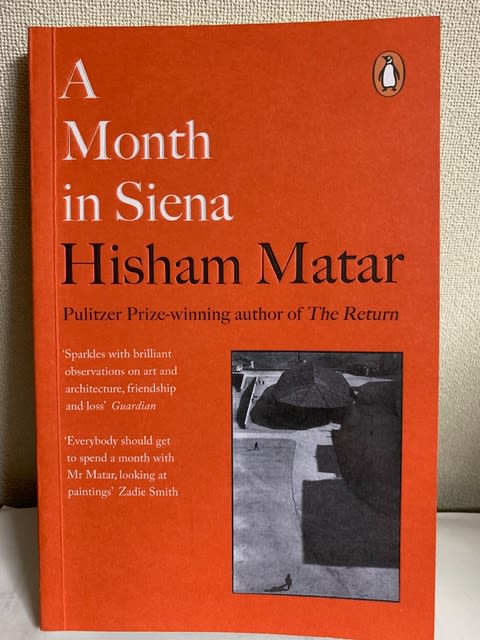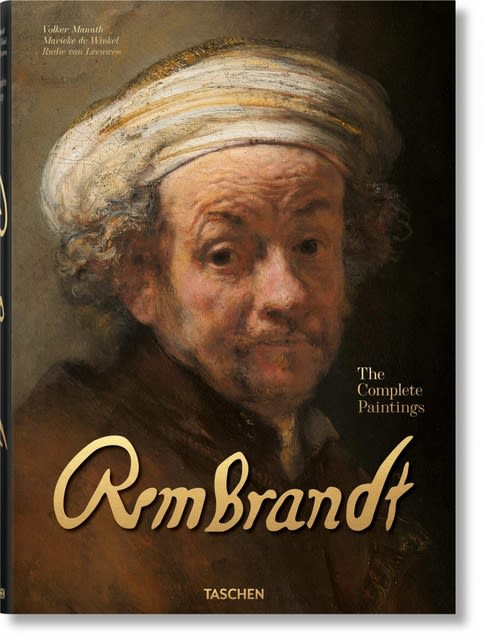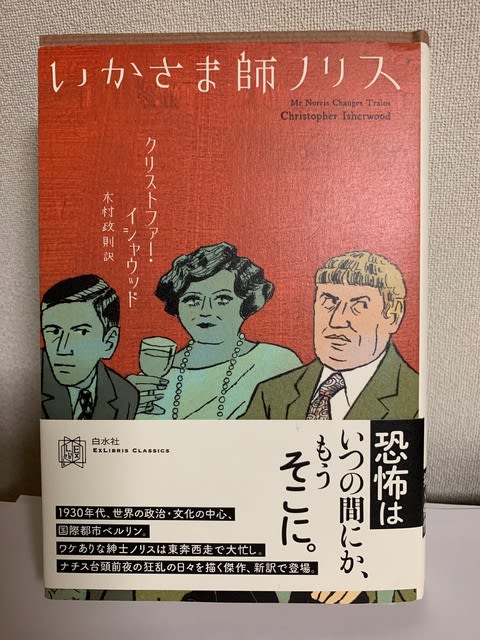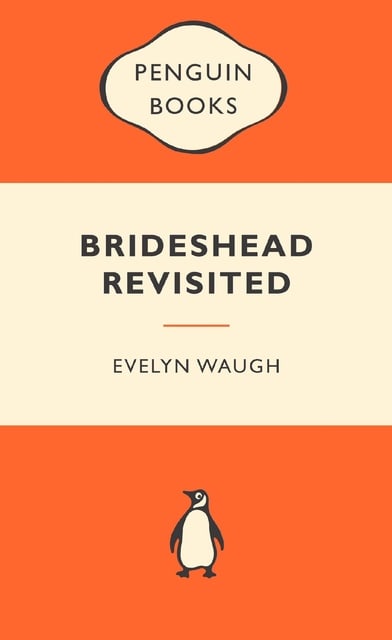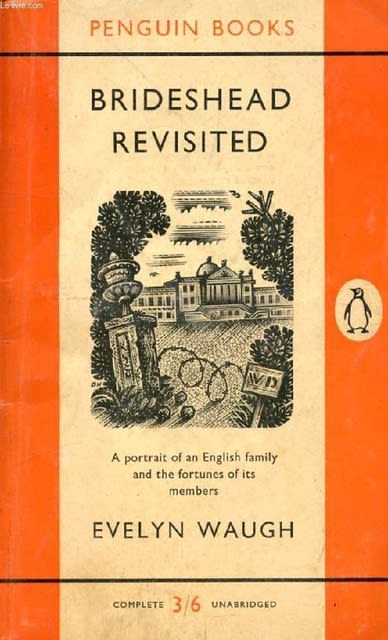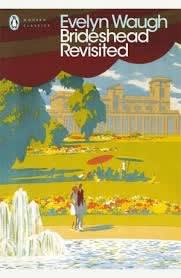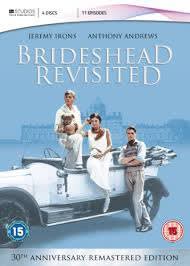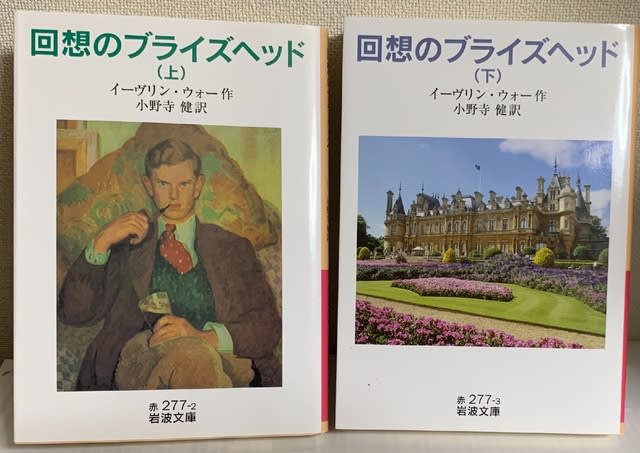A waiter in Patis
Edward Chisholm, A Waiter in Paris: Adventures in the Dark Heart of the City, London:Monoray, 2022, cover
現代の世界を見渡して、パリほど華やかさや活気で溢れた都市は少ない。世界中から観光客ばかりでなく、この都市で働きたいとやってくる人たちも多い。
今回は、エドワード・チザム Edward・Chisholmなるイギリス人の若者が、ロンドンで就職できず、将来が見通せないままに、失意の身でパリのレストランでウエイターとして働くことを目指し、信じがたい環境の下で働き、記した体験記を紹介したい。本書は2022年に刊行以来、大きな注目を集め、ルポルタージュ文学の傑作とされたジョージ・オーウエル『パリ・ロンドン放浪記』(原著1933年、岩波文庫、1989年)*に匹敵する現代版とも言われ、ベストセラーとなった。
waitingの語源(本書巻頭)
waiting noun
BrE/weiting/
1. the factor of staying where you are
or delaying doing something until
somebody/something comes or
something happens
2. the fact of working as a waiter or waitress
Oxford Advanced Learner’s Dictionary
*ジョージ・オーウェルGeorge Orwell(1903―50)は、イートン校卒業後、インド帝国の警察官としてビルマに勤務した後、は1927年から3年にわたって自らに窮乏生活を課す。その体験をもとにパリ貧民街のさまざまな人間模様やロンドンの浮浪者の世界を描いた。人間らしさとは何かを生涯問いつづけた作家の出発にふさわしいルポルタージュ文学の傑作とされる。
労働の世界の底辺で
レストランという、人々にエンターテイメントを提供する<労働の世界>で働くことが、いかなるものかを考えてみたい。世の中に大企業などの組織で働く人たちの世界を描いたルポルタージュ・ドキュメント*は多いが、レストランという表面的には華やかな働き場所に覆い隠された非人間的な実態を描いた作品はさほど多くはない。
*例を挙げれば、上掲のジョージ・オーウエル『パリ・ロンドン放浪記』に加え、日本では鎌田慧『自動車絶望工場:ある季節工の日記』(講談社文庫、1974年)などが思い浮かぶ。
筆者チザムは、イギリスで高等教育(London School of Orienta and African Studies)
の過程を修了した後、ロンドンで職探しをしたが、適職に就けず困窮し、再起して自らの夢を実現しようと、2012年、パリへ赴いた。職探しをするが、良い職業に出会えない。仕方なく、イギリスから見ると、華やかさなどで、しばしばファンタジー化されていたパリの有名レストラン Le Bistrot de la Saine (仮名)に職を得る。しかし、そこはかねて思い描いた光の当たる華やかな場所とは程遠い、厳しくも冷酷で非人間的な階層社会であった。
フランスで働き暮らす際の気が狂いそうな官僚主義、例えば社会保障番号を取得することの煩瑣な手続きや、賃貸住宅に入居する場合、所有者にle dossier (家主の証言を含む賃貸履歴のフォルダー)を提示することの不合理など、パリで働くことに関わる多くの煩雑さが描かれる。
現在のパリは、もはやピカソやヘニングウエイの時代とは大きく異なったものになっている。ブールヴァルやきれいな公園はガイドブック上のものだ。この都市に住んでみると、街路や住居がゴミその他で、ひどく汚れていることにも気づく。歩道にダンボールやごみが散乱した街だ。
テーブルと椅子、さまざまな客たち
着飾った客たちがさんざめくパリのレストランのテーブルは、食器の触れ合う音、人々の話し声、ワインの香りなどで満ちたいわば表舞台、劇場である。そこは、さまざまな国から集まる、階層も異なる客たちと、ウエイター、シェフたちとの間で虚々実々の会話が交わされる舞台なのだ。
白いエプロンなど、ユニフォームを身につけたウエイターは、しばしば 20−30代の若者には憧れの職業といわれる。
しかし、チザムが割り当てられた仕事は、調理場と客席まで料理の皿を運ぶ runnerと呼ばれる文字通り最低の内容だった。ここでの労働に支払われる賃金はあまりに低いため、彼らは客からのティップが期待できるウエイターを目指し、日々、虚々実々の戦いをしている。着飾った客たちが賑やかに食事を楽しむテーブルは、ウエイターにとっても客層の嗜好に合わせ、<外交的な>会話を楽しむ場のように見えるが、内実は人間の醜さ、利己的野心など、さまざまな欲望が渦巻く場所でもある。
いかにすれば、客たちに楽しい一時を過ごしたと思わせるか。適切な話題、間の取り方など、応対の仕方にも多大な蓄積が必要となる。ティップについても、例えば、有名人は日頃、タダで欲しいものが手に入ることもあって概してケチだ。アラブ人は小銭を持っていないことが多いなど・・・・・・。
Q:一般にフランス人はほどほどにしか払わないが、最も高いティップを払う客層はどこの国から来た人か(Q1)。ヨーロッパの客の中で、少しのティップしかくれないのは?(Q2) 外貨の交換レートを間違え、時に高いティップを払っているのは?(Q3)。[答: Q1. 日本人、ブラジル人、Q2, フランス人、オランダ人、Q3. アメリカ人]
その日暮しの日々
反面、料理を作るキッチンはさまざまな食材、調理の匂いに溢れ、コック長を頂点として幾重にもなる階層で構成される働き手がざわめく場所であった
レストランの裏側に当たる調理場は、別の世界だ。想像とはおよそ異なる厳しい労働環境で、賃金は最低であり、家賃や高い生活費と不安が常に重なり合い、日々再計算しながら働いているような状況だった。厳しさに耐えかね、仕事を辞める人も多い傍ら、チザムは過酷な重圧に耐えながらも、パリのサービス業の一端で当初の目的を成し遂げようとする。
夢を叶えたいとパリでやっと辿り着いた賃金は、月額税込みで€1086.12だった。1日14時間のシフト、週6日勤務だった。職場での食べ物といえば古くなったロールパンかディナーの残り物。彼のわずかな慰めは、タバコだけだった。
テーブルでは顧客からの屈辱、とりわけ何度でも突き返してくるセレブの客、嫌なら辞めろとばかり、ひどい対応をする使用者、騙しあい信用できない同僚など、想像し難い日々が続く。一見、綺麗に整頓、セットされたレストランのように見えても、内実は恐ろしく汚れたキッチン、掃除したことのないようなカーペットなど、全てに耐えねばならなかった。
ウエイターとして過ごした間に、チザムは得難い教訓も得る。フランス固有のエティケット、人々の個性の相違、世界でも有数の生活費が高い都市て生き抜くさまざまな術を学ぶ。
我が物顔に振る舞う客たち、横暴な雇い主, 信用できない同僚・・・・・。実際、彼の周りのウエイターと言ったらナルシスト、麻薬の売り手、滞在許可証を持っていない移民、元外国人部隊兵士、脱走兵などまで混じっていた。30歳代の若者たちが多く働く場所ではあるが、人生について展望を持たない者には出口の見えない地下の底にいるような感じさえ与える。しかし、そこでも人生で得難い友情を感じた同僚もいた。
本書は、読者としてチザムの経験した苦難に、憐憫の情を共有させることとは別として、ただ若く高等教育を受けていても、それだけでは現代の厳しい世界を生き抜いてゆくことは非常に難しいことを示唆している。
パリのレストラン・ウエイターのような世界がどの程度存在し、執拗に存続しているのか、その仕組みは分からないことが多い。しかし、20ー30代の若者にとって、秩序のようなものがなく、希望を抱かせないような仕事の雰囲気が良く伝わってくる。ともすれば、数字ばかりに目を奪われる労働経済の分析では、到底分からない現実がそこにある。
チザムは、結局7年近くパリに住み、ウエイター、バーの下働き、美術館の警備など、さまざまな劣悪、低賃金、そして働き続ける意義を感じさせないような仕事で働いた。それらが無益な経験ばかりであったわけではない。他では到底得難いものも学んだ。そして、今はイギリスに戻り、文筆業として生きる道を模索し始めたようだ。
本書の成功で、彼はその一歩を踏み出したといえる。
パリという現代資本主義社会の只中にある大都市で、30代の若者が将来のキャリアを模索しながら、レストランという「食物連鎖の末端」と言われる場で働くということが、いかなることを意味するか、多くの暗闇と僅かな光がそこにある。
A waiter in Paris
Edward Chisholm, A Waiter in Paris: Adventures in the Dark Heart of the City, London:Monoray, 2022, pp.370
Contents
INTRODUCTION
AMUSE-BOUCHE
L’APERITIF
LA SOUPE
L’ANTREE
LE PLAT PRINCIPAL
LE FROMAGE
LE DESSERT
LE DIGESTIF
ACKNOWLEDGEMENTS