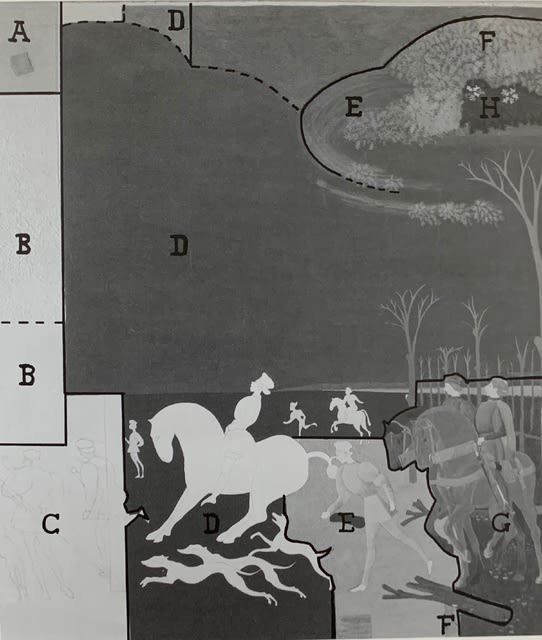バイデン大統領の高齢不安の問題が、アメリカ、そして世界を駆け巡っている。本ブログで、2024年はアメリカが動乱状態になる可能性が高いことを記したが、その当時はトランプ候補が大統領に選ばれない場合が、動乱発生の最大のリスクであると考えられていた*。その可能性は今になっても払拭されずに存続している。
*7月13日にはトランプ候補暗殺未遂事件も勃発。本記事執筆時点では詳細不明。
他方、バイデン大統領の高齢に関わる不安という問題が急速に浮上している。バイデン大統領が再選されなかったり、トランプ大統領が復帰再選ということになれば、今度は反トランプ側の圧力が過熱することが懸念される。
いづれにせよ、代わりの候補の浮上の可能性を含め、バイデン、トランプ候補のいづれが当選しても、アメリカは大きな混乱、分裂の危機に直面する可能性は高まるばかりだ。2024年から2025年にかけて、アメリカの動乱突入、社会的分断の進行は、ほとんど不可避だろう。
他方、前回記事の流れで、画家ジョン・サージェントの作品カタログを見ていると、思いがけず脳裏に浮かんできたことがあった。アメリカ合衆国政治史上、最も若くして大統領の座に着いた人物の肖像画を制作した画家が、サージェントだったという事実である。
Q:さて、この若い大統領とは誰でしょう。アメリカ政治史に詳しい人でも、意外と答えられない。
大統領の高齢化
話が前後するが、2017年1月20日をもってドナルド・ジョン・トランプ氏は、第45代アメリカ合衆国大統領に就任した。就任時の年齢は70歳220日で、第40代大統領ロナルド・レーガンの69歳349日を上回り、歴代最高齢の大統領となった。後に現在大統領の地位にあるジョン・バイデン氏によりこの記録は更新された。
話を戻すと、今日の段階でアメリカ合衆国の歴史で、最も若くして大統領の座に就いたのは、セオドア・ローズベルト・ジュニア(Theodore Roosevelt Jr, 1858-1919)氏で、42歳10ヶ月でアメリカ合衆国第26代大統領となった(ルーズヴェルト、ルーズベルトとも表記)。愛称テディ(Teddy)、イニシャルT.R.でも知られる。N.B.
==========
N.B.
ここでは同大統領のことを詳しく記すことは目的ではないが、政治家としての業績、その過程での軍人、作家、探検家、自然主義者など、多彩な活動を精力的に行い、1901年、ウイリアム・マッキンリー大統領が暗殺された後、米国史上最年少の42歳10ヶ月で大統領に就任。日露戦争の停戦を仲介、ノーベル平和賞を授与され、ノーベル賞を受賞した初のアメリカ人となった。政治的には共和党だが、後に短命に終わった進歩党へ傾斜した。アメリカ政治史上、大変優れた大統領としてフランクリン・ローズヴェルト大統領(FDR)と並び、10指の中にはほとんど常に数えられるひとりである。
ちなみに、第32代大統領フランクリン・ローズヴェルト(FDR)は、5従弟(12親等)に当たり、フランクリンの妻エレノアは姪に当たる。
========
前置きが長くなってしまったが、今日ホワイト・ハウスに残るセオドア・ローズベルト大統領の公式肖像画を制作したのは、ジョン・シンガー・サージェントであった。実はサージェントより前に大統領夫妻の肖像画を描いた画家がいたが、大統領自身が気に入らず、最終的に破棄されてしまったといわれる。
その後、大統領が期待した画家として登場したのが、サージェントであった。アメリカ生まれの医師の息子としてイタリア、フィレンツェに生まれたが、ロンドンを主な活動の舞台としていたサージェントは、アメリカ国籍を取得し、1905年頃からほぼ毎年アメリカに戻ることがあった。1903年2月、ホワイト・ハウスのゲストとして1週間滞在することが決まった。この間に大統領の肖像画制作に当たろうという計画だった。
二人が考えた大統領の肖像画のイメージはそれぞれ異なり、大統領側の多忙もあって制作途上はかなりギクシャクしたようだ。大統領がポーズをとった場所も、2階へ上がる階段の踊り場であった。多忙な大統領は、週数回昼食後の30分程度しか、落ち着いて画家の前に立つことなく、丁寧な仕事で知られるサージェントは大変不満だったようだ。しかし、大統領は作品を大変気に入り、終生、大事に扱ってきた。その結果、第1級のアングロ・アメリカンの肖像画として評価され、連邦政府の決定で、公式のホワイトハウスの肖像画となった。
作品は正確に大統領の風格、目の輝き、エネルギッシュな性格を捉えている。屈指の肖像画家としての地位を確保していたサージェントの的確な人物像の把握が素晴らしい。ブログ筆者もかつてホワイトハウス見学の際、作品に接する機会があったが、1週間という短期間によくこれだけの作品に仕上げたものだと感銘した。同時期の肖像写真と比較しても、その的確な人物イメージの把握が素晴らしい。
作品は見事に大統領の風格、目の輝き、エネルギッシュな性格を捉えていると思われる。屈指の肖像画家としての地位を確保していたサージェントの的確な人物像の把握が素晴らしい。実際に作品に接する機会を得て、1週間という短期間によくこれだけの作品に仕上げたものだと感嘆した。同時期の肖像写真と比較しても、その的確な人物イメージの把握が素晴らしい。

第26代アメリカ合衆国セオドア・ローズヴェルト大統領の公式肖像画、ジョン・シンガー・サージェント制作、油彩、カンヴァス、1903年。
The official White House portrait of President Thodore Roosevelt(1858–1919),twenty-sixth president of the United States. John Singer Sargent (1856-1925), oil on canvas, 1903, The White House, Washington, D.C.
REFERENCE
Stephanie L.Herdrich, The Sargent: Masterworks, Rizzoli Electa, 2018