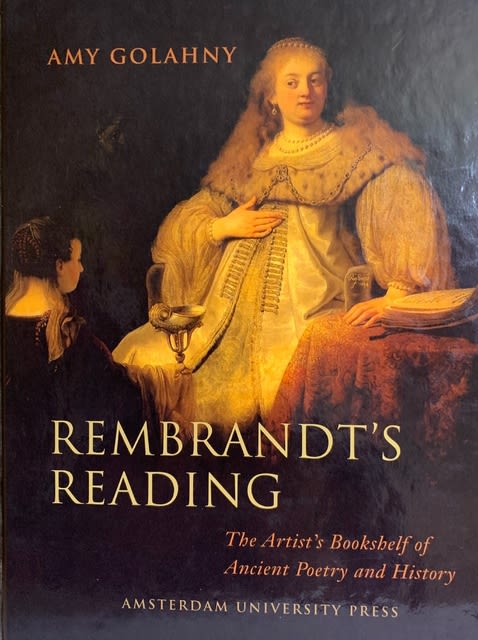
Cover illustration: Rembrandt, Artemisia, 1634.
カヴァー:レンブラント、アルテミシア、1634.
新型コロナウイルスへの感染予防のために導入された自粛生活は、必ずしも悪いことばかりではない。多くの人がこれまでの生活を振り返り、コロナ後のあるべき姿について考えている。激動する世界で生きるには時々立ち止まり、これまで来た道を振り返り、足元を見直すことも必要になる。
図書館や書店にも自由には行かれないとなると、身の回りのことに目がゆく。一度読んだ本でも、時間をおいて再読すると新たな発見がある。「断捨離」で涙を呑んでお別れする前にもう一度読み直したい本が次々と出てくる。今回は一冊の本*を手がかりに、かねてからの疑問、近世ヨーロッパの画家たちが自らの作品「ジャンル」をどうして決めていたかについて少し考えてみた。この場合、「ジャンル 」genre とは、絵画、詩・小説・戯曲など文芸作品の様式上の種類・種別をいう。
17-18世紀の画家の作品を見ていると、画家たちはなにを手がかりに自らのジャンルを設定していたのだろうかという疑問が生まれる。「静物画」、「風景画」、「肖像画」などについては、対象が比較的設定しやすい。「肖像画」などは顧客の依頼などもあるだろう。
しかし、「歴史画」、「宗教画」といわれるジャンルについては、描かれる対象について、かなりの準備や蓄積が必要に思われる。イメージは画家の脳裏で創り出される。同じ歴史の場面を描いても、画家によって見るものに与える印象は大きく異る。
画家の研鑽の成果
画家は主題についてなにを知っていたか。いかにしてイメージを形成したのだろうかという疑問が生まれる。この疑問は17世紀の画家ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの作品と生涯にのめり込んだ頃から抱いていた。
ラ・トゥールの作品はジャンルでみると「宗教画」が多い。17世紀ロレーヌのように文化環境という点では、決して恵まれていたとはいいがたい地域で、画家は主題をいかにして決定したのだろうか。そしてどのようなイメージで画布上に具体化したのだろう。他方、前回取り上げたシャルダンの場合は、「風俗画」や「静物画」のジャンルに入る作品が多い。画家が住んでいたパリの環境が反映している。
今回は、同じ17世紀、オランダの巨匠レンブラント(1606~1669)が活動していた社会の文化環境、言い換えると画家が受けた教育、自らの知的探究心による知識の習得・蓄積がいかなるものだったかを探索することで、画家の作品イメージ形成の一端を推察してみたい。レンブラントが聖書についての造詣が深かったことは知られているが、世俗的な主題について画家がどれほどの知識を持っていたかはほとんど不明のままであった。しかし、画家が古い歴史書などを探索し、歴史について研鑽を続けていたことが知られていた(Philip Angel, 1641)。
美術史家エイミー・ゴラニー Amy Golahnyは、レンブラントの本棚に残っていたと思われる書籍を材料に、この巨匠の創作活動の秘密に迫ろうとした。
Amy Golahny, Rembrand’s Reading, The Artist’s Bookshelf of Ancient Poetry and History, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2003. pp.283.
レンブラントの本棚
1656年、レンブラントが破産状態になった時には、画家がかなりの数の収集品を所有していたことが知られている。しかし、残っていた書籍は22冊にすぎなかった。そのうちのいくつかは表題も分かっており、旧約聖書、デューラーの比率に関する書籍、トビアス・スティマーが描いたフラヴィス・ジョセフス*に関する書籍などがあった。しかし、15冊についてはこれまで内容がはっきりしていなかった。レンブラントの仕事部屋については、詳細は不明だが作品《ヤン・シックスの肖像》などから雰囲気は感じることができる。
*
フラヴィス・ヨセフスは帝政ローマ期の政治家及び著述家。66年に勃発したユダヤ戦争で当初ユダヤ軍の指揮官として戦ったがローマ軍に投降し、ティトゥスの幕僚としてエルサレム陥落にいたる一部始終を目撃。後にこの顛末を記した『ユダヤ戦記』を著した。

レンブラントの芸術収集品のコーナー(再現)
(Golahny, 2003, p.76)
~~~~~~~~~
N.B.
1656年、レンブラントが破産状態になった時、高等裁判所は法定清算人を指定し、レンブラントに「セシオ・ボノルム」(ケッシオ・ボノールム、財産譲渡または財産委託)を宣告した。セシオ・ボノルムとは、商取引の損失でよく適用される債務者の財産をすべて現金化して全債権の弁済とする方法であり、破産するよりは比較的緩やかな処分である。これを受けてレンブラントの363項目にわたる財産目録が作成された[。
幸い、競売に付された財産リストが残っており、蒐集品の内容を知ることができる。著名な作者の絵画や素描、ローマ皇帝の胸像、日本の武具やアジアの物品、自然史関係の物品や鉱物などがあったことが知られている。競売は1656年9月に始まり、翌年まで続いた。1660年12月、画家は住み慣れた豪華な邸宅から貧民街であるヨルダーン地区ローゼンフラフトに移住した。
アムステルダムはすでに1578年に公的な図書館があった。レンブラントはライデンでラテン語学校へ通っていたし、徒弟修業も経験していた。破産時に財産目録中に残っていた22冊の書籍の中には、ジャック・カロが描いたイエレサレムについての1冊も含まれていた。
~~~~~~~~~
画家の置かれた文化的環境
1656年時点で残された書籍は、レンブラントがほとんどの財産について処分やむなしとして競売に付せられた後のことであり、目録に残る22冊が画家が所有していた書籍のすべてではないことも分かっている。
アムステルダムはすでに1578年に公的な図書館があった。レンブラントはライデンでラテン語学校へ通っていたし、徒弟修業も経験していた。破産時に財産目録中に残っていた22冊の書籍の中には、ジャック・カロが描いたイエレサレムについての1冊も含まれていた。
レンブラントが活動拠点としたオランダでは、画家がオランダ語について習熟していたことはいうまでもないが、おそらく言語の構造が類似しているドイツ語も読めたのではないかと推定されている。しかし、ルーベンス(1577~1640)のようにラテン語まで手中にしていたかというと、疑問が残る。
こうした点を踏まえた上で、エイミー・ゴラニーが興味深い研究を行った。レンブラントに関する研究は数多いが、この研究も限定されたスコープと史料ではあるが、興味深い結果を導いている。
レンブラントは破産後も画家として制作活動を再開しているが、多くの収集品を失った後は、かつての師匠 ピエテル・ラーストマン Pieter Lastman の工房にかなり頼ったのではないかと思われる。ラーストマンの収集品は、当時の画家たちの工房と比較して、かなり優れていたとみなされている。美術書などを含めて、制作活動の助けとなる書籍なども多数所蔵されていたのではないかと推定されている。
創作活動を支えた環境へ注目する
他方、ロレーヌのような戦乱の多い地域で制作活動を行ったジョルジュ・ド・ラ・トゥールのような画家にとっては、レンブラントのような恵まれた環境にはなく、「歴史画」のジャンルはきわめてハードルが高かったものと推定できる。代わって近づきうるジャンルはせいぜい「宗教画」そして「風俗画」のジャンルだったのではないか。
他方、ニコラ・プッサンやクロード・ロランのようにイタリアで制作活動を行えた画家は、文化環境という点でも格段に恵まれた条件を享受しえただろう。プッサンは宗教画、神話画、歴史画、肖像画など多彩なジャンルで活動したが、おそらく高い文化環境に恵まれたイタリア、ローマの地を拠点にしたから可能だったのだろう。
レンブラントの本棚に残された書籍を探索することで、巨匠の作品イメージの形成に迫るというゴラーニーの試みは大変斬新であり、疲れた脳細胞をかなり活性化させてくれた。巨匠は文字から得たイメージをいかにして絵画という次元へ昇華させたか。レンブラントが好きな方にはお勧めの一冊である。
Reference
Amy Golahny, Rembrand’s Reading, The Artist’s Bookshelf of Ancient Poetry and History, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2003. pp.283.
目次の紹介は省略。





























