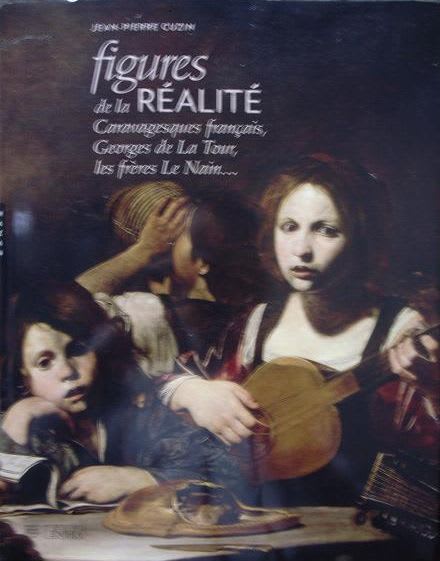ジョルジュ・ド・ラ・トゥールが洗礼を受けたサン・マリアン教会(ヴィック)銅版画
Emile auguin, Eglise Saint-Marien (Vic sur Seille), Gravure.
Source; Paulette Chone. Georges de La Tour
なにが、ジョルジュを貴族にさせたか
画家ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの作品ならびに生涯については、美術史などの研究者の地道な努力によって、かなりのことが明らかになった。しかし、不明な部分の方がはるかに大きい。特に、少し立ち入って作品を鑑賞してみたいと思う側として、ぜひ知りたい中核の部分が明らかにされていない。たとえば、この画家が1593年3月14日、ロレーヌの小さな町ヴィック・シュル・セイユで洗礼を受けた後、1616年10月20日、23歳で、同じ町の知り合いの子供の洗礼の代父として突如記録に登場するまで、公的な文書記録としてはなにも残っていない(1613年に同名の画家がパリにいたという謎の文書はあるが)。画家が最も重要な時期である画業の修業を、どこで受けたかという点についての情報がないのだ。これは、同時代のより知られていない画家については、ごく普通のことなのだが。
その後、画家の名が次第に公文書などの記録に残るようになってからも、不明な点は数多くある。そのひとつ、ジョルジュ・ド・ラ・トゥールが、ある時点からロレーヌ公国の貴族に列せられたことは確かなのだが、いつから、いかなる背景の下で貴族になったかという点は明らかでない。
もちろん、ジョルジュが妻として娶ったディアヌス・ル・ネールの父親が貴族であったことは確実な記録として残っているが、貴族の娘を妻としたからといって、画家の夫が直ちに貴族に列せられることはまずない。そこには、さまざまな要因が働いたと考えられる。
ラ・トゥールの才能を発掘したと思われるメッツ司教区ヴィックの代官ランベルヴィリエールなどの影響も十分ありうる。ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの母親の家系は、貴族の血筋を引いていたかもしれないという研究もあるが、これが直接影響したとは考えられない。仮に幼いジョルジュが、その話を母親から聞いていたとしても、それがなんらかの結果に結びついた可能性はきわめて少ない。マウエ家の例のように、子孫が貴族であった先祖のことを持ち出して、復権・継承を請願するようなことはありえないだろう。もちろん、こうしたことが貴族への願望につながったことはあったとしても。
1620年7月、画家が27歳までの間に、多くのロレーヌの画家のようにイタリアへ画業修業に赴いた可能性はきわめて低い。当時のローマなどイタリア文化礼賛の空気を考えれば、ローマに行っていれば、ロレーヌ公への請願書に記したことだろう。
画家についての謎は次々と浮かんでくる。あたかもクイズを解いていくような面白さがある。
今回、概略を紹介したロレーヌ公国の下級貴族マウエ家の記録文書は、ラ・トゥールと同時代を同じ地域で生きた貴族の生き様を伝えており、さまざまな点で参考になる。貴族となったジョルジュ・ド・ラ・トゥールの専横な振る舞いとされてきた点も、当時の下級貴族たちの生き方と多くの点で重なっており、とりわけラ・トゥールに固有な問題ではないと思われる。
貴族に任ぜられた後のラ・トゥールの考えや行動にも、探索に値する多くの謎が多数残されている。画家本人に直接かかわる記録がなくても、同時代に生きた人々の記録などが、新しい理解につながる糸口となることは十分ありうる。
もしかすると、今後もラ・トゥールに関する新たな文書あるいは作品が突然見出される可能性もないわけではない。作品の裏を読む興味が、長らくこの画家に惹かれてきたひとつの要因かもしれない。脳細胞が動いている間、もう少し探索の旅を続けてみたい。