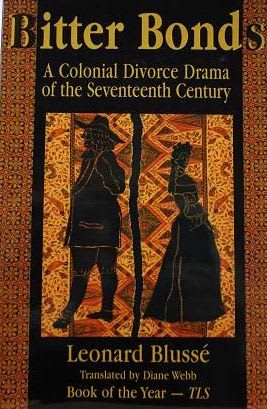年の終わりに
このところ年末になると、図らずもかなり哲学的なテーマが浮かんできて、しばし考えさせられる。ことさらに、自分でそうした課題を設定しているわけではない。色々なことがきっかけになって、考えさせられるだけのことである。
一昨年と昨年は「幸福とはなにか」という課題について考えていた。比較的よく目にしているイギリスの雑誌 The Economist が、クリスマスの特別号に短い論文を掲載し、触発されたこともある。今年は「進歩についての現代の考えは、なぜこれほどまでに中身がなくなったのか」*1という論題だ。いずれも、ブログに取り上げるには難しすぎる。
「進歩」progress という概念は、いつ頃歴史に登場し、その後いかなる経過をたどって、今日にいたったのか。「進歩」という概念自体、論者によってさまざまで到底一元的に整理はできない。しかし、漠然としてはいるが、人間がある望ましいと思われる一定の方向へ進んでいることを意味している。
こうした考えが生まれたのは、主にヨーロッパで人間の素晴らしさが開花したルネッサンスの土壌の上に、文化、技術、商業などの革命的変化が展開した17世紀以降、とりわけ啓蒙運動時代に遡るとされている。確かにこの頃から、地球上に生まれた富は、概していえば、さまざまに人間の世界を潤し、生活を豊かにした。その後、多くの起伏はあったが、20世紀に入ると「進歩」の考えは次第に正面から問題として取り上げられることが少なくなった。そればかりか、議論自体が内容に乏しくなった。確かに、まだ学生であった頃、まさにこの問題を取り上げたバリーの古典的名著『進歩の概念』*2を読んだことがあった。その後、折に触れて考えることはあったが、本格的議論に出会ったことはなかった。
「進歩」ということがまだ議論されていた頃の作品だが、今回、ひとつのたとえ話が取り上げられている。1861年に出版されたハンガリア人作家、イムレ・マダックの『人間の悲劇』Imre Madach. The Tragedy of Man(Az ember tragédiája)と題した長詩だ。
アダムとイヴが楽園を追われ、神から離れ、自らの力でエデンの園を再建しようとする。彼らは「私の神は自分だ」「私が取り戻したものは私のものだ。これこそが私のすべての力と誇りの源だ」と自負する。さて、どれだけのエデンを「取り戻す」か。二人は勇躍し、楽園を求める旅に出る。
古代エジプトから出発するが、それが奴隷制の上に築かれていることを知り、次のギリシャに移るが、偉人を否定する民主制に飽きたらず、ローマの無害な世俗的享楽へと移行する。こうして時間とともに次々と11の歴史上の場を旅をするが、楽園は見いだせない。彼らの旅の最後は人間らしさが凍り付いたようなたそがれで終わる。人類の傲慢さに対する警告の物語だ。
現代人の目から見ると、「進歩」はどう見えるだろうか。これほどの暗い閉ざされた光景ではないにせよ、諸手を挙げて人間は進歩しているとはなかなか言い切れない。宇宙基地ができる時代ではあるが、地球上に戦争は絶えず、環境悪化は進歩どころか、破滅につながりかねない。
確かに人間の物質的生活は総じて豊かになった。それは17世紀とは比較にならない。しかし、天井知らずに豊かになった人たちの対極には、数世紀昔からほとんど変わらないような水準の生活を続けている人たちも少なくない。
The Economist の論説は上記のマダックの旅の一場面を例示し、神が人間に求めることは、ひたすら進歩に向けて励むことだと結んでいる。楽園と堕落・退歩の両極のいずれかの選択ではないという。進歩は保証もされてはいないが、まったく希望がないわけでもない。すべて人間の意思と行動次第にかかっているという。至極妥当な結びといえば、その通りだ。しかし、個人的にはなにか物足りない。昨年の「幸福とはなにか」と同様、この課題も満足感にいたらず、思い半ばで新年以降に持ち越されそうだ。
どうぞ良いお年をお迎えください
References
*1
”Onwards and upwards: Why is the modern view of progress so impoverished?” The Economist December 19th 2009
*2
J.B. Bury. The Idea of Progress: An inquiry into its growth and origin, New York: Dover Publications, 1955, unabridged and unaltered republication of the 1932 edition, pp.357.