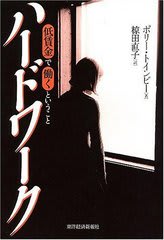リュネヴィルで開花するラトゥールの才能
ラトゥールがリュネヴィルに移り住んでからのほぼ10年間、1620年代は、ロレーヌ地方にとって、おおむね繁栄を享受しえた時期であった。1624年7月末のアンリII世の死去と、その後のチャールズIV世の継承についての不安は住民の間にあったとは思われるが、その後の時期と比較すると明らかに平穏な時代であった。
ラトゥールは、妻の故郷であるリュネヴィルで画家としての地位を確保し、その才能を十二分に発揮しえた。彼はリュネヴィルを本拠にロレーヌの画家としてたちまち頭角を現し、社会的にも名士として上流階級に迎えられていった。その過程で、彼の妻ディアンヌがどのくらい助けになったかは公的な資料しかなく、推定は難しい。それでも、ディアンヌは夫の名前と並び、しばしば記録に登場している。
多産多死の時代
リュネヴィルという地方都市の規模と社交の範囲を考えれば、すでにディアンヌの父親は娘の結婚の翌年に世を去っていたが、ディアンヌは貴族の家系を継承して相応の社会的ステイタスを保っていたと思われる。
ラトゥールとの結婚は、その当時の状況に照らして、概して幸福であったとみられる。1919-36年の間に5人の男児、5人の女児、合計10人の誕生が記録されている。15-17ヶ月の間隔で子供が生まれている。
現代の人々は、ずいぶん多産と思うかもしれないが、幼児死亡率の高さなども考えると、当時のロレーヌでは良く見られた出産パターンであった。大体、40歳代で出産は終わる。1636年以降の出産があった可能性もないではないが、ディアンヌはそうであれば45歳になっていたはずで、リュネヴィルも波乱の時代に入っていた。1642年に生活が平静を取り戻した時には、ディアンヌは55歳になっていたはずである。当時の環境を考えると、この年齢で出産の可能性はきわめて少ない。
夫妻の間に生まれた10人の子供のうちで、最初の5人の中でわずかに3人だけが両親とほぼ時代を生きている(6人目からの子供はすべて死亡)。わずかに画家となった息子エティエンヌの5歳下であったクリスティーヌだけが両親より後まで生きながらえている。死亡した者の記録は、ひとりを除き存在していない。おそらく1630年代の疫病期に死亡したとみられる。
この実態を考えると、当時の人々がいかなる不安を抱き、救いの手がかりをなにに求めていたか、推測ができよう。
画家はどこに住んでいたか
ラトゥール夫妻がリュネヴィルへ移住してきて、どこに住んだかも十分な記録がなく不明である。しかし、1620年8月31日に聖フランシス修道女会の修道女たちSisters of St Francisから224フランで購入した”meix”と呼ばれる土地つきの家に住んだとは考えられていない。
この資産は1年前に義母のカトリーヌ・ラマンスが売却したものだった。ラトゥールはそれを買い戻したのだが、小さな土地で粗末な農夫の家があったにすぎない。羊小屋sheepfoldsといわれた土地で、価格からしてもラトゥール夫妻が一時的にも居住したとは思えない。おそらく、ラトゥール夫妻は当初ル・ネルフ家が所有していた家屋か、義母の家に移り住んだと思われる。
しかし、1623年義母は息子のフランソワと住むことに決め、転地している。フランソワはその当時テノワTennois教区の司祭であった。ラトゥールは、義母の家を当時としては少なからぬ額である2500フランで購入している。そこには納屋とか、羊小屋とか牧草地もあった。そしてサンジャック教会への道に続いていた。この地の名士の家としてふさわしい場所であったと思われる(この光景は、7月4日の記事で紹介したデイヴィッド・ハドルの小説にも使われている。)。ラトゥールはそこへアトリエを建てて、その後の制作を行ったのだろう。
リュネヴィルに落ち着いてからは年を経るごとに、ラトゥールの生活もかなり充実したと思われる。
徒弟の受け入れ
画家としての職業も軌道に乗っていた。ラトゥールは1620年、最初の徒弟クロード・バカラを受け入れている。そして、彼に対して「誠実かつ熱心に・・・・・絵画の技を教示し、習得させるものとする。・・・・・・当該の技の徒弟修業を行うのに必要な絵具を彼に対して供給する」ことを約束している。
1626年には徒弟、シャルル・ロワネを受け入れている。この時は住居、まかない付きであった。工房や住居も拡大したのだろう。3年間の徒弟受け入れ費用は500フラン、当時のパリ並みの水準であった。
土地の名士としての活動
ラトゥールはさまざまな機会に、妻ディアンヌ側の家族や親戚の支援を受けた。リュネヴィルではそうした機会が多数あったことが記録に残っている。逆にラトゥール自身も、洗礼の代父、名づけ親、さまざまな機会の保証人などとして登場している。妻側の親戚筋などのつながりも十二分に活用していたことが、記録文書から確認されている。
ラトゥールは家の財政問題にも注意深く対処していた。1623年、義母の家屋・土地などを2500フランで購入するについて、資金手当てをしていたと思われる記録がある。彼は1618年の父親そして義父の死亡の時、そして1624年、母親の死亡の折もかなりの遺産相続をしているようだ。
記録が十分でないだけに、研究者などの間でもさまざまな憶測、議論を生んできたが、リュネヴィルには家畜や相当の農地も所有していた。穀物倉には高い利益の得られるとうもろこしが搬入されていたようだ。しかし、これらの資産からの収入などについては、情報が少ない。はっきりしていることは、ラトゥールの収入のほとんどは、疑いもなく彼の制作した作品から生まれていたことである。
しかし、残念ながら誰がラトゥールの作品の顧客であったかについてはほとんど不明である。 公式記録にあるのは公爵アンリII世がラトゥールの2枚の絵を購入し、1枚は123フラン(1623年7月12日付け)、もう1枚は画題の記録では、”image of St Peter” となっているが、150フランで1624年7月以前に支払ったことである。これらは当時の絵画作品の価格としては、きわめて高額であった。特に後者を現存する「聖ペテロの画像」とすると、とりわけそうである。この絵はロレーヌ公によってリュネヴィルのミニモ会修道院に捧げられている。ラトゥールに対する公爵の後ろ盾があったことか、画家の力量を誇示する価格なのかは不明である。
画家としてのジャンル選択
いずれにせよ、かなりはっきりしていることは、ラトゥールはこの時期に生涯で最も活発に制作活動をしていた。今後さらに検討すべき、やや不思議な点もある。
この当時は一般に大きな祭壇画がもてはやされていた。しかし、こうした大作はラトゥールについては、いまだ見つかっていない。さらに、当時の環境からすると、ラトゥールは肖像画もかなり手がけたはずであった。肖像画は金を手に入れる手ごろな手段であり、土地の名士であるラトゥールには、その点での人脈もあり、依頼も多かったと思われる。彼の画才からすれば、肖像画家としても十分な力量もあったはずなのだが、肖像画を描いた形跡はない。
おそらく中流および高貴な階層の顧客が、家庭で鑑賞あるいは護符の意味も兼ねて保持していたいと思い、ラトゥールの作品を求めた事情などがあったのだろう。
祭壇画や肖像画で、ナンシーの競争相手と同じ土俵で競うことを避けたのかもしれない。こうした制作態度は1630年以降、プッサンがローマで行っていたことであり、ラトゥールはリュネヴィルで同様な道を選択したものと推定される。
いずれにしても、この時期においてラトゥールはかなりの資産家であり、裕福に暮らしていた。
References
Jacques Thuillier. Georges de La Tour, Flammarion, 1992, 1997(revised)
『Georges de La Tour.』東京国立西洋美術館「ジョルジュ・ド・ラトゥール展カタログ」2005年