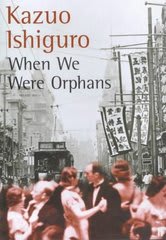Unknown (after La Tour), St. Sebastian Tended by Irene, Staatliche Museum, Berlin
真贋論争を超えて
前回、(横長の)「聖セバスティアヌス」をとりあげたからには、(縦長の)「聖セバスティアン」を見逃すわけには行かない。いずれ劣らぬ素晴らしい作品である。しかし、専門家からはいずれもラ・トゥール本人の真作とは認められていない。ラ・トゥールは、本人の責任ではないとはいえ、実に真贋論争の渦中に取り込まれることの多い画家である。それほど、模作・コピー・贋作が多いということは、この画家の作品が時代を超えて人々に訴えるものを持っているからだろう。真作でなくても、身近かに置きたいという人々が多かったと思われる。実際、これらの作品に接すると、真贋論争など、どうでもよいという気になってくる。
というわけで、この(縦長の)「聖セバスティアヌス」も、専門家によるラ・トゥールの真作というお墨付きのない作品である(初めて、この画家の作品をまとめて見る機会があった1972年オランジュリー展当時は、ラ・トゥールの真作とされていた。田中英道『ラ・トゥール:夜の画家の作品世界』造形社、1972年にも掲載されている。)しかし、この絵に接した人は、直ちに並はずれた力量の持ち主の手によるものであることを感じるだろう。そして、前回見た(横長の)「聖セバスティアヌスス」と、根底でどこかつながっていることを思うのではないか。
モダーンな構図
事実、作品の発見・検証の過程はそうであった。この縦長の「聖セバスティアヌス」はまったく同じ構図の作品が2点発見されている。それぞれ、ルーヴルとベルリン国立美術館が所蔵している。今回は、ベルリン版を見てみよう。(ベルリン国立美術館が所蔵する現作品は、最初の出所は不明だが、ブラッセルに持ち込まれ、1906年ニューヨークのStillwell Collectionの所有となるが、1927年に売りに出され、ベルリンのMatthiesen Galleryが入手、その後Kaisesr-Friedrich Museumの時代を経て、現在のベルリン国立美術館に移転している。)
主題は横長の作品と同じではあるが、いずれもそれぞれに斬新な印象を与える。特に、縦長の作品は大変モダーンな感じがする。構図自体が洗練されていて見事であり、意図して筆を抑制し、輪郭を鮮明にしたような部分もある。とりわけ、中央の黒衣の女性の顔立ちなどにそれがうかがわれる。
描かれた登場人物は、5人である。矢で射抜かれ、瀕死の状態で横たわる若者聖セバスティアヌスとたいまつをかかげて事態を見つめる聖女イレーヌと友人、従者と思われる女性が描かれている。横長の作品と今回の作品に共通な点のひとつは、同時代の他の画家たちが、聖セバスティアヌスにかなり焦点を当てているのとは異なり、聖女イレーヌに重点を移していることである。この縦長の作品では、紅赤色の衣装をまとった聖イレーヌと黒い衣装の女性が中心人物である。
見事な仕事
ベルリン版とルーヴル版の明瞭な相違点は、後列で合掌する従者のかぶるヴェールがルーヴル版では美しい青色で描かれているが、ベルリン版では黒色である。これは、ベルリン版は安価な顔料が使われたために、褪色した結果らしい。その他の点では、ベルリン版の方が全体に色鮮やかであり、コントラストが大きくとられている。ただ、後ろに並ぶ二人の従者については、ルーヴル版の方がはっきり描かれている。これらのことを含めて、今日ではベルリン版はラ・トゥール工房で制作された正確なコピーと推定されている(キュザン=サルモン)。他方、全体としてルーヴル版の方が穏やかな、落ち着いた印象ではある。しかし、見る人の好みもあるが、いずれも甲乙つけがたいところがある。これは、「いかさま師」の場合などにも当てはまる。
両者に当てはまるが、細部にわたる綿密な制作ぶりには圧倒される。従者のかぶる帽子の縁取りまで丁寧に描き込まれている。たいまつの光に映し出された聖女イレーヌの胴着の紅赤色の美しさ、スリーヴの陰影も見事である。とりわけ、聖女イレーヌのかかげるたいまつの3重に重なった炎のゆらぎは、絶妙といってよい。昨今のデジタル画像も、遠く及ばないのではないかと思われるほどである。
美しい画面にこめられた深い悲しみ
伝承によれば、聖セバスティアヌス(2013/0115修正)はこの後、イレーヌたちの介抱で一度命を取り戻すが、まもなく殉教し世を去ることになる。意識を失っている若者の脈をとる聖女イレーヌ、そして友人の妻(?)、従者たちの表情には、闇の彼方に待ち受ける結末が見えているようだ。画家が聖ヒエロニムスについては陰影で覆い、見る人の視点を介抱する聖女イレーヌの方に誘導しているのは、この若者の運命がもはや限られたものであることを暗示している。
横長の作品以上に、抑制された色彩と様式化された描き方で、ジャック・テュイリエが指摘するように、後年のキュービストにつながるところがある。ルーヴル版と比較して、ベルリン版の方がその印象が強い(ちなみに、この二つの版が並列して比較されたのは、1972年のパリでの展示であった。最近は印刷や画像の技術が大変進歩しているので、必ずしも現物を並べなくても、かなりの点は明らかになるが、当時は並列、比較の意味は大きかったに違いない。ラ・トゥールについて、私が最初に日本語文献で読み、感銘を受けた田中英道『ラ・トゥール:夜の画家の作品世界』の時点では、印刷技術も今日ほど進んでいなかったので、作品一覧の図版はモノクロであった)。
ラ・トゥールの他の作品と同様に画題にもかかわらず、宗教画的な印象をほとんど与えない。しかし、画面を覆う独特の静謐さ、完成された美的構図が人々の胸に響く。他の画家の作品に多い光輪や天使はいっさい描かれていない。同時代の人々にとっては、もしかすると、自分たちの日常生活の中にいる人たちではないかと思わせるイメージである。しかし、そこには引き締まった空間が生まれ、世俗の世界とは微妙な一角を画している。
「(横長の)聖セバスティアヌス」と並び、これらの作品が疫病や戦乱などがもたらした不安の中に、一筋の光明を見出したいと思う人々にとって、なににもまして心の救い、護符の役割を果たしたことは容易に想像できる。その思いは、フランス王やロレーヌ公爵などの上流階層から、小さな教会に通う一般人まで共通なものであったのだろう。このテーマの作品が多数コピーとして存在するのは、そうした事情があったに違いない。
よみがえった古典世界
ルーヴル美術館所蔵の作品についても記しておくと、来歴は不明だが、1649年にロレーヌ公に寄贈されたものに相当するのではないかと推定されている。作品は1945年にノルマンディのボワ=アンズレーの小さな教会で発見され、ルーヴルへ落ち着くことになった。修復後、1948年から展示されている。最初はラ・トゥール工房の作品の域を出ない、あるいは単なるコピーではないかとの評価もあったが、その後、再評価が進み、X線調査なども行われて今日ではラ・トゥール自身の手になるものでないにせよ、オリジナル作品であるとされている。ベルリン版も同様にオリジナル作品あるいはそれにきわめて近い作品との評価で落ち着いているようだ。いずれも、その光の絶妙さ、熟達した筆使い、そしてなによりも構成の美しさからラ・トゥール工房で少なくともラ・トゥールの指導の下、あるいはラ・トゥール自身が筆を加えて制作されたものではないかとの推測もなされている(Thuillier 222)。
これらの作品を通して、幸いにも、見事に17世紀という「同時代」contemporaryによみがえった古典ローマの世界に接することができる。そればかりか、明日なにが起こるか分からないという現代社会が抱え込んだ不安に対する一筋の光明と心の支えを、この絵に見出す人もいることだろう。