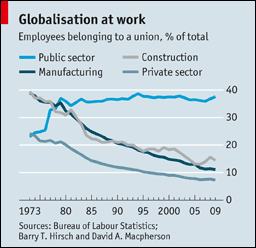最近、歴史家(京都大学)の藤原辰史氏が『日本経済新聞』に「就活廃止論1&2」*2 を寄稿されていた。この機会に問題が発生した頃から、ブログ筆者も多少関わったこともある就活廃止に向けての議論を振り返ってみた。
*1
その後、2013年には政府の要請もあり、経団連が「採用選考に関する指針」(通称:採用選考指針)を発表し、2016年卒業生から、広報活動は「卒業・終了年度に入る前年度の3月1日以降」、採用選考活動は「卒業・終了年度の8月1日以降」に開始すると提示している。
この問題については、ブログ筆者も協定の廃止で事態が深刻化した当時、さまざまなメディアで、就職活動のあるべき姿について意見を求められたり、検討委員会の一員として改善案*3を求められたりしてきた。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「学生の職業観の確立に向けて:就職をめぐる学生と大学と社会」日本私立大学連盟・就職部会就職問題研究分科会1997年6月
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
しかし、それから20年以上経過した現在の状況は、実質的に何も変わっていない。大学側、経営側双方に事態を改善しようという意欲が欠けている。成り行き任せで、今年も同じという事態が継続してきた。
あまりに長い期間、抜本的改善もなく放置されてきただけに、多くの問題が発生、蔓延、定着してしまい、事態を容易に立て直すこともできなくなっている。
改めて考え直してみると、究極の問題は、大学生活において最も重要な時期である最終学年の勉学が就活のために大きく損なわれることについての大学、企業など当事者の責任感が弱く、改善努力に欠けることにある。
この問題に長らく当事者として関わってきた者の一人として、改めて提言したいのは、就活を大学生活と時期的に切り離し、原則、大学卒業後に移行することである。大学生活のあるべき状態をなんとか取り戻したい。就活はひとまず大学などでの学業を修めた段階で、職業を選択する上で必要な行動である。兵役などとは異なり、自らの意思で望ましいと考える職業機会に就くためには必須の期間でもある。他方、大学などの最終年次は、学業の修得の成否を左右する最重要な時期に当たる。卒業論文などの作成もこの時期と重なる。大学のみならず、企業側もこの点を改めて認識すべきだろう。
筆者の経験で分かりやすい例をあげてみよう。ある年、4年生になったゼミ生のひとりが2、3ヶ月ゼミに出席していないことがあった。他の学生はほぼ全員出席していたので、当該学生になぜ出席できないのか尋ねたところ、父親から電話があり、「今は息子の人生を決める重要な時だ。大学側は半年くらい閉講にして、学生のことを考えるべきだ」との厳しい口調であった。筆者も立場上、強く反論はしたが、息子の人生が決まるとまで言われると、いささか答えに苦しむ所もあった。
こうした経験も踏まえた上で長らく考えた結果、望ましい解決は、大学生活と就活を切り離し、後者を卒業後の時期に充当することしかないという結論に至った。大学としては、教育の場としてのあるべき姿を回復、確保することが第一義的に重要なことだ。就活は必要な行動だが、大学生としての必要な課程を全うした学生が対象になるべきだ。諸外国の例を見ても在学中に職業が定まる比率は、日本よりはるかに低い。就職のための活動は、原則卒業後の活動と考えられている。自らの学業習得の成果を語れるのは、本来規定の学修過程を終了してのことである。そのためには、就活をする学生が、大学生活をあるべき形で終了したことを示す示す証明、端的には卒業証書が必要だろう。
卒業証書であるから、常識では卒業式*4の際に手渡されるのが普通である。その時期は、ほぼ統一されており、日本では3月末には終了する。それから数ヶ月が新しい就活の時期となる。卒業論文をもって証書に代えるというのは、普遍的に実施することは難しい。学生の学習成果を示す2次的な証明材料とはなるだろう。卒論を構想、作成するにしても、雑念に惑わされず、専念できる期間が必要だ。
*4
会社訪問を含む就活は、ここからスタートする。全ての候補者が同じ線上に並ぶことになる。卒業証書を授与されていない学生は、就活の対象とならないとすることで、就職市場では最低限の整理が行われる。企業、大学側も、求職、採用に至る活動は、効率的に行われるため、比較的短期間になるだろう。元来、外国で見られるように、採用は通年で行われるものであり、日本のように特定の時期に入社などが集中するのは異例といえる。卒業証書を持っている者は、通年いずれの時でも求職の活動を行えることになる。労働市場の国際化が進む中、こうした次元へ日本も移行することは望ましいことでもある。
この新しい次元への移行に際しては、大学側と企業側の間で、目的達成に必要な最低の条件を整えるためのルールの確認と申し合わせを改めて確認、遵守することが必要である。大学生の在学期間を勉学という本来の活動に当てることは、それに続く就活を後押しすることになり、学生は4年間の学生生活を本来あるべき形で全うできるはずだ。充実した学業の成果を達成した学生を採用対象とできることは、優れた人材を望む企業側にとって本来望むべきことなのだから。これまで見られた在学中に就職先が決まってしまったことで、残された期間が安易に過ごされてしまう例もなくなるだろう。
他の諸国にはほとんど見られない修学の期間を犠牲にしての就活という奇妙な慣行を速やかに消滅させ、本来の大学のあるべき姿を取り戻すことは、入学者の減少を始めとする危機的段階を迎えた日本の大学にとって、真摯に考えるべき重要事項だ。これまでのように安易に流されることなく、教育そして職業選択という重要な活動をあるべき姿に取り戻す時である。