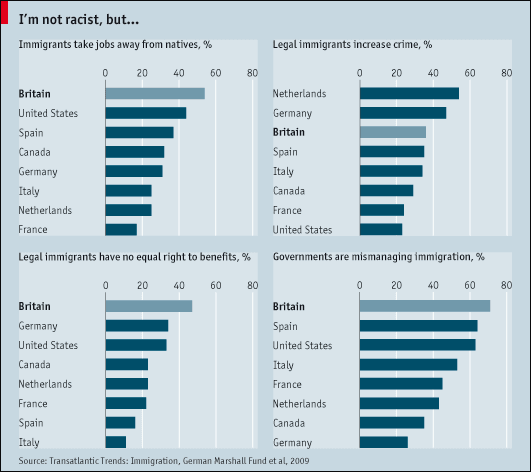ドバイ・ショックがリーマン・ショックのごとき世界経済への決定的な大衝撃にいたらず、多くの人々がほっとしたのではないか。といっても、問題が完全に解決したわけではない。関連して読んだ記事*の中から、このブログのテーマに関連する話題をひとつ。
ドバイ危機の騒ぎの中であまり話題にはならなかったが、この国に世界最高のビルと誇示するブルジュ・ハリファBurj Khalifaが竣工した。公称168階建て、最高828メートルの超高層ビルだ。これまで順風満帆であるかにみえたドバイ経済が急発展した中から生まれた大胆な建造物だ。ドバイ・ショックの洗礼を受けた後では、なにやら「砂上の楼閣」の感も禁じ得ない。
注目すべきことは、この建物がほとんどすべて外国人によって企画、建造されたことだ。アメリカ企業が設計し、施工、管理は韓国、ベルギー、日本などの外国企業が行い、もっとも時間と労力を要する土木工事は東南アジアを中心とする外国人出稼ぎ労働者が担った。 関与した労働者の国籍は100カ国を越えた。
実際、アラブ首長国連邦の労働力の90%は外国人だ。カタール、クエートでは80%以上である。サウジアラビアのように2200万人近い自国民を擁する国であっても、同国の仕事の半数近くは外国人が担っている。しかし、彼ら外国人はこの国に住むことを認められていない。仕事が終われば、直ちに国へ帰るしかない。生産工程に投入される原材料のように、融通無碍に増減されるフローの労働力として位置づけられている。
他方、公務員に代表される高給で安定した仕事の機会は、ローカルの自国民にしか開放されない。彼らは事業や景気の後退時にも解雇されることがない、いわばストック労働力だ。経営管理者層や中間管理職層などの仕事は、UAEの自国民、下級技能の事務や肉体労働は、ほとんどすべて低賃金・フロー型の外国人労働者によって担われている。両者の間には賃金など労働条件でみても、「超絶格差社会」ともいうべき実態が存在する。
湾岸諸国の多くは、概してマクロ経済的には豊かだ。しかし、この豊かさはその反面で、無気力、無関心、退廃、安逸に流れるなどの後退現象を引き起こす。自分がこの世界でなにをなすべきか、なにができるかを見出すことができず、無為、無気力に日々を過ごしている若者たちが増えている。彼らは低賃金の民間雇用の機会には就こうとしない。やむなく、そうした仕事は出稼ぎ外国人労働者にゆだねられている。自国民でありながら、積極的に生きるインセンティブを見出せない人たちの増加に、国の指導者たちのいらだちはつのる。なんとなく、日本の現実に通じるところもある。
こうした湾岸諸国の物質的には恵まれた豊かな国民と、貧しい出稼ぎ外国人の実態を、「マリアナ海溝」にたとえる人もいる。社会が別の社会のように、深く断絶、分け隔てられているという意味だ。近年、UAE政府は、「首長国化」Emiratisation あるいは「サウジ化」Saudisationというのスローガンの下に、企業に割り当て制で自国民を優先雇用するように勧めている。さらに、UAEとサウジは、景気後退時には外国人を最初に解雇するように指示してもいる。ローカル優先策である。
こうした状況で、バーレーンの採用した政策に湾岸諸国の注目が集まっている。バーレーンも民間部門の仕事の80%近くを外国人労働者に頼っている。 しかし、政府は外国人労働者の雇用を抑制する反面で、ローカルな自国民をより雇用しやすい状況を生み出すことを意図している。豊かな社会に取り残された無気力な若い労働者の雇用機会の創出だ。
この目的のために、2008年7月以降、バーレーン政府は、外国人の労働ヴィザの発給について、企業に対し外国人一人当たり200ディナール(530ドル)の費用支払いを、さらに外国人従業員一人当たり、毎月10ディナールの課金支払いを求めている。外国人労働者を雇用するコストを高めて、ローカルな国内労働者に目を向けさせようとする考えだ。
しかし、バーレーンの経営者たちはこうした課金を払っても、外国人労働者を雇用することをやめられないでいる。 バーレーンはその後、外国人労働者への課金を増やし、年間9百万ディナールが課金収入として入ってきた。その80%は「タムキーン」(Tamkeen バーレーン企業と労働者の生産性改善のための機関)へ、安いローンと訓練費用負担という形で注入される。19,000人のスキルを持たないバーレーン人労働者を訓練し、データ入力の仕事、新聞配達などの仕事を与えようとしている。 言い換えると、外国人労働者を雇用することを課金によってコストが高いものとし、得られた課金を原資に自国民労働者の雇用改善を図ろうとする政策だ。
安い労働力の存在は訓練、技術への投資を妨げていると、バーレーンの労働大臣は述べる。「だから生産性は低く、賃金も低い。そのため民間部門はバーレーン人にとって魅力がないものとなる。バーレーンはローカルな人々が期待する高い賃金にふさわしい労働力を養成したい。」
合理的な考えのように見えるかもしれない。しかし、どこかおかしい。いくつかのことが考えられる。最大の問題は、バーレーンに代表される湾岸諸国は、外国人労働者の力と才能を十分に取り入れない限り、発展はありえないということだ。彼らの存在を必要悪のように考え、「2級市民」として固定化する政策に固執するかぎり、望む成果は得られない。
外国人労働者の受け入れを国民的議論の対象とすることなく、先延ばしにしている日本とは、大きく異なると思われるかもしれない。しかし、この問題、よく考えると、日本の格差縮小政策についても、大きな示唆を含んでいる。
バーレーン労働者と外国人労働者の労働コスト
民間部門 (通貨単位:バーレーン・ディナール)

References
* "Briging the gap" The Economist 2010
中東湾岸諸国の労働実態は、日本ではあまり知られていない。下記の新著は出版時とドバイ金融危機が運悪く重なってしまって大変残念だが、中東を代表するドバイの実態を深く解明した労作だ。ご関心のある方々にぜひお勧めしたい。
佐野陽子『ドバイのまちづくり』慶応義塾大学出版会、2009年