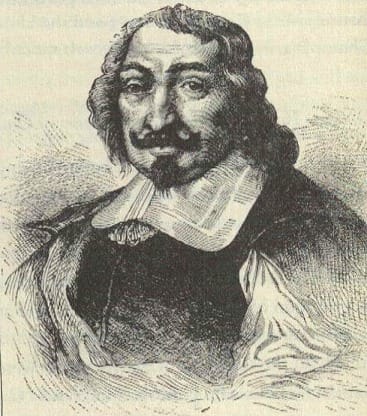VERMEER, Johannes
(b. 1632, Delft, d. 1675, Delft)
A Lady Drinking and a Gentleman
c. 1658
Oil on canvas, 66,3 x 76,5 cm
Staatliche Museen, Berlin
2011年という年が世界史上、画期的な年となることは半年を経過した段階でほぼ見えてきた。しかし、過去の歴史で世界が大きく転換する年であったことを後年まで気がつかなかったことは多々ある。歴史の評価には時の経過を含めて、かなりの熟成が必要であることは少しずつ分かってきた。
帽子ひとつから見えてくる世界
フェルメールの作品と推定されるもので、描かれた人物が帽子を被っている作品はいくつかある。しかし、この画家を専門の研究対象とする美術史家の多くは、帽子は作品に描き込まれた小道具程度にしか考えてこなかった。帽子がどこで作られたかなど、作品の解釈には関係ないと思っている。だが、興味深い世界はそこから開かれるのだ。あの『不思議な国のアリス』で、シルクハットをかぶったウサギが飛び込んだ穴のように。広い世界への入り口は別に帽子でなくてもよいのだが、ブルックは話を面白くするために帽子を選んだのだろう。
ブルックはフェルメールの作品のビーヴァー帽を被るオランダ軍の士官と思われる若者が後ろ向きに脇役として描かれている背景についても記しているが、文字通り、作品の裏を読むことは多くの新しい事実を明るみに出してくれる。しばらく前まではオランダ独立戦争の主役であった兵士(志願兵や民兵)たちの時代は終わり、舞台は兵士から市民へ、君主制から共和制、カトリックからカルヴィニズム、君主国から市民国家、そして戦争から貿易へと移りつつあった。グローバリゼーションの夜明けでもあった。
さらに「フェルメールの帽子」というと、どうもあの「赤い帽子の女」*を思い出す人が多いようだ。しかし、この作品はこれまでの美術史家などの鑑定では、フェルメールの作品ではないという見方が有力だ。

Girl with a Red Hat, ca. 1672, Washington: National Gallery
*推定の根拠のひとつには、この作品が大変小さく、しかもキャンヴァスではなく、板上に描かれている、雰囲気がフェルメールの他の作品と異なる、などの理由が挙げられている。それ以外にも、最近はフェルメールに近い家族の一員ではないかなど、興味深い研究・推察が行われているが、今回はひとまず措いておこう。この赤い帽子もなかなかの代物なのだ。
帽子は社会階層のアイコン
以前のブログに記したように、フェルメールの生きた17世紀オランダあるいはイギリスでは、男女ともに、帽子なしで人目に触れる場に出るということは考えられなかった。帽子はその人がいかなる人物、階層、職業であるかなどを象徴する重要なアイコンだった。とりわけ、作品に描かれた娘と語り合う若い兵士や下士官などにとっては、ファッションや社会的地位を誇示する重要な装身具だった。とりわけ男性にとっては、北米産ビーヴァーの毛皮で作られた帽子をかぶることは、虚栄心も満たす重要な役割を持っていた。美麗に仕立てられ、実用性の点でも防水性に優れ、耐久性も抜群のビーヴァー毛皮の帽子は競って求められた。 毛皮の帽子といっても、ビーヴァーやラッコなどの毛皮の柔らかい内毛だけを丁寧に採取、縮絨、加工して、フェルト化した美しい出来合いだ。当時の絵画などを注意してみると、さまざまなタイプがある。
王侯、貴族、聖職者、軍人など、それぞれの社会的階層に応じて、デザインの異なる帽子があった。たとえば、イギリス紳士の象徴とされてきた通称山高帽も、材料は、絹、ビロード、タフタ、ウールなどさまざまであったが、最も高価なものはビーヴァー毛皮が使われた。それまで広く着用されてきた羊毛フェルト製の帽子は、最初はエレガントだが、雨に濡れるとたちまち汚れ、変色し、男たちは高価だがしっかりと縮絨加工されている、丈夫な毛皮の帽子を好んだ。ビーヴァー(beaver海狸ともいわれるが狸ではない)は、ねずみ目ビーヴァー科ビーヴァー属の哺乳類でヨーロッパにも生息するが、北米産の毛皮が格段に人気を集めた。フェルメールの家にも、こうした帽子があったと思われるし、実際にも作品に描かれたような男女が出入りしていたのだろう。当時、貿易国として世界各地へ乗り出していったオランダであった。フェルメールやレンブラントの目の前をさまざまな珍しい外国の産物が通り過ぎていた。毛皮の帽子にしても、当時のヨーロッパの国々の支配者や探検家たちが思い描いていた「中国への道」発見の副産物ともいえるものだった。
フランスが目をつけたカナダ
西欧の歴史上、最初にカナダを発見したのはイギリスのヘンリー7世が派遣したイタリア人探検家ジョン・カボットと、セントローレンス川を探検したフランス人ジャック・カルティエであるとされている。当時、大西洋を西北に向かえばアジア、とりわけ中国に到達する経路があると信じられていた。イギリスはこの新世界の開拓・領有に食指を動かしていなかったが、フランスは1526年探検家カルティエをしばしばカナダへ派遣し、セントローレンス川流域を探検させた。16世紀半ばには、この地はフランス領となった*。
*カナダの植民におけるフランスの活動の詳細については、日本ではあまり知られていない。しかし、リシュリューの時代にフランスが先駆けて新大陸、そして中国への道を模索していた事実は大変興味深く、近年新たな注目が集まっている。筆者ODが記憶の中を探し求めている例の文献には未だ出会えずにいるが、その後それをはるかに上回る内容の研究が行われており、記憶をリフレッシュする意味でも大分充足された気分だ。とりわけシャンプラン自身の旅行手記の出版、そしてピュリツアー賞受賞者の歴史家フィッシャーの大著は、従来のシャンプランおよびカナダ植民史を書き換えたといわれるほど多数の知見に満ちている。
Voyages of Samuel de Champlain 1601-1618. Ed. By J.F. Jameson, of the edition published by Charles Scribners’ Sons, New York, Elibron Classics,2005.an unabridged facsimile
David Hackett Fischer. Champlains Drream. New York; Simon & Schuster, 2007, pp.834.
さて、毛皮の原料とされたビーヴァーは、当初5大湖周辺の地帯、後には北西部で捕獲され、毛皮商人の手でヨーロッパ、とりわけパリへ持ち込まれた。パリでは主としてユグノー〔プロテスタント〕の帽子職人が1685年の「ナントの勅令」廃止で事実上追放されるまで製作にあたり、製品は国内ばかりでなく、ヨーロッパ諸国へ輸出された。
1608年、フランスの探検家サミュエル・ド・シャンプランは、セントローレンス川中流域に永続的なケベック植民地を創設した。フランスの目的は、インディアンとの毛皮交易の拠点を作ることにあった。とりわけ、ルイ13世の下で、宰相リシュリューはこの新大陸の植民構想に熱心であり、1627年には、ヌーベル・フランス会社を設立し、植民地経営を会社にゆだねた。当時、カトリック教徒以外の者が入植することは禁じられていた。
ヨーロッパからの探検家などが到達しない以前の北米大陸には、アメリカ・インディアン(ヨーロッパ人が、インド人と考えたことから)と呼ばれるようになった先住民がいた。彼らは実際には多くの種族に分かれていたが、その実態が判明するのは17世紀もかなり過ぎてのことである。実は、シャンプランがセントローレンス川流域の探検を行っていた頃よりはるか以前から、先住民族の語族・部族間には後に「ビーヴァー戦争」の名で知られることになる激しい種族・語族間の戦争が展開していた。シャンプランの探検隊は、たちまちその抗争に巻き込まれ、その力、とりわけ火縄銃の威力を利用されることになる。シャンプランは1608年夏の頃には、セントローレンス北岸のヒューロン族と南のイロコイ族との争いで、ヒューロン族側を支援していた。
戦闘は、1609年7月30日朝、シャンプレーン湖(後年、シャンプランの探検を記念して命名)のクラウンポイントと呼ばれる地点でイロコイ族と遭遇することで起きた。シャンプランはフランスの探検隊を率いて、イロコイ川(現在のリシュリュー川)を探検していた。この段階で、多いときは300人を越えていた探検隊だったが、フランス人と先住民のはとんどは逃亡し、60人になっていた。
先住民のグループが彼らを部族間闘争に利用しようとしていた。ふたつの対立する部族の兵士が湖畔で遭遇した時、シャンプランは手に火縄銃 arquebus を手にしていた。他の兵士は弓矢と盾という旧来の武器であり、相手方のモホーク族(イロコイ側の1部族)*は、それまで火縄銃など目にしたこともなかった。
*余談だが、モホークの名は、筆者の脳裏ではながらくニューヨークから5大湖地域をカバーした航空会社(モホーク航空)として残っていた。筆者はかなりの回数、搭乗したことがあり、懐かしい思いがする。1972年にアレゲニー航空(現在のUSエアウエイズの前身)が買収した。このセントローレンス川から5大湖周辺地域は先住民族やヨーロッパからの移住者の歴史をしのばせる多くの地名があって、きわめて興味深い。
両軍兵士がほぼ30メートルの距離で対峙した時、シャンプランはいきなり相手の隊長など戦闘の3人を火縄銃で射殺してしまう。モホーク族は大混乱を来し、戦闘は数分で終わってしまった。ちなみに、この時まで北米先住民は火縄銃の存在を知らなかった。発射の大音響とともに、たちまち3人の大物を射ち倒されてしまったインディアンは、驚天動地の驚愕で逃走したらしい。日本の1543年の種子島への火縄銃伝来よりもはるかに衝撃的であった。この1609年7月30日、シャンプランの一行と彼らを頼みとする部族(モンターネ族、アルゴンキン語族そしてヒューロン族)が宿敵のモホーク族の部隊と遭遇し、戦闘する場面は北米開拓史上きわめて注目すべき光景だ。これは、その後イロコイ族との間で100年続いた「フレンチ・インディアン戦争」の始まりとなった。

1609年サミュエル・シャンプランがモホーク族の首領目がけて火縄銃を発射、3人の男たちが倒れる場面。現在のアメリカシャンプレーン湖畔での出来事を描いた図。左側中央部で銃を構え、発射しているのがシャンプランと考えられる。Brook p30(原図はシャンプラン航海記から転載)。
世界史の大きな転換は、時に思いがけないことで起きる。この衝撃的な出来事はたちどころに北米先住民の間に拡大し、先住民族はなんとかこの新兵器を獲得したいと思うようになる。フランス、イギリスなどの探検隊はビーヴァー毛皮を入手するために、原住民に銃器を交換手段として渡すようになり、先住民間の戦いは一段と残酷なものとなる。
ブログで簡単に扱えるような問題ではとてもないのだが、その後毛皮交易で得られた収益は、まだ見ぬ中国への探検航海費用となる。後に、中国への道が開かれると、ペルー産の銀で鋳造された貨幣で、中国の陶磁器など珍しい産品が求められるようになる。17世紀オランダ絵画に、中国の陶磁器などが描かれるようになる背景でもある。フェルメールに限ったことではないが、一枚の絵も見方によって広い世界が見えてくる。ラ・トゥールについても、興味深い点が数多いのだが、しばらくゆっくり歩きたい(続く)。