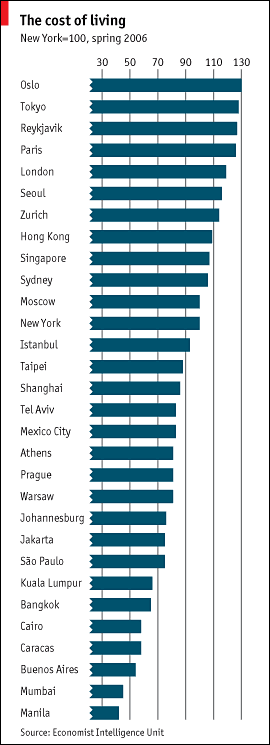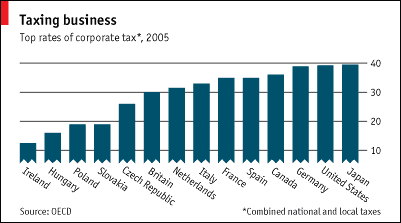Botticelli, The Annunciation (about 1490), Florence, Uffizi, Panel.
優れた画家とはいかなる資質を持った人なのだろうか。作品の優劣評価は、何によってなされるのか。これはきわめて本質的な難しい問題である。美術についての好み(taste)は、時代とともに変遷をとげてきた。時代を超越して好まれる作品があることはいうまでもないが、それぞれの時代を支配した主流があり、固有な「時代の目」ともいうべき評価の基準が存在すると考えられる。極端なことをいえば、ピカソやマティスの絵画が17世紀の西欧美術界に提示されたとしても、恐らく一顧だにされないだろう。
前回7月2日の記事でとりあげたが、15世紀イタリア絵画界における最も重要な変化は、画材の品質から画家の熟練・技量の質・水準重視への移行であった。
それでは、当時「時代の目」は、なにを基準としていたかということになるが、これはきわめて難しい問いで、とても容易に答は得られない。
「受胎告知」のテーマの具象化
ただ、以前から不思議に思っていたことがいくつかある。そのひとつは、15世紀イタリア絵画などに多数見られる「受胎告知」Annunciation(「ルカ福音書」1:26-38)というテーマの扱い方である。「受胎告知」は、神と人間の仲介を行う役割を担った大天使ガブリエルによる聖母マリアへのお告げというキリスト教においてはきわめて重要な主題である。大天使は、マリアに「あなたはみごもって男の子を産むでしょう。その子をイエスと名づけなさい」と告げる。キリスト教美術では、何度となく扱われてきた著名なテーマである。一人の画家が何点も描いていることも多い。世界に「受胎告知」を取り上げた作品がいったいどれだけあるのか、想像がつかない。
キリスト教史では、キリストの「托身」(神がキリストの姿をとること)は、この時に行われたと考えられている。従って、受胎告知の祝祭は、キリスト降誕からちょうど9ヶ月遡った3月25日に行われる。
作品を解く鍵の存在
大変興味があるのは、受胎告知を扱った作品はこのように数限りなくあり、ヴァリエーションも多いが、作品を見るものをして、あのテーマだと直感させる一定の約束事が含まれていることである。慣れてくると、作品に接した瞬間にすぐに分かる。
「受胎告知」における重要な3要素は、天使、聖母、そしてしばしば彼女に向かって降りてくる聖霊の鳩である。この主題は、ゴシック聖堂美術の中に最初に登場したと考えられている。興味を惹くことは、「受胎告知」の場面を描くにあたっての約束事がどのようにして生まれ、具象化され、美術界へ伝播していったのかという点にある。
「受胎告知」の時を描くに際しては、上記の3要素に加えて、象徴的な小道具、アトリビュートが付け加えられてきた。そのいくつかは、外典福音書および「黄金伝説」から採られたものである。たとえば、百合の花については、聖ベルナルドゥスは、この出来事が春に起こったことを強調しており、ここから花瓶に挿した花のモティーフが生まれ、後に百合となり、聖母の無垢の象徴へと展開してゆく。さらに、糸巻き棒、書物なども書き込まれている。大天使ガブリエルは翼をつけ、伝統的に白い衣をつけている。描かれている場所としては、ルネッサンス期には屋外の回廊あるいは中廊が設定されていることが多い。
主たる登場者である大天使ガブリエルと聖マリアの関係についても、興味ある点が見られる。多くの場合は、大天使は跪きお告げを奏上する姿勢をとり、聖マリアは直立して、真摯な表情で耳を傾けている構図がとられている。大天使や聖マリアの指先の仕草にも約束事がある。
画家の創意は
他方、フラ・アンジェリコのサン・マルコ美術館(フローレンス)のように、大天使は直立し、聖マリアが身をかがめるようにしてお告げを聞いている構図やボッティチェリの作品(フローレンス、ウフィツイ)のように、聖マリアが身をよじるように複雑な姿勢をとっている作品もある。これらは、一定の約束事の範囲で、画家が創意を発揮した部分である。
大天使と聖マリアが位置する空間にしても、大変古典的な印象を与えるドメニコ・ベネチアーノDomenico Venezianoの作品(about 1445, Cambridge, Fitzwillian Museum) のように 中間に遠くまで見通せる回廊を挟んで、両者の間に長く距離をとったものもある。他方、ウフィツイが所蔵するボッティチェリの作品のように、両者が近接し、指が触れ合いそうな構図もある。
しかし、いずれにせよ、「受胎告知」という主題について知識を持つ者にとっては、ほぼ瞬時に含意を読み取りうる工夫がこらされている。この一定の知識とは、言い換えれば優れた作品の鑑識力discriminationであるといえる。こうした知識は時と共に伝承され、社会に沈殿していった。画家とパトロンの関係からすると、この時代にこれらの鑑識力を持っていたのは、画家そしてパトロンとその周囲にある特定の人たちであった。社会的にも上流階級である。
一般民衆の水準まで、こうした知識が浸透するには多くの時間が必要であったと思われる。とりわけ宗教画が多かったことを考えると、この「時代の目」は、洗練された鑑識の力を蓄えたパトロンと画家などの芸術家の関係を軸に形成されていったのだろう。教会、修道院などが大きな役割を果たしたことはいうまでもない。その過程についても、さまざまな問いが浮かび上がり、興味は尽きない。
Reference
Michael Baxandall. Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy. second edition, Oxford University Press, 1972, 1988.