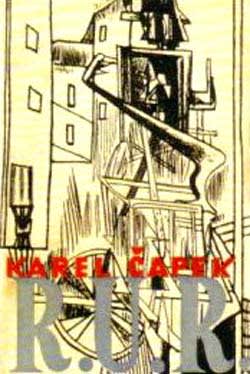カレル・チャペック、「RUR」への連想
奇妙な言葉の氾濫
少子・高齢化の予想を上回る速度での進行、「2007年問題」といわれるまでになった「団塊の世代」の大量退職、そしてついにやってきた「大学全入時代」。さらに、「フリーター」、「ニート」と他の国ではほとんど使われない言葉を多数の人が口にする日本はかなり奇妙な国である。
「フリーター」はメードイン・ジャパン
ある辞書の執筆にかかわった時に知ったのだが、実際、「フリーター」は日本製?なのだ。語源はどうやら、「フリー」と「アルバイター」を接合させたものらしい。これでは英語freeとドイツ語Arbeiterの接着である。「アルバイト」は、昨今では「バイト」である。ドイツ人もびっくりでしょう。他方、いまや知らないと常識を疑われそうな?「ニート」NEET(Not in Education, Employment or Training)の語源はイギリスといわれているが、しばらく暮らしたイギリスではほとんど聞いたことがなかった。イギリス人でも知っている人は少ないが、日本ではティーンエイジャーがニートで困っているという話を聞かされると、強いヘアローションと細かい櫛で髪をきちんと(ニート neat, 発音も異なる)固めている若者を思い浮かべるというから、かなりの落差がある*。
こうした状況で、日本から例のごとく視察団がやってきて、イギリスは「ニート」の先進国?だそうだがと聞かれれば、大変面食らうだろう(ちなみに、日本は視察団の大変好きな国である。「ニート」問題でも多数イギリスへ出かけたらしい。)
深刻なのは労働力不足
ところで、人口激減時代に入った日本では、最近は公表される失業率もやや低下し、これでフリーターやニートも救われると報じているメディアもあるが、とても手放しで喜ぶ気にはなれない。現実に起きていることは、これまで経験したことのない深刻な労働力不足の先駆けである。とりわけ、土木建設や介護に携わる労働者が不足するだけである。失業者が多くの職種について、大幅に減少するわけではない。多くの若者がフリーターや失業状態でありながら、その裏側では日本人が誰も働こうとしない職場が確実に増えて定着してしまった。そこでは多数の外国人が働いている。
すでに10年ほど前のことになるが、まだ不況から脱却していなかった頃、静岡県の浜松市で、フィールド調査をしていた時、ある小企業の経営者が嘆いていたことを思い出す。「日本人の若者は半日もいませんよ。それに比べて・・・」と彼が手で示した先には中東系と思われる若者が3人ほど、真剣な顔つきで、油まみれで小さな機械を動かしていた。バブルで見せかけの豊かさを経験してしまった日本人には、もう見られなくなってしまった顔であった。
先が見えない日本
なぜ、こんなことになってしまったのか。思い当たる点は多々ある。しかし、過ぎ去ってしまったことを嘆いてもしかたがない。日本はこれからどうやって労働力不足に対応していくのか。このごろの政府は、目先の問題に追われてか、日本の将来についての構想はほとんど示さなくなった。少子高齢化対策は、根本的なヴィジョンに欠け、部品の寄せ集めのような印象である。これで、出生率が目立って回復し、子供が増えるとはとても思えない(実際、その後10年近く経過しても、出生数は激減一方である。
移民かロボットか
労働力不足に対応する道のひとつとして国際的な場で提示されてきた政策のひとつに移民受け入れがある。国連人口部が提案した先進国の人口減を開発途上国からの移民で補充する案は、ほとんどまともに議論されることなく忘れ去られている。これは人口減少の数の点だけをみた提案ではあったが、それを契機に質を含めて、日本のあり方をもっと議論すべきであった。
外国人の受け入れを増やして共存の道を模索することは、最近のテロ事件などをみても、かなりけわしい道のりとなる。10年近くも住んでいて隣人と思っていた人たちが、事件を起こしたとなると、どの国も開放政策には二の足を踏む。しかも、実効ある選択肢は限られている。国民的議論が必要である。
RURの時代?
もうひとつの道は、ロボットに手助けをお願いすることである。世界ではおよそ80万台の産業用ロボット(アミューズメント・ロボットなどは除く、2003年末)*2 が稼働している。その内、実に34万8千台は日本で動いている。ドイツの11万3千台、アメリカの11万2千台をはるかにしのいでいる。しかも、1台で何人分もの仕事をこなしている。
日本は世界でも突出した「ロボット王国」である。ロボットにはニートもフリーターもいない。文句もいわずに昼夜を問わず働いている。いずれ「国勢調査」の人口にロボット人口?を数える時代が来るかもしれないと思うのは、炎天下でのあながち妄想ではない。「ロボット」という言葉を初めて使ったチェッコの国民的劇作家カレル・チャペックは、その名作「RUR」(ロッサム・万能ロボット製造会社、1920年)の中で登場人物に次のように云わせていた。
バスマン ははは、こいつはいいや! ロボットはなんのために作るのか、だってさ!
ファブリー 労働のために、ですよ、グローリーさん。一人のロボットは二人半前の働きをします。人間の労働者ってのはね。グローリーさん、恐ろしく不完全なしろものでした。早晩その地位から追われるべき運命にあったんですよ。
バスマン そのうえ費用ばかりかかってね。
ファブリー 能率的じゃなかったんです。人間の労働者はもう近代産業の要求には応じきれません。しかるに自然のほうでは近代的労働と歩調を合わせる考えなどすこしもありませんからね。たとえば、技術的見地からすれば子供時代なんてものはまったく愚の骨頂でね、えらい時間の浪費でしかありません。そしてまた――
カレル・チャペック「RUR」『海外SF傑作選 華麗なる幻想』所収(深町真理子訳)、講談社文庫
Reference
* Neet generation Education Guardian.co.uk
*2 International Federation of Robotics (IFR)
★ 2014年現在、「フリーター」も「ニート」もほとんど使われなくなった。もしかすると、意味も忘れられているかもしれない。