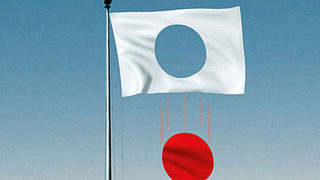梅雨時の夜半、17世紀の闇の世界、魔女審問の記録などを読んでいると、しばしば形容しがたい不思議な気分になる。およそこの世に本当にこんなことがあったのかと思われるような奇々怪々な話が出てくる。到底、箒に跨って空を飛ぶおとぎ話のような魔女の次元ではない。それでも、もしかすると現代の世界の方がはるかに怪しく不気味だと思うようなこともあり、興味は尽きない。格好の暑さしのぎかもしれない。
17世紀前半のロレーヌで魔術を操る者(魔術師 wizard, witch, )によって被害を受けたとされ、告発、審問などの対象になった案件では、牛、馬、豚、羊など、主として農民が飼育する家畜にかかわるものが最も多かった。農民たちが自分の飼育する牛や馬などが魔術師の妖術?によって、疫病に罹病したり、死んでしまったというような事例が非常に多い。そして、その原因をめぐって犯人捜し、魔女狩りが始まる。
当時でも明らかに家畜に伝染する疫病があったのだろう。人間の場合は疫病が流行し始めると、城門を閉じ、家の戸口も閉めて、自分の周りにバラの香りを振りまいたり、薬草を焚いたりして、「別の空間」を作り出すくらいがせいぜいだった。魔術師、healer と呼ばれる魔術による治療を勧める者などが跳梁する時でもあった。最近の口蹄疫問題などでの騒ぎをみると、医学的進歩で伝染予防、ワクチン注射など、対応はかなり変わったとはいえ、人間の行動様式は根底ではあまり変わっていないのではないかと思う部分もある。
さて、前回のブログに記したが、16世紀後半から17世紀前半にわたる近世前期といわれるこの時代、なぜ「魔女」といわれるように、女性の比率が高かったのか。そこには女性に対するなんらかの特別の要因が働いているのだろうか。
実は、この問題、現代における魔女研究でもきわめて大きな関心を集めているテーマだ。しかしながら、すでに遠く離れた時代、しかもきわめて異常な内容のジャンルであるために、納得できる答を出すことは非常に困難だ。迷信、妖術のたぐいが未だ広く蔓延していた近世初期の闇の次元、情報も不確かであった時代に形成された話の多くは、それ自体かなり怪しげな要素を含んでいる。審問の過程も不明な部分が多い。立証の資料も十分でなく、なぜ「魔女」が多かったのかを確定する統計的あるいは時系列分析も容易ではない。重要なことは最近の研究者たちが指摘するように「悪のジェンダー」探しをすることではなく、いかなる社会のどんな人たちが、どのような場合に、魔術を体現 bewitchmentする傾向があったかを探求することにある。
再三述べたように、こうした状況で、ロレーヌの魔女審問アーカイヴ(史料館)は、きわめて豊かな情報を含んでいる。しかし、ロレーヌの魔女裁判の研究者ブリッグスが認めるように、アーカイヴが充実すればするほど、その一般化が難しくなる面もある。多数の事例が蓄積され、事件の内容が多様化すると、中心的な課題を抽出することが難しくなる。ロレーヌでは他の地域で見られたような集中的な魔女狩りが行われた証はない。1620年代にひとつの事件で50人近い犠牲者を生んだ例があるが、むしろ例外であった。起こった時間と地域もかなり分散していた。
ブリッグスがその著書で取り上げている審問事例は、すべて男の魔術師が関わったものだ。その例を分析したかぎり、犯罪とされた基本要因には、魔術師が男だからあるいは女だからという男女のジェンダーに関わる特有の要因はなく、なににもまして怪しげな魔術を操った者(魔術者)としての行為が基本だとされている。魔術治療者 healer としての面でも、ジェンダー・レヴェルで区分線を引くことは難しいという。とはいっても性別の違いがまったくないわけではない。 男の魔術師はしばしば農民の収穫を損なう企てを行った者あるいは狼人間(werewolves 伝説で満月に狼に変身する人間)として登場している。
ブリッグスはいくつかの注目すべき点を挙げている。被疑者となった魔術師の多くは、長年、時には数十年にわたる魔術師としてのうわさや非難に基づいている。しばしば特定のうわさがある家族が対象となってきた。この点は、この時期の社会的コミュニティにおける噂や偏見の形成あるいは地域性、階層といった要因についても深く考える必要を示唆している。
ブリッグス が例示する、男女それぞれ96例について、魔術師が魔術をかけたとして告発された場合をみると、大変興味深いのは、馬、牛、豚などの家畜にかかわる問題が圧倒的に多く、人間については誰か(多くは成人)が病気(死亡を含む)に罹病したという事例が多い。しかも、ブリッグスが指摘するように、魔術師のジェンダーによる差異は少なく、多くの審問例について男女の魔術師がほぼ等しくかかわっている。しかし、魔術をめぐるジェンダー問題について、十分説得的であるとは思えない。継続して考えてみたい問題として残っている。
近世初期 early modern といわれるこの時代。1632年、ペストの大流行があった時代だが、1637年にはデカルトの『方法序説』が発表され、理性の光がヨーロッパに射した時でもある。ロレーヌに生まれ、ナンシー、パリなどで当時の新たな思想にも触れる機会が多かったと思われるジョルジュ・ド・ラ・トゥール、ジャック・カロなどロレーヌの知識層の精神世界の深奥がいかなるものであったか、興味が尽きない。
(続く)
Robin Briggs. 'Male Witches in the duchy of Lorraine.' Witchcraft and Masculinities in Early Modern Europe, Edited by Alison Rowlands. London:Macmillan palgrave, 2009.