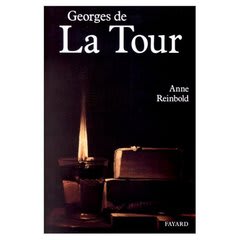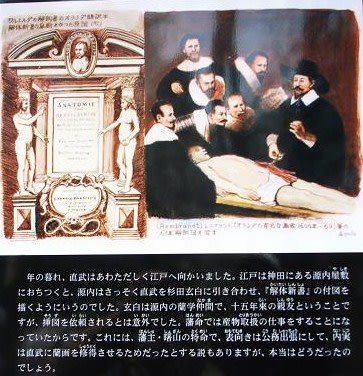Rembrandt van Rijn?. Self-Portrait, 1665
画家が自画像を描く時はなにを考えているのだろうか。10数年前のことになるが、ある国際会議のアトラクションとして、フローレンス、アルノ川に架かるヴェッキオ橋上の「ヴァザーリ回廊」の見学が組み込まれていた。通常はあらかじめ予約をとりつけておかないと入れない。得がたい機会だった。ヴァザーリ回廊は1565年に作られ、ピッティ宮殿をヴェッキオ宮殿と結ぶ特別の通路だった。
実際に見てみて驚いたのは回廊が予想外に長かったこと、そして多数の肖像画のコレクションであった。短時間で見るには、へきえきするほどの量だった。後に知ったのだが、ここの肖像画コレクションは世界最大級のものであった。
コレクションは、枢機卿レオポルド・デ・メディチによって1664年に始められた。現在では1630点に達し、西欧美術のおよそ6世紀をカバーしているといわれる。このコレクションの中から、芸術家が自らを描いた作品に限って厳選された50点が、ちょうど今ロンドンのダルウイッチ・ギャルリー Dulwich Picture Gallery で展示されている(「ウフィッツイからの芸術家の自画像」*)。
展示された作品には、ヴェラスケス、フィリッピノ・リッピ、ベルニーニ、レニ、カウフマン、ドラクロア、アングル、シャガールまで含まれている。晩年のレンブラント(1655)自画像も含まれている。もっともこの自画像の制作者が、レンブラント本人であるかはいささか議論もあり決着していない。よく知られているように、レンブラントは90点近い多数の自画像を画いており、それ自体がいわば自分史となっている。画家自らが記しているように、「私がどんな人間であったか、あなたは知りたいだろう」というレンブラントの考えがこれでもかとばかりに伝わってくる。少なくも、画家の生涯について考えるきわめて重要な手がかりが与えられている。
実は、このダルウイッチ画廊の歴史も大変面白い。フランス人、ノエル・デセンファンと若いスイス人の友人フランシス・ブルジョワの二人による画商としてスタートしている。それも、デセンファンの妻マーガレット・モリスの結婚持参金に頼ってのようだ。そして、1790年にポーランド王スタニスラス・オーガスタスからの注文で、「ポーランドの美術振興のために」、ゼロからの出発だが(イギリスのナショナル・ギャルリーのような)王室コレクションを創り出すという大仕事を請け負った。ところが、ポーランドは衰退を続け、1795年には独立国家としては消滅してしまった。王は退位し、画商は仕事半ばの収集品を手に放り出されてしまった。(スタニスラス王家については、ナンシーとの関係で以前に少し記したが)、画商がたどったその後の経緯も大変興味深い。後は画廊のHPをご覧ください。
*
“Artists’ Self-Portrait from the Uffizi”, Dulwich Picture Gallery, London, until July 15th.