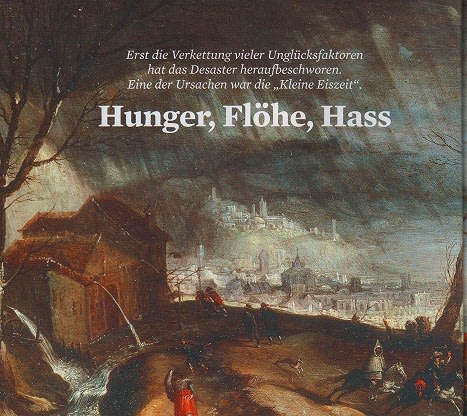記憶の中のランターンは、これよりずっと大きく赤銅色で輝いていた。
まだほんの10年くらい前のことのように思っていた。ある新聞記事*を読んでいると、その光景が脳のどこからか浮かび上がってきた。もう30年近い年月が過ぎていたのだ。
道路に置かれたランターン
青空がほとんど見えることなく、連日どんよりと曇った日が続いていた。寒気も厳しく、町も薄汚れた感じで活気がなかった。行きつけの書店があるチャリングクロス通り(古書店などが多い)も、人通りは少なかった。ある寂れた書店の前で、一見して労働者と思われる頑強な体躯の若者が2、3人、小さなプラカードを掲げてカンパを求めていた。前に置かれた段ボール箱には、わずかな貨幣と泥がついたままの野菜以外、ほとんどなにも入っていなかった。
1984年から85年にかけて、イギリスの全国炭鉱労働者組合(NUM; National Union of Mineworkers) が、サッチャー政権へ抗議するストライキが大きな話題となっていた。当時、政治ストは違法とされていた。彼らはどこかの炭鉱町からロンドンへ出て、カンパに頼りながら抗議運動を行っていたのだ。そして、こうした行為には、警官が巡回して追い払うか、拘束しているようだった。労働組合を経済・社会の改革を阻害する組織勢力として敵対視した「鉄の女」The Iron Ladyの意志は強かった。結局、85年に組合の敗退は決定的になった。1992年までに多数の「非効率な」炭鉱が閉鎖された。
カンパを募る箱の傍らに、見事な赤銅色に磨き上げられ、いかにも重そうな金属製の一個のランターン(坑内作業用の安全ランプ、デービー・ランプの名で知られる)が置かれ、小さくSaleと手書きされた紙が貼られていた。きっとこれまで毎日仕事が終わった後、入念に磨かれ、大切に手入れされていたのだろう。点灯されていたわけではないが、その重厚な存在感に、なにかあやしい魔力を秘めているかのように惹きつけられ、思わず見入ってしまった。
ひと目でかなりの風雪を経たものと思われ、それ自体が生命を宿しているかに思えるほどだった。もしかすると、炭鉱夫の家で親子代々受け継がれてきたものかもしれない。ランターンはピケットpickaxe (つるはし)とともに、炭鉱夫にとっては入坑の際の必携品であり、彼らにとっては命とも思われる道具ではないか。それを手放そうとしている。しかし、道行く人の誰も見向きもしていなかった。
思わずランターンの魔力に引き寄せられるかのように近づいた時、2、3人いた若者の誰かが短く口笛を吹いた。そのとたん、彼らは路上に置いてあったわずかな品物をつかむと、あっという間に立ち去ってしまった。その数秒後だった。2頭の馬に乗った警官が現れた。組合の活動を厳しく取り締まっていたのだ。しかし、若者たちの姿は視界にはなかった。
1984年はイギリス現代史の上で、「炭鉱争議の年」として記憶されている。その後、労働争議も労働組合員数も激減していった。
湧き上がったカウンター・カルチュア
ギリシャに端を発する世界的金融危機に、固唾をのむこの頃の世界だが、それでも今のロンドンは当時と比較すると、見違えるように明るくなった。人通りも多い。見事に再生を果たしたのだ。しかし、それは決して平坦な道ではなかった。
「鉄の女」の時代は、パンクロックなど数多くの「カウンターカルチュア」(反体制文化)を生み出した。地底からわき上がるような文化のうねりが、源だった。次々と新しい音楽、演劇、小説などが生まれていた。ビートルズはずっと以前(1970年)に解散していた。
天変地異が世界を揺るがしている今年、アメリカを含む多くの国で、政治への反発、不信が高まっている。新しい時代が生まれる前兆だろうか。
まもなく、マーガレット・サッチャーに、名女優メリル・ストリープが扮した映画「ジ・アイアン・レディ」The Iron Lady が公開されるとのこと。ブログにも記した『ソフィーの選択』 (1982年)、『めぐりあう時間たち』(2002年)以来のごひいきだ。どんなアメリカ版サッチャーとして現れるか、楽しみでもある。
この後、ある集まりで、サッチャーの話をしかけて、途中で止めてしまった。彼女のことは、誰も名前程度しか知らなかった。
* 『「マーガレット・サッチャーの復活:「ニューヨークタイムズ・マガジン」から』『朝日新聞』GLOBE、2011年10月16-11月5日、日本語版は抄訳。原記事は下載。
‘The Iron Lady as Anti-Muse’ The New York Times Magazine, September 23, 2011.
上記記事中のThe 6th Floor Blog のAntiーThatcher Song には改めて驚かされます。