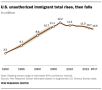前回、『アルノルフィーニ夫妻』像について記した時、確かどこかにあるはずだと思った一冊の研究書*があった。目につくところを探したが、直ぐには見つからなかった。これまでかなりの数の蔵書を涙を呑んで断捨離したり、ディジタル・ライブラリーに寄贈してきたので、あるいはと思ったが、幸い書棚の片隅に残っていた。『アルノルフィーニ夫妻像』は、かつてブログ筆者がイギリス滞在中、好んで通ったロンドン、ナショナル・ギャラリーが所蔵する至宝の一枚である。
*Carola Hicks, GIRL in a GREEN GOWN: The History and Mystery of the Arnolfini Portrait, Vintage, London, 2011
この作品、前回記したように、この時代には大変珍しく制作年が1434年と、画面の中心部に明記されている。テンペラではなく3枚のパネルに油彩で描かれた作品である。テーマとしても、中流階級の安らぎと一夫一婦婚の姿を描いたと思われる貴重な作品でもある。さらに、画家はこの作品に描きこまれたあらゆるものに全て意味を持たせたと思われる。画面を見ると、実に細々としたものが描きこまれている。しかし、15世紀の人々にはそれらが何を意味するものかは、暗黙のうちにも伝達され、かなり容易に理解されてきたと思われる。少なくも、何を意味するかを考える材料となっていた。しかし、長い年月が経過するうちに含意の内容は風化したり、忘れられて、現代人には理解できないものになってしまった。
描かれたのは誰だったのか
この絵を鑑賞する時にしばしば話題に上がる美術史家のエルヴィン・パノフスキー(1892-1968)は、この絵の制作年(1434)から500年後の1934年に図像学を駆使した画期的な論文を発表している。しかし、それで全て謎が解明されたわけではない。その後多くの研究が積み重ねられてきたが、上掲の美術史家カロラ・ヒックスの研究を見ると、謎はかえって深まった感じもする。カロラ・ヒックスはパノフスキーの時代には知られていなかった古文書などを掘り起こし、この謎の多い作品に新たな光を当てた。
それによると、これまでに解明されたと思われた事柄が、実は謎のままに残されていることが判明した。例えば、作品に書き込まれた制作年と思われる1434年の時点では、作品に描かれた夫妻と思われるジョヴァンニ・アルノルフィーニとジョヴァンナ・セナミは結婚していなかった。彼らが結婚したのは1447年であり、画家ファン・エイクの死後6年を経過した後のことであった。
そこで次の可能性が探求され、従兄弟のGeovanni di Nicholas Amolfiniと結婚したCosstanza Trentaではないかとの推定が行われた。彼らが結婚したのは1426年だったが、妻のコスタンザは、この絵画が制作された1年前の1433年に子供の出産時に死亡していたことが判明した。そうなると、描かれている女性はコンスタンツアか、夫が再婚した女性の婚約記念?なのかも分からなくなった。画家ヤン・ファン・エイク夫妻ではないかとの推定も行われている。こうした背景も考慮してか、今日のナショナル・ギャラリーは、作品の表題にThe Arnolfini Portrait と簡単に記している。
謎はこれだけに留まらず、次々と現れてきた。カロラ・ヒックスの研究書にはこの他にも多くの興味深い指摘・発見が含まれている。画家ヤン・ファン・エイクや、その作品、時代背景などに関心を寄せる人にとってはお勧めの一冊でもある。
この興味深い研究書の著者カロラ・ヒックスは、ケンブリッジ大学のキングス・コレッジのステンドグラスの研究(The King’s Glass: A study of Tudor Power and Secret Art, 2007)でも知られている。彼女はケンブリッジのニューナム・コレッジで20年以上、美術史を教えた。
ブログ筆者の専門は美術史ではないが、たまたまケンブリッジに滞在時に彼女の話を聞く機会があった。筆者もケンブリッジ近傍のイリー大聖堂の建築過程に関心を抱いていたので、大変興味深く記憶に残っている。惜しむらくは、カロラ・ヒックスは新著の刊行直前の2010年に世を去り、その後は夫の手によって遺稿が整理されて出版が実現した。
作品が辿った数奇な経路
この絵がブルッヘの持ち主の手を離れた後、ハプスブルグ家一族の所有を経て、フランダースからスペインの王室へ移り、その一隅に掲げられていた時もあった。ベラスケスも見る機会があったのではと考えられている。ナポレオン戦争の渦中でウエリントン公の軍隊によって没収され、スコットランド軍将校のコレクションに入った。その後、摂政皇太子に贈られたが関心を惹くことがなく、1842年にロンドンのナショナル・ギャラリーに600ギニアで買い取られた。その後一時はヒトラーの手に入ったこともあるらしい。その後、1991年からナショナル・ギャラリーに展示され、多くのファンが生まれることになった。この作品が辿った来歴 provenance についても未解明な点があり、カロラ・ヒックスの著書はその面でも興味深い点を指摘している。
カロラはパノフスキーなどの先行研究を再検討し、作品に描かれた鏡の周囲の装飾から、ブラッセル・グリフォンとして知られる足元の犬に至るまで、興味深い再検討を行っている。記述はこの作品の現代の美術や風刺画への影響まで及んでいる。例えば、鏡のアイディアはその後多くの画家によって、様々に導入されている。
改めて読み返すと時間を忘れる。断捨離されないで良かったねと、一冊の本の幸運を思った。